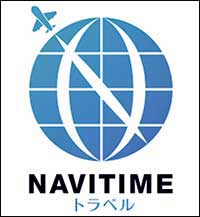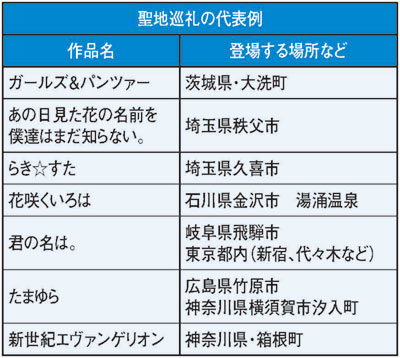第42回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」の投票が今年も10月1日から始まった。締め切りは10月末日。全国の旅行会社からの投票に基づき、「ホテル・旅館100選」と「観光・食事、土産物施設100選」および「優良観光バス30選」をそれぞれ選出する。「ホテル・旅館100選」の中間集計の1回目を紹介する。
(順不同)
【北海道】
あかん遊久の里鶴雅・あかん湖鶴雅ウィングス▽登別石水亭▽知床第一ホテル▽知床グランドホテル北こぶし▽十勝川温泉第一ホテル▽第一滝本館▽観月苑▽ニュー阿寒ホテル▽知床プリンスホテル風なみ季▽ホテル鹿の湯花もみじ▽ザレイクビュー TOYA 乃の風リゾート▽洞爺サンパレスリゾート&スパ▽HAKODATE海峡の風
【青森県】
ホテルグランメール山海荘▽星野リゾート青森屋▽海扇閣▽南田温泉ホテルアップルランド
【岩手県】
結びの宿愛隣館▽ホテル森の風鶯宿▽ホテル紫苑▽浄土ヶ浜パークホテル▽ホテル志戸平▽瀬美温泉▽悠の湯風の季▽グリーンピア三陸みやこ▽ホテル対滝閣▽愛真館▽南部湯守の宿大観▽長栄館
【宮城県】
ホテル松島大観荘▽伝承千年の宿佐勘▽鷹泉閣岩松旅館▽松島一の坊▽篝火の湯緑水亭▽鳴子観光ホテル▽ホテルニュー水戸屋▽ホテルきよ水▽名湯の宿鳴子ホテル▽岩沼屋
【秋田県】
結いの宿別邸つばき▽ホテル鹿角▽秋田温泉さとみ▽妙の湯▽鶴の湯▽駒ヶ岳グランドホテル
【山形県】
日本の宿古窯▽萬国屋▽蔵王国際ホテル▽天神の御湯あづま屋▽たちばなや▽八乙女▽月岡ホテル▽ほほえみの宿滝の湯▽河鹿荘▽仙峡の宿銀山荘▽游水亭いさごや▽蔵王四季のホテル▽深山荘高見屋▽おおみや旅館▽亀や▽高見屋別邸久遠
【福島県】
ホテル華の湯▽匠のこころ吉川屋▽八幡屋▽丸峰観光ホテル▽大川荘▽庄助の宿瀧の湯▽風望天流太子の湯山水荘▽スパリゾートハワイアンズ▽四季彩一力▽旅館玉子湯▽陽日の郷あづま館▽檪平ホテル
【茨城県】
五浦観光ホテル別館大観荘▽思い出浪漫館▽筑波山江戸屋▽大洗ホテル
【栃木県】
あさや▽花の宿松や▽鬼怒川グランドホテル夢の季▽鬼怒川温泉ホテル▽日光千姫物語▽ホテルエピナール那須▽ホテルサンバレー那須▽ホテルニュー塩原▽湯けむりの里柏屋
【群馬県】
草津白根観光ホテル櫻井▽四万やまぐち館▽源泉湯の宿松乃井▽舌切雀のお宿磯部ガーデン▽福一▽ホテル木暮▽旅館たにがわ▽万座温泉日進舘▽猿ヶ京ホテル▽別邸仙寿庵▽望雲▽草津ナウリゾートホテル▽奈良屋
【千葉県】
満ちてくる心の宿吉夢▽鴨川館▽鴨川ホテル三日月▽勝浦ホテル三日月▽鴨川グランドホテル▽宿中屋
【東京都】
水月ホテル鴎外荘
【神奈川県】
海石榴▽箱根吟遊▽強羅花壇▽ホテル河鹿荘▽強羅花扇
【山梨県】
銘石の宿かげつ▽ホテル鐘山苑▽ホテルふじ▽若草の宿丸栄▽全館源泉かけ流しの宿慶雲館▽湖山亭うぶや▽秀峰閣湖月▽下部ホテル▽華やぎの章慶山▽富士野屋夕亭
【長野県】
ホテル翔峰▽明神館▽旅館花屋▽上林ホテル仙壽閣▽藤井荘▽あぶらや燈千▽ホテル白樺荘▽立山プリンスホテル▽緑翠亭景水▽ホテルやまぶき▽ぬのはん▽白樺リゾート池の平ホテル▽RAKO華乃井ホテル▽白船グランドホテル▽昼神グランドホテル天心▽ユルイの宿恵山▽昼神の棲玄竹
【新潟県】
白玉の湯泉慶・華鳳▽ホテル清風苑▽水が織りなす越後の宿双葉▽夕映えの宿汐美荘▽風雅の宿長生館▽四季を彩る湯沢グランドホテル▽ゆもとや▽四季の宿みのや▽ホテル小柳▽ホテル摩周▽赤倉ホテル▽岬ひとひら▽大観荘せなみの湯
【静岡県】
稲取銀水荘▽堂ヶ島ニュー銀水▽いなとり荘▽季一遊▽ホテル九重▽ABBA RESORTS坐漁荘▽ホテルカターラRESORT&SPA▽柳生の庄▽観音温泉▽稲取東海ホテル湯苑▽桂川▽ホテル伊豆急▽ホテルサンハトヤ▽堂ヶ島温泉ホテル▽ホテルアンビア松風閣▽ホテルウェルシーズン浜名湖
【愛知県】
旬景浪漫銀波荘▽ホテル東海園▽ホテル竹島▽源氏香▽伊良湖シーパーク&スパ▽風の谷の庵
【三重県】
戸田家▽風待ちの湯福寿荘▽ホテル花水木▽サン浦島悠季の里▽鳥羽シーサイドホテル
【岐阜県】
水明館▽本陣平野屋花兆庵▽岐阜グランドホテル▽穂高荘山月▽ひだホテルプラザ▽ホテルくさかべアルメリア▽十八楼▽宝生閣
【富山県】
延楽▽金太郎温泉▽宇奈月国際ホテル▽ホテル立山▽延対寺荘▽宇奈月グランドホテル▽つるぎ恋月
【石川県】
加賀屋▽瑠璃光▽ゆのくに天祥▽日本の宿のと楽▽法師▽海游能登の庄▽辻のや花乃庄▽花紫▽お花見久兵衛▽ホテル高州園▽茶寮の宿あえの風▽花つばき▽たちばな四季亭▽みどりの宿萬松閣▽ゆ湯の宿白山菖蒲亭
【福井県】
まつや千千▽清風荘▽グランディア芳泉▽美松
【滋賀県】
びわ湖花街道▽里湯昔話雄山荘▽湯元舘▽琵琶湖グランドホテル京近江
【京都府】
松園荘保津川亭▽おもてなしの宿渓山閣
【兵庫県】
ホテルニューアワジ▽ホテル金波楼▽佳泉郷井づつや▽淡路インターナショナルホテルザ・サンプラザ▽西村屋ホテル招月庭▽有馬グランドホテル▽朝野家
【奈良県】
さこや
【和歌山県】
かつうら御苑▽ホテル中の島▽ホテル浦島▽白良荘グランドホテル▽紀州・白浜温泉むさし▽花いろどりの宿花游
【鳥取県】
皆生つるや▽華水亭▽依山楼岩崎▽皆生グランドホテル天水▽三朝薬師の湯万翆楼
【島根県】
玉造グランドホテル長生閣▽曲水の庭ホテル玉泉▽佳翠苑皆美▽白石家
【岡山県】
湯郷グランドホテル▽鷲羽ハイランドホテル▽八景▽清次郎の湯ゆのごう館▽ゆのごう美春閣
【広島県】
ホテル鴎風亭▽景勝館漣亭▽みやじまの宿岩惣
【山口県】
大谷山荘▽萩観光ホテル▽西の雅常盤▽錦帯橋温泉ホテルかんこう
【香川県】
湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭▽琴平グランドホテル桜の抄▽ことひら温泉琴参閣▽喜代美山荘花樹海
【徳島県】
和の宿ホテル祖谷温泉▽ホテルかずら橋
【愛媛県】
大和屋本店▽道後プリンスホテル▽宝荘ホテル▽ホテル椿館
【高知県】
土佐御苑▽城西館▽三翠園
【福岡県】
六峰館
【佐賀県】
和多屋別荘▽萬象閣敷島▽大正浪漫の宿京都屋▽大正屋▽和楽園
【長崎県】
東園▽ゆやど雲仙新湯▽雲仙宮崎旅館▽雲仙福田屋▽ホテル東洋館▽九州ホテル
【熊本県】
清流山水花あゆの里▽杖立観光ホテルひぜんや▽湯峡の響き優彩▽阿蘇の司ビラパークホテル&スパリゾート
【大分県】
九重悠々亭▽杉乃井ホテル▽ホテル白菊▽由布院玉の湯▽花菱ホテル
【宮崎県】
酒泉の杜綾陽亭
【鹿児島県】
いぶすき秀水園▽指宿白水館▽指宿海上ホテル▽霧島国際ホテル▽指宿フェニックスホテル▽霧島いわさきホテル▽城山観光ホテル▽霧島ホテル
【沖縄県】
カヌチャベイ&リゾート▽ホテル日航アリビラ▽沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ▽ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート