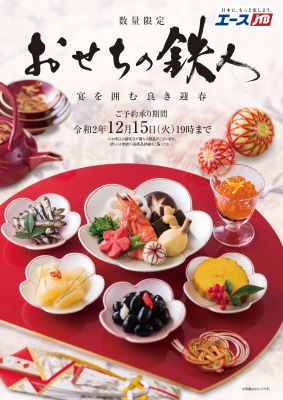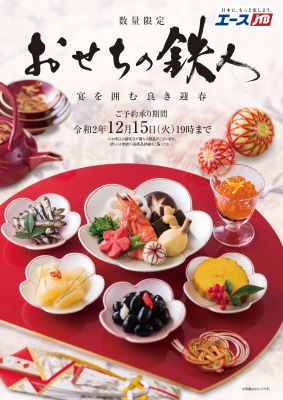2020年9月15日(火) 配信
-web.jpg)
JTB(山北栄二郎社長)で高品質旅行を専門に扱う「ロイヤルロード銀座」は9月7日(月)から、新商品「全国通訳案内士と旅をするプライベート英語ツアー」の受け付けを始めた。日本人のお客が、訪日外国人旅行者の目線で日本の魅力を再認識できる機会を提供する。
全行程に同行し、英語で案内を行うとともに日本語の補足説明を加える。英語のレベルはお客の希望に合わせるため、これから英語を学びたいシニアや語学留学を延期している学生なども参加しやすい。観光地や体験メニューは、事前に希望を確認する完全オーダーメイド制となっている。
「密を避けたい」というお客からの要望に対し、単独グループのプライベートツアーを実現。交通手段は、人数に合わせて同店保有の大型バス「ロイヤルロードプレミア」または提携会社のハイヤーを使用する。ロイヤルロードプレミアムは、通常45人乗りのスペースに客席10席を設置。全席窓側独立型シートを採用している。ハイヤー利用の際は、高級感のある黒塗りのアルファードクラスを手配する。
発着地は、お客の希望地からの発着が可能だが、「ロイヤルロードプレミアム」利用の際は制限がある。プランは、日帰りから手配可能となっている。
全国通訳案内士は、日本を訪れた外国人旅行者に対して、日本語以外の言語(英語、仏語、西語など)で観光案内するプロのガイド。だが、コロナ禍によって外国人旅行者が減少し、ガイドする機会が失われている。これらの状況を鑑み、今回のツアーが誕生した。
-web.jpg)



.png)
.png)


.jpg)
.jpg)