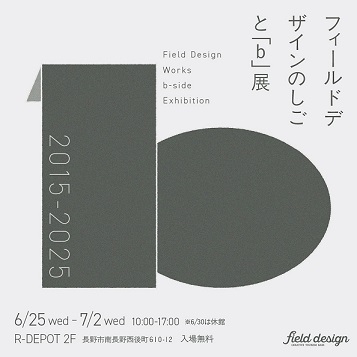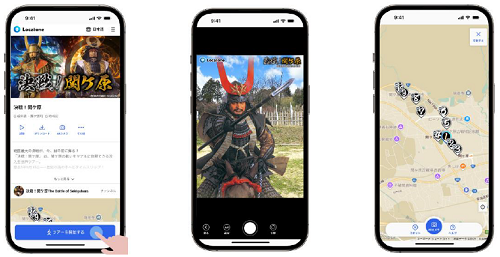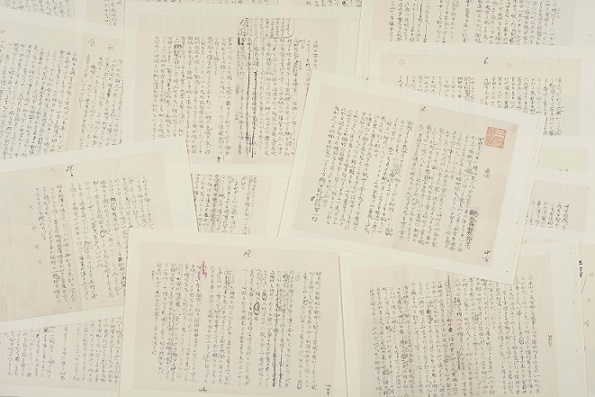2025年6月9日(月) 配信

東武トップツアーズ(百木田康二社長、東京都墨田区)は5月28日(水)、「バスタ新宿インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト協議会」と施設見学ツアーなどの実施に関する連携協定を結んだ。
バスタ新宿は、インフラツーリズムの拡大に向けて国土交通省が立ち上げた「インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト」のモデル地区として2024年4月に選定。バスタ新宿における社会実験としてインフラツーリズムを実施すべく、バスタ新宿インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト協議会から、連携協定事業者として同社が選ばれ、このほど協定を締結するに至った。
同社は協定締結を契機に今後、バスチケットや観光商材の一元的な販売システムの導入や、バスタ新宿の施設見学ツアーの実施をはじめとしたインフラツーリズムの拡大や地域活性化を進める。
具体的には、バスタ新宿の知られざる構造や仕組みを発見するインフラツアーの企画・実施や、インフラツアーを契機にバス会社や観光協会などとの連携による地方観光支援に取り組む方針だ。