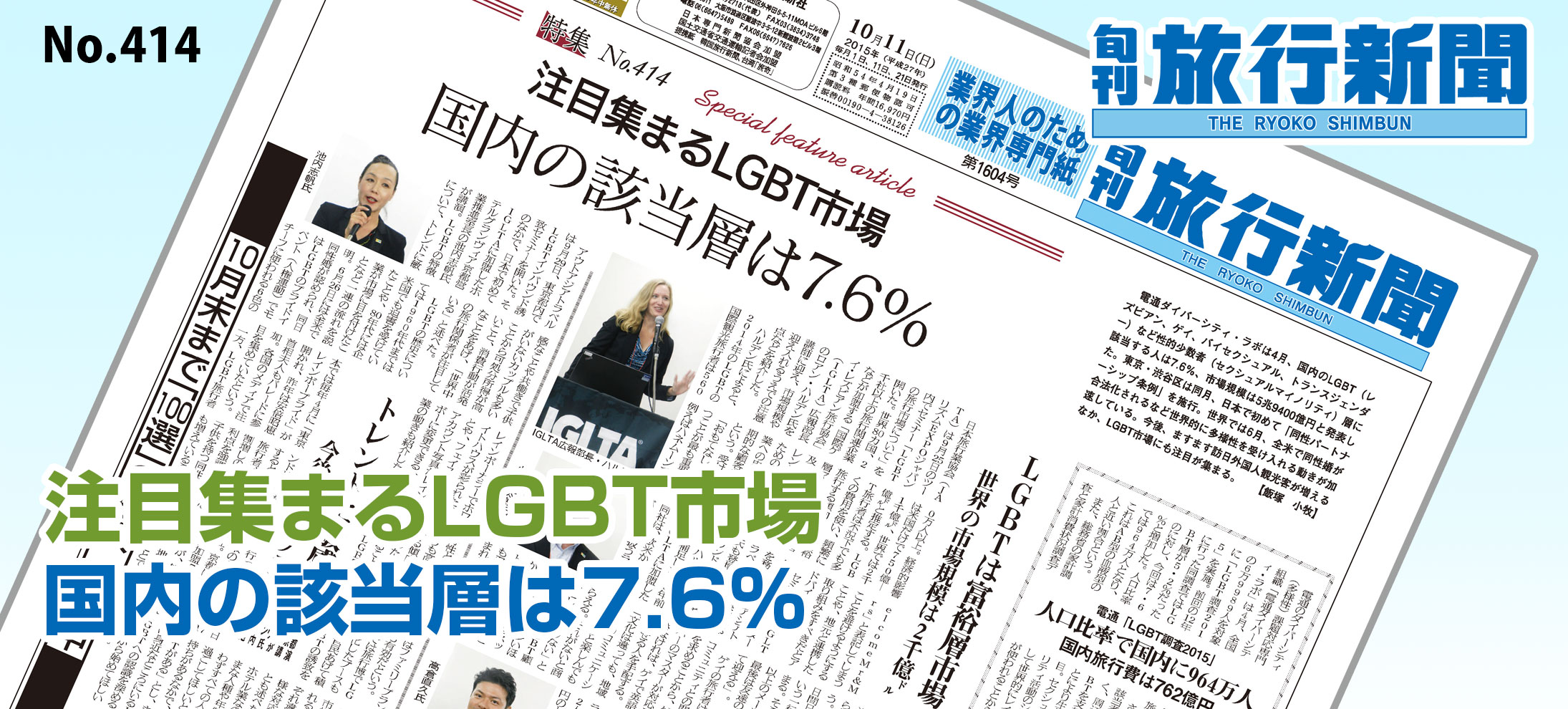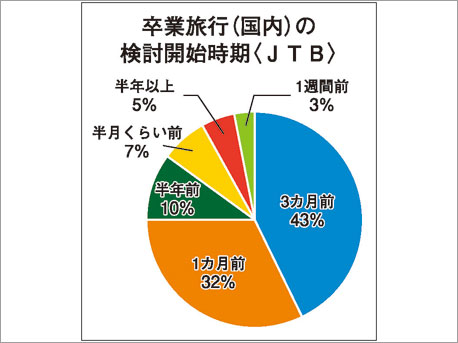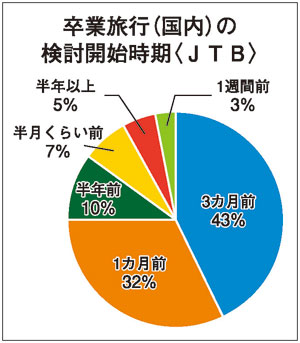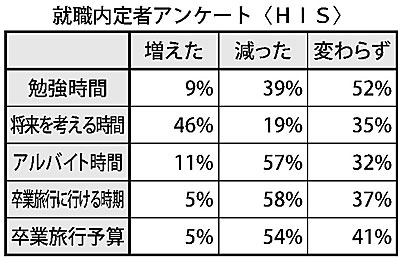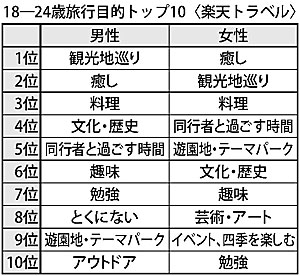第1種特別地域も地下部への傾斜掘削を認める――。環境省は2012年3月27日付の自然環境局長通知「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」の内容を見直し、10月2日付で新たに地方自治法に基づく技術的助言として、自然環境局長名で各都道府県知事宛てに通知した。
今回の改正の大きなポイントは、第1種特別地域については、これまでの通知では「地下部への傾斜掘削も認めない」としていたが、地表に影響がないことなどを条件に、「地下部への傾斜掘削を認める」としたところだ。ただし、特別保護地区は地下部も認めないことは変わらない。
建築物の高さ規制についても、「風致景観への著しい支障が回避され、風地景観との調和がはかられている場合に限り」という条件付きで、「13㍍にとらわれずに運用できることを明示する」とした。つまり、地熱発電の建物の規模に歯止めがなくなったことになる。
同省は今回の改正について、「自然環境と調和した地熱開発のより一層の促進をはかるための考え方などを整理し、優良事例形成の円滑化をはかることが目的」とし、今年3月から「国立・国定公園内の地熱開発に係る優良事例形成に関する検討会」を7月まで計4回開催。同検討会の最終回で得られた結論を踏まえ、各地方環境事務所長と、各都道府県知事宛てに新たな通知を行った。
12年3月27日付の通知では、(1)普通地域は個別に判断して認める(2)第2種、第3種特別地域は優良事例の形成について検証を行い、真に優良事例としてふさわしいものは認める。公園などからの傾斜掘削については個別に判断して認める(3)特別保護地区および第1種特別地域は認めない(傾斜掘削による地下利用も認めない)――などの内容に規制緩和されていた。
環境省によると、同検討会では優良事例の円滑な形成のためには、(1)開発の早期段階から、自然環境に配慮した立地選定の検討を実施(2)「立地選定段階」「建設段階」「操業段階」の各段階に応じた手法や、精度による環境配慮の取り組みが重要との結論も得られており、15年度末までに取りまとめる「通知の解説」で具体的に解説する予定という。これを受けて日本温泉協会は地熱対策特別委員会などと協議し、協会としての考え方を近く発表する予定だ。