2023年9月12日(火) 配信
ゆのくに天祥代表取締役社長 新滝 英樹(しんたき・ひでき)氏
ゆのくに天祥(新滝英樹社長、石川県・山代温泉)は今年6月、創業60周年を迎えた。コロナ禍で個人客に対応する客室や、食事処などの高付加価値化に取り組む一方、徐々に需要が戻りつつある団体旅行の需要取り込みにより、平日の稼動維持につなげる戦略だ。また、共有空間での過ごし方を重視し、社員からのさまざまなアイデアをかたちにしている。働きやすい職場環境へ、生産性向上やITを駆使して業務の省力化にも取り組む。北陸新幹線の福井敦賀への延伸を来春に控え、新滝社長に今後の宿の方向性などインタビューした。 【聞き手=編集長・増田 剛】
◇
――ゆのくに天祥の歴史を教えてください。
創業は1963(昭和38)年6月で、今年60周年の「還暦」を迎えることができました。
建築関係に携わっていた祖父が木造2階建て10室の旅館を開業したのが始まりで、その後、増改築を繰り返していきました。団体客中心に観光や宴会の需要が伸び、1980年代には90室500人収容規模となりました。
先代(父)も観光ブームのなか、88年には「加賀 伝統工芸村ゆのくにの森」をオープンさせるなど、業容を拡大していきました。
3代目となる私は、1995(平成7)年に宿に入りました。阪神淡路大震災が発生した年で、当時大阪で銀行勤務をしていました。
震災が宿に入るきっかけとなりましたが、大規模化していくなかでバブル崩壊後の財務的な課題も山積しており、これらの整理に注力していかなければならない状況にありました。
当時は団体旅行が中心で、小グループ化への兆しが現れている時期でした。団体自体も目的型へと変化しており、03年に新築した「天祥の館」は、全館48室が特別室で、また、大規模なコンベンションホールや宴会場も整備し、MICE需要も積極的に取り組んできました。
その後、マーケットの変化を見ながら、湯めぐりを楽しめる3つの大浴場や「天祥の館」の24室をスイート客室(うち12室を温泉露天風呂付き客室)にリニューアルし、特別フロアを新設、新たに自家源泉を開湯するなど、時代に合ったかたちで商品整備を進めています。現在は全156室(700人収容)です。
――コロナ禍ではどのような取り組みをされましたか。
当館がターゲットとしているファミリーのお客様の温泉露天風呂付き客室の需要が高まったため、22年には観光庁の「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」事業を活用して、「白雲の館(2号館)」24室を温泉露天風呂付き客室にリニューアルしました。
23年も同様に「高付加価値化」事業を活用して、「白雲の館(1号館)」16室を個人客向け客室に改修し、食事処なども整備する予定です。
コロナ前は、団体4:グループ2:個人4という割合でしたが、徐々に団体の割合が減少傾向にあります。
新型コロナが個人・グループ客中心に切り替えるきっかけになりました。スムーズに移行できたのは、コロナ前から食事処のリニューアルや、個人客に対応できるオペレーションの導入に取り組んでいたことも大きかったと思います。個人客への接遇のレベルアップを目指して、社員教育研修なども頻繁に実施しています。一方で、団体客の需要回復に向けた準備も整えています。
――高付加価値化に向けては。
施設、サービスの充実に加え、利用形態を問わず高付加価値化と単価アップも目指しています。
個人客はもちろんですが、「団体のお客様も個人客の集合」と捉え、これまで以上にご満足いただけるようなサービスの提供を目指しています。
個人客への対応を基本に、平日はグループや団体の需要を取り込んで、上手くバランスを取って稼働を平準化していきたいと思っています。
コロナ前に比べて客数が戻り切れていなくても、付加価値を高めることによって売上や収益率が改善するだけでなく、館内も落ち着いた雰囲気となります。お客様から「ゆったり過ごせた」という高い評価をいただくことも増えました。
――食事の提供方法に変化はありますか。
コロナ禍を機に、ビュッフェと部屋食をやめました。接触回避という面もありますが、ハード部分を改修していく過程で、パントリーなどもスタッフが提供しやすい“効率的なオペレーション”へと、細かく見直していきました。今は夕食も朝食も会席料理を提供しています。
また、食事会場のほとんどを2階に集約し、地下2階の厨房とパントリーがエレベーターで直結しているため、スタッフは横移動のみとなり負担が大幅に軽減しました。
従来はプラン数が多かった夕食は3プラン程度に絞り、素材の吟味と献立の工夫に努めています。団体の献立も個人客のメニューに準じたものを提供しています。
食事会場は、個室やグループ客で利用できるレストランなど多種多様です。ほかのお客様に気を使わなくてもよいように小さなお子様連れのファミリーを集めた食事処なども用意しています。朝食は「満足度を高めたい」と考え、品質を上げて統一し、評価は上がっています。
――生産性向上の取り組みについて。
デジタル化によって、フロントや調理のスタッフが、インジケーターで一元化した情報を共有しています。予約処理や各部課の手書き業務も、高度なデジタル化による自動化・省力化に取り組んでいます。
社内チャットの活用も進め、画像も含めて伝達がスムーズになりました。情報共有のためのミーティングが減ったことで、社員に好評です。お客様に褒められたコメントなどは全社員に共有し、モチベーションの向上にも貢献しています。
人手不足の問題もありますが、コロナ禍も一定程度採用を継続していたため、社員数は大きく変わっていません。IT化によりオペレーションが改善できた分、より丁寧なおもてなしに注力できるようになりました。生産性の向上へ業務改善を続けながら、働きやすい環境づくりにも取り組んでいます。
――旅館での過ごし方も工夫されていますね。
パブリックエリア(共有空間)での過ごし方はとても重視しています。試行錯誤を繰り返し、さまざまなアイデアをかたちにしています。具体的には、ロビーに午後3時から10時、朝は午前11時まで無料ドリンクコーナーを設けています。
温泉旅館らしさを出すために、「温泉」と「自家製」にこだわり、自家源泉を活用した蒸し饅頭や、調理部がゼリーやスイーツなどを作ってお客様に振る舞っています。
朝は温泉で蒸し立てのジャガイモやわらび餅、白玉ぜんざいなどの甘味もドリンクと一緒に楽しんでいただいています。
生たまごをネットに入れて、お客様自身が温泉たまごを作って召し上がっていただくことも、大変好評を得ています。お客様満足度が上がっているだけでなく、厨房スタッフもやりがいを感じてくれているようで、さらに進化させていきたいと考えています。
2023年6月、ゆのくに天祥は60周年を迎えた
――他館との差別化していく部分は。
おもてなしをどのように表現するかと考えたときに、「お客様を客室までご案内する」部分はしっかりと残していきたいという考え方です。
当館は導線がやや分かりにくいこともありますが、お客様との接点を保つために館内の色々な施設を客室までご案内しながら、滞在中の過ごし方などを説明しています。
――省エネへの取り組みや効果について。
東日本大震災後から環境負荷低減への取り組みを進めています。コロナ禍にも空調・熱源・LEDという3つの柱で省エネ投資を行いました。
BEMS(ビルエネルギ―マネジメントシステム)を導入し、館内のエネルギー使用状況をリアルタイムで把握できるように「見える化」しており、どこに問題が発生したかも即時にピンポイントで原因が分かるため、対応も迅速にできます。
――来春北陸新幹線が福井敦賀へ延伸します。
首都圏からのお客様は増えることが予想されますが、何よりも延伸効果を一過性ではなく、持続させていくことがとても大事です。地域の魅力の底上げや、商品の磨き上げが必要となります。
――今後の方向性について教えてください。
お客様へ良いサービスを提供するためにも、最前線で接客する社員が働きやすい環境づくりを第一に考えています。
お客様に満足していただくおもてなしこそが、ゆのくに天祥らしさを表現できる部分ですので、さらに強化していきたいと思っています。
一方で、地域全体の魅力がなければ、お客様を呼び込むことは難しい。山代温泉の温泉街も魅力アップに向けた整備も着々と進んでいます。
コロナ禍にも「温泉地全体を楽しみたい」というニーズを強く感じましたので、地域のイベントや事業と一体感を持たせて宿を運営するように心掛けています。
――ありがとうございました。
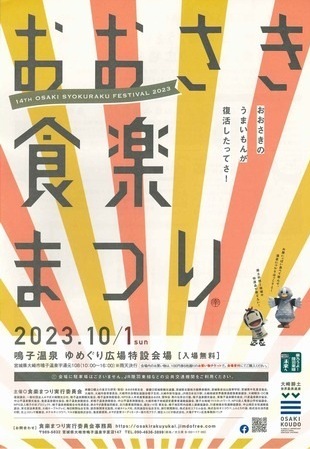



氏-1.jpg)





にオンラインで実施する.jpg)



.jpg)