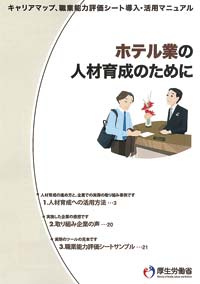
厚生労働省はこのほど、企業が人材育成に活用する「キャリアマップ」と「職業能力評価シート」の普及を進めるため、「導入・活用マニュアル」を、ホテル業など4業種で作成した。3月30日から、同省ウェブサイトの「職業能力評価基準」ページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/syokunou/index.html )で実際に活用した企業の取り組み事例と合わせて公開している。
同省は、企業が人材育成に取り組む際に職業能力を客観的に評価するため、業種ごとに「職業能力評価基準」を策定しているが、「キャリアマップ」と「職業能力評価シート」は、この基準をより簡単に利用できるように作成したツール。さらに今回は、そのツールのマップと評価シートを活用しやすいようにマニュアルを作成した。マップと評価シートの解説から、実際に導入して人材育成制度を整備する際のポイントと注意点など、人材育成の目的別に、事例も盛り込みながらまとめている。人材育成の目的は大きく(1)企業・職場の人材レベルの把握(2)階層別の人材育成(3)能力チェックの高度化(4)中途採用時の知識・技能レベルの把握――の4つに分けている。
なお、今回マニュアルを作成したのは、ホテル業のほかスーパーマーケット業と電気通信工事業、在宅介護業。




