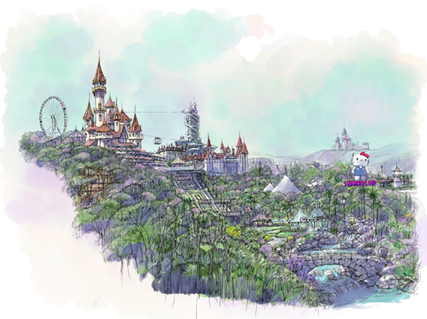2025年12月13日(土) 配信
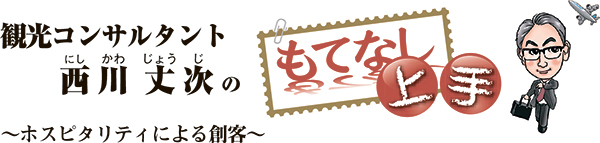
「あれ? 確かここに旅行会社の店舗があったはずなのに、気がついたら無くなっている」。そんな光景を目にすることがこの数年で多くなりました。
旅行会社の立地重視の営業には、大きなコストが伴います。そこで多くの店舗が路面店舗から空中店舗へと移動しました。同時に偶然から必然の来店を得るために、店舗を探してでも来てもらえる「旅行相談予約」システムを導入する企業も増えました。
しかし、ここで忘れてはいけない大切なことは、お客様が私たち企業の都合に合わせてくれているという事実です。ネットなら自宅で簡単に予約できる時代に、わざわざ時間を調整し、電車賃を払い、営業時間に合わせて来店してくださる。それは決して当たり前ではないのです。
せっかくの来店に大きな価値を感じてもらうことが重要です。お客様にとって予約制度のメリットは、事前に時間を決めて相談できるため、無駄な待ち時間を減らすことができる点にあります。さらに最近では、オンラインでの旅行相談を導入する企業も増えました。オンライン相談の大きなメリットは、専門性の高い担当者が対応できる点です。
しかし実際の運用を調査してみると、単に相談を受けているだけのケースが多く、制度を十分に生かし切れていません。どんなに丁寧に相談を受け親身に提案をしても、情報だけ取って予約は他社のサイトでというお客様も存在します。
そこで今後は、専門的なオンライン相談は予約者限定のサービスとする、あるいは有料相談として提供するなども検討すべきでしょう。
さらに、来店予約をいただいた段階で、「どんな旅行を望まれているのか」を丁寧に伺い、相談当日までにしっかり準備を整えることが、「旅行相談予約制度」を本当に価値ある仕組みにする最大の鍵です。
あるホテルでは予約サイトから宿泊予約後に、そのホテルから電話がかかってきました。内容は「このたびはご予約ありがとうございます。ご滞在中に何かお手伝いできることがあれば」という内容でした。宿泊前から歓迎されているという温かい印象を与えると同時に、事前にお客様の要望が分かっていれば、チェックイン日までに調べて対応することができます。
旅行会社でも、来店予約を受けた段階で、旅行の目的や希望をより詳しく聞き、相談当日までに最適な提案準備をする。その積み重ねが「またこの会社にお願いしたい」という信頼へとつながっていくのです。
大切なのは、限られた接点のなかで、いかに心を込めてお客様を迎えるかです。それが、これからの旅行会社の価値を決める時代になっています。
コラムニスト紹介

西川丈次(にしかわ・じょうじ)=8年間の旅行会社での勤務後、船井総合研究所に入社。観光ビジネスチームのリーダー・チーフ観光コンサルタントとして活躍。ホスピタリティをテーマとした講演、執筆、ブログ、メルマガは好評で多くのファンを持つ。20年間の観光コンサルタント業で養われた専門性と異業種の成功事例を融合させ、観光業界の新しい在り方とネットワークづくりを追求し、株式会社観光ビジネスコンサルタンツを起業。同社、代表取締役社長。
、JTBの森口浩紀取締役常務執行役員.png)



国土交通省関東地方整備局の山下副所長がバスタ新宿を説明した.jpg)