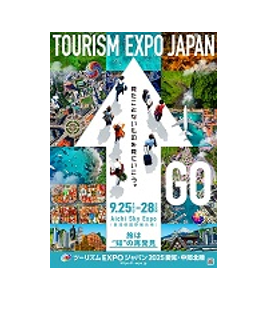2025年7月17日(木) 配信

ジョイポート淡路島(鎌田勝義社長、兵庫県南あわじ市)は淡路島から出航している「うずしおクルーズ」で8月9日(土)、「フルムーンナイトクルーズ」を実施する。通常は昼間しか運航していない「咸臨丸」で幻想的な夜の鳴門海峡に出航し、満月と生演奏の音楽を楽しむ。
日本百名月に選ばれている、鳴門海峡の名月は、無心で見とれてしまうほどの絶景という。淡路島は街の明かりが少なく、晴れていると月や多くの星が見られる。とくに、海上は周囲が暗く、透き通る夜空を眺めるには最高のスポット。同社は「満月と夜の海、さらにプロの音楽家による船上生演奏は、『この場所だからこそできる過ごし方』。都会の喧騒から離れ、日常をリセットし心と体を解き放つ時間、『記憶に残る夏の想い出』を旅先で届けたい、そんな想いから企画した」とアピールしている。
船内ではパソナグループ「音楽島₋Music Island」のメンバーによるバイオリンとピアノの生演奏を披露する。また、VIP席限定で、特別にシェフによるライブキッチンを用意。淡路牛のサーロインステーキを目の前で焼き上げる。
料金は自由席が中学生以上6000円、小学生3000円、幼児無料。淡路牛のミニカレーライスとウェルカムドリンクが船内で提供される。幼児はドリンクのみ。VIP席は中学生以上の参加で料金は1万5000円、先着14人まで。自由席と合わせた定員は100人。