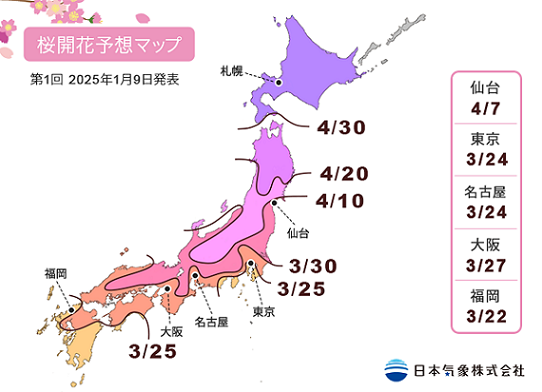2025年1月10日(金) 配信

日本旅行(小谷野悦光社長)は1月1日付の人事異動を発表した。
◇
【CS推進室】
西日本CS推進室長兼西日本お客様相談室長兼関西広報室長兼営業戦略本部(関西)マネージャー(TWILIGHT EXPRESS瑞風ツアーデスクマネージャー)佐々木幸枝
西日本CS推進室マネージャー兼西日本お客様相談室マネージャー兼CS推進室マネージャー兼お客様相談室マネージャー(国内旅行事業部担当次長)座間洋子
【ガバナンス推進部】
法務室長(西日本CS推進室長兼西日本お客様相談室長兼関西広報室長兼営業戦略本部〈関西〉チーフマネージャー)山本寛子
ガバナンス推進部チーフマネージャー(秘書広報部マネージャー兼デジタルイノベーション推進部マネージャー)宇野大悟
【秘書広報部】
秘書広報部マネージャー(秘書広報部主任兼デジタルイノベーション推進部主任)井出瑶子
秘書広報部マネージャー兼DX推進本部デジタルイノベーション推進部マネージャー(デジタルイノベーション推進部マネージャー兼総務人事部マネージャー)三宅佳広
【経営管理部】
経営管理部担当部長(経営管理部チーフマネージャー)三宅克行
経営管理部チーフマネージャー(経営管理部マネージャー)木原秀和
経営管理部チーフマネージャー(経営管理部マネージャー)弘中賢悟
【総務人事部】
総務人事部担当部長兼CSR推進室長(総務人事部担当部長)小野寺智弘
総務人事部マネージャー(総務人事部担当次長)白石亜美
日本旅行ビジネスクリエイトチーフマネージャークラス(日本旅行ビジネスクリエイト出向)北島直樹
【経理部】
経理部(中部駐在)チーフマネージャー(経理部〈中部駐在〉マネージャー)森下和一
経理部マネージャー(経理部担当次長)林大智
【DX推進本部】
デジタルイノベーション推進部担当部長兼ツーリズム事業本部WEB事業部担当部長(デジタルイノベーション推進部担当部長兼ツーリズム事業本部デジタルツーリズム推進部担当部長)佐野正樹
デジタルイノベーション推進部チーフマネージャー兼ツーリズム事業本部デジタルツーリズム推進部チーフマネージャー(デジタルイノベーション推進部マネージャー兼ツーリズム事業本部デジタルツーリズム推進部マネージャー)原井川寿美
【JR横断ソリューション本部】
企画部担当部長(西日本旅客鉄道地域まちづくり本部出向)松本佳恵
JCLaaS営業推進部チーフマネージャー(中国広域営業部〈岡山〉チーフマネージャー兼ビジネストラベル事業部チーフマネージャー兼MaaS事業推進部チーフマネージャー兼四国広域営業部チーフマネージャー兼JCLaaS営業推進部チーフマネージャー兼インバウンド事業部〈中四国〉チーフマネージャー)菅谷隼
TWILIGHT EXPRESS瑞風ツアーデスクマネージャー(TiS三ノ宮支店長)宇根裕美子
【事業共創推進本部】
事業共創推進本部副本部長(事業共創推進担当部長)本間恒志
グローバル人財活用推進チーム担当部長兼ガバナンス推進部担当部長(ガバナンス推進部担当部長兼CSR推進室長)若松英樹
日本ファームステイ協会マネージャークラス(事業共創推進部マネージャー)島岡忍
【グルーバル戦略推進本部】
NTA TRAVEL(SINGAPORE)PRIVATE LIMITED社長・副社長クラス(在外)(同マネージャークラス)細谷浩明
NTA TRAVEL(SINGAPORE)PRIVATE LIMITEDマネージャークラス(同主任クラス)久野克彦
【ソリューション事業本部】
企画部(青森駐在)チーフマネージャー(企画部〈大阪駐在〉チーフマネージャー)杉﨑勇一
企画部(大阪駐在)担当次長(公務法営担当次長)広瀬淳子
企画部チーフマネージャー(フレックスインターナショナルツアーズ出向〈西日本営業本部〉チーフマネージャークラス兼海外旅行推進部西日本チーフマネージャー兼BTN大阪発券センター副所長)迫謙一
事業統括部コーポレート事業部担当部長兼企画部担当部長(金沢支店長)宮本貴正
事業統括部ビジネストラベル事業部マネージャー(ビジネストラベル事業部主任)植松真吾
事業統括部教育事業部担当部長(教育事業部チーフマネージャー)今田誠
事業統括部公務・地域事業部マネージャー兼DX推進本部デジタルイノベーション推進部マネージャー(公務・地域事業部主任兼デジタルイノベーション推進部主任)白石慧介
事業統括部ビジネストラベル事業部東京ビジネストラベル支店長兼事業統括部ビジネストラベル事業部チーフマネージャー(東京ビジネストラベル支店長兼ビジネストラベル事業部マネージャー)船守剛
事業統括部ビジネストラベル事業部東京ビジネストラベル支店副支店長(東京ビジネストラベル支店課長)水谷喜預
【ソリューション事業本部首都圏広域営業部】
首都圏広域営業部担当部長兼東日本広域営業部担当部長(新潟支店長兼新潟教育支店長)番場太吉
東京法人営業部チーフマネージャー(東京法人営業部マネージャー)髙柴輝由
東京法人営業部マネージャー(東京法人営業部課長)石田好史
東京法人営業部マネージャー(東京法人営業部課長)永野里沙
新宿法人営業部チーフマネージャー(新宿法人営業部マネージャー)大信田貴則
訪日旅行営業部マネージャー(訪日旅行営業部課長)髙橋沙予
神奈川営業統括部長兼神奈川営業統括部神奈川法人営業部長兼神奈川営業統括部京浜法人営業部長兼首都圏広域営業部副部長(神奈川法人営業部長兼京浜法人営業部長兼首都圏広域営業部副部長)野田史郎
神奈川営業統括部副部長兼神奈川営業統括部神奈川教育支店長兼神奈川営業統括部神奈川法人営業部副部長(神奈川教育支店長兼神奈川法人営業部副部長)土肥野雅之
神奈川営業統括部神奈川法人営業部副部長(静岡支店長兼沼津営業所長)沼田篤寛
首都圏教育営業統括部長兼首都圏教育営業統括部東京教育営業部長(東京教育営業部長)富永高広
首都圏教育営業統括部副部長兼首都圏教育営業統括部東京教育営業部副部長(東京教育営業部副部長)矢嶋順
首都圏教育営業統括部東京教育営業部副部長(東京教育営業部課長)只隈修一
首都圏教育営業統括部埼玉教育支店長(東京多摩支店課長)金色成人
【ソリューション事業本部 東日本広域営業部】
東日本広域営業部(新潟駐在)マネージャー兼新潟営業統括部新潟支店副支店長(東日本広域営業部〈新潟駐在〉マネージャー)細貝菜穂子
甲府支店長(東日本広域営業部チーフマネージャー兼首都圏広域営業部チーフマネージャー)堀川浩二
甲府支店副支店長(甲府支店課長)原泰輔
高崎支店担当次長(埼玉教育支店長兼埼玉法人営業部副部長)岩井利光
高崎支店副支店長(長野支店課長)伴野大輔
新潟営業統括部長兼新潟営業統括部新潟支店長兼新潟営業統括部新潟教育支店長(甲府支店長)宮川隆明
新潟営業統括部新潟支店副支店長(長岡支店長)小森谷敦史
新潟営業統括部副部長兼新潟営業統括部新潟支店副支店長兼新潟営業統括部新潟教育支店副支店長(新潟副支店長兼新潟教育副支店長)清水大輔
新潟営業統括部長岡支店長(宇都宮支店長)本田浩
長野営業統括部長兼長野営業統括部長野支店長(長野支店長)尾形容之
長野営業統括部副部長兼長野営業統括部長野支店副支店長(長野支店副支店長)舟木健一郎
栃木営業統括部長兼栃木営業統括部宇都宮支店長(栃木支店長)岩松栄幸
栃木営業統括部副部長兼栃木営業統括部宇都宮支店副支店(宇都宮支店副支店長)仲田竜二
栃木営業統括部栃木支店長(神奈川法人営業部副部長兼神奈川教育支店副支店長)三村隆博
【ソリューション事業本部 中部広域営業部】
中部広域営業部マネージャー兼愛知営業統括部副部長兼愛知営業統括部愛知法人営業部副部長(中部広域営業部マネージャー)大野晃敬
愛知営業統括部長兼愛知営業統括部愛知法人営業部長兼名城大学コーナー所長兼大同特殊鋼知多営業所副所長兼大同特殊鋼星崎営業所副所長兼愛知営業統括部愛知東営業所長兼愛知営業統括部豊田営業所長(愛知法人営業統括部長兼愛知法人営業部長兼名城大学コーナー副所長兼大同特殊鋼知多営業所副所長兼大同特殊鋼星崎営業所副所長)竹井康三
愛知営業統括部愛知法人営業部副部長(東京法人営業部マネージャー)及部高義
愛知営業統括部愛知法人営業部担当次長(津支店副支店長兼伊勢支店長)国枝光隆
愛知営業統括部愛知法人営業部担当次長(愛知法人営業部副部長兼名城大学コーナー所長兼豊田営業所長)和田伸寿
静岡支店長兼沼津営業所長(東京教育営業部副部長)戸伏俊之
三重支店長兼三重支店伊勢営業所長兼三重支店四日市営業所長(津支店長兼四日市営業所長)福原渚
【ソリューション事業本部 北陸広域営業部】
北陸広域営業部マネージャー兼JR横断ソリューション本部JCLaaS営業推進部マネージャー(西日本旅客鉄道㈱北陸営業部福井営業出向)小板尚人
北陸広域営業部マネージャー(北陸広域営業部主任)山澤祐美
北陸営業統括部長兼北陸営業統括部金沢支店長(ソリューション事業本部企画部チーフマネージャー)渡邉義男
北陸営業統括部副部長兼北陸営業統括部金沢支店副支店長兼北陸営業統括部金沢教育支店長(金沢支店副支店長兼金沢教育支店長)松原一晃
【ソリューション事業本部 関西広域営業部】
関西広域営業部副部長兼MICE・インバウンド営業統括部関西インバウンド営業部副部長(関西広域営業部副部長兼関西インバウンド営業部副部長)櫛野孝史
関西広域営業部マネージャー兼万博推進室マネージャー(関西広域営業主任兼万博推進室主任)藤村七瀬
関西広域営業部マネージャー(関西教育営業部課長)吉田明日美
MICE・インバウンド営業統括部長兼MICE・インバウンド営業統括部西日本MICE営業部長兼MICE・インバウンド営業統括部関西インバウンド営業部長兼関西広域営業部担当部長兼MICE事業推進本部担当部長(関西広域営業部担当部長兼MaaS事業推進本部担当部長兼関西インバウンド営業部部長兼西日本MICE営業部長)木村雄一郎
MICE・インバウンド営業統括部副部長兼MICE・インバウンド営業統括部西日本MICE営業部副部長兼MICE・インバウンド営業統括部関西インバウンド営業部副部長兼関西広域営業部マネージャー(関西広域営業部マネージャー兼関西インバウンド営業部副部長兼西日本MICE営業部副部長)吉村直樹
MICE・インバウンド営業統括部関西インバウンド営業部マネージャー兼首都圏広域営業部訪日旅行営業部(関西駐在)マネージャー(関西インバウンド営業部課長兼訪日旅行営業部〈関西駐在〉課長兼関西広域営業部主任)劉昭
京滋営業統括部京都四条支店副支店長(京都四条支店課長)栗田槙也
京滋営業統括部長兼京滋営業統括部京都四条支店長兼JR横断ソリューション本部JCLaaS営業推進部チーフマネージャー(京都四条支店長兼JCLaaS営業推進部チーフマネージャー)青山啓二
京滋営業統括部副部長兼京滋営業統括部京都四条支店副支店長(京都四条支店副支店長)包昕蕾
阪奈和営業統括部長兼阪奈和営業統括部大阪法人営業部長(大阪法人営業統括部長)横出利之
阪奈和営業統括部副部長兼阪奈和営業統括部大阪法人営業部マネージャー(奈良支店長)江畑隆史
阪奈和営業統括部大阪法人営業部チーフマネージャー(大阪法人営業統括マネージャー兼訪日旅行営業部〈関西駐在〉マネージャー)大津宜也
阪奈和営業統括部奈良支店長(大阪法人営業統括部マネージャー)田中誠一
阪奈和営業統括部TiS和歌山支店長兼JR横断ソリューション本部JCLaaS営業推進部チーフマネージャー(神戸支店副支店長)小林薫
兵庫営業統括部長兼JR横断ソリューション本部JCLaaS営業推進部チーフマネージャー(神戸支店長兼JCLaaS営業推進部チーフマネージャー)速水栄司
兵庫営業統括部副部長兼兵庫営業統括部神戸支店副支店長(関西広域営業部マネージャー)福住光弘
兵庫営業統括部神戸支店副支店長(神戸支店課長)濱田理紗▽西日本旅客鉄道地域まちづくり本部マネージャークラス(TiS和歌山支店長兼西日本旅客鉄道㈱和歌山支社マネージャークラス兼JCLaaS営業推進部部マネージャー)前畑泰洋
【ソリューション事業本部 四国広域営業部】
四国広域営業部担当部長(米子支店長兼鳥取支店長兼JCLaaS営業推進部チーフマネージャー)由良浩二
四国東営業統括部長兼四国東営業統括部高松支店長(高松支店長)定金伸司
四国東営業統括部副部長兼四国東営業統括部徳島支店長(徳島支店長)曽我部友仁
四国西営業統括部長兼四国西営業統括部高知支店長(高知支店長)佐藤圭一郎
四国西営業統括部副部長兼四国西営業統括部高知支店副支店長(高知副支店長)松岡潤一
【ソリューション事業本部 中国広域営業部】
中国広域営業部(岡山駐在)マネージャー兼事業統括部ビジネストラベル事業部マネージャー兼MaaS事業推進本部マネージャー兼四国広域営業部マネージャー兼インバウンド事業部(中四国)マネージャー(おとなび・ジパング商品センター所長兼JR横断ソリューション本部マネージャー)谷道洋介
広島営業統括部長兼広島営業統括部広島支店長(広島支店長)蓑崎功一
広島営業統括部副部長兼広島営業統括部岩国支店副支店長(九州統括マネージャー)大上修司
広島営業統括部広島支店副支店長(広島教育課長)冨永恭兵
岡山支店長兼JR横断ソリューション本部JCLaaS営業推進部チーフマネージャー(岡山支店長兼岡山教育支店長)宮地洋樹
山陰営業統括部長兼山陰営業統括部米子支店長兼JR横断ソリューション本部JCLaaS営業推進部チーフマネージャー(広島教育支店長兼広島副支店長)坂本修一
山陰営業統括部副部長兼山陰営業統括部鳥取支店長(米子支店副支店長兼鳥取支店副支店長)桑谷義人
【ソリューション事業本部 九州広域営業部】
九州広域営業部副部長(九州法人営業部長兼九州広域営業部チーフマネージャー)石本信二
九州広域営業部担当部長兼総務人事部(九州駐在)担当部長(長崎支店長兼九州広域営業部チーフマネージャー)内野弘樹
九州広域営業部(宮崎駐在)担当部長兼宮崎営業統括部副部長(宮崎支店長兼九州広域営業部チーフマネージャー)橋村康弘
九州営業統括部長兼九州営業統括部九州法人営業部長(九州法人営業部マネージャー兼ビジネストラベル事業部〈福岡駐在〉マネージャー)髙橋宏聡
九州営業統括部九州法人営業部マネージャー(九州法人営業部課長)河本大樹
九州営業統括部副部長兼九州営業統括部九州法人営業部マネージャー(北九州支店課長)坂井貴彦
長崎支店長(九州法人営業部マネージャー兼大分支店副支店長)吉岡孝治
宮崎営業統括部長兼宮崎営業統括部宮崎支店長(延岡支店長)工藤真吾
宮崎営業統括部延岡支店長(大分支店課長)室住良
【ツーリズム事業本部】
企画部担当部長(JR横断ソリューション本部JCLaaS営業推進部チーフマネージャー兼ジパングプラザチーフマネージャー)森本敬太
企画部(中部・北陸担当中部駐在)担当部長兼Web事業部中部Webセンター支店長(企画部〈中部・北陸担当中部駐在〉担当部長)吉川泰史
デジタルツーリズム推進部担当部長(アライアンスマーケティング推進部長兼ダイレクトマーケティング事業部長兼ICT営業推進部長兼エリア営業推進部長)西尾昭一
デジタルツーリズム推進部(関西駐在)マネージャー(西日本旅客鉄道環境経営室出向)塚越美由紀
デジタルツーリズム推進部チーフマネージャー兼DX推進本部IT部チーフマネージャー(ICT営業推進部チーフマネージャー兼DX推進本部IT部チーフマネージャー兼デジタルツーリズム推進部チーフマネージャー)武田理恵
Web事業部長兼国内旅行事業部担当部長(国内旅行事業部担当部長)金澤裕司
Web事業部チーフマネージャー(ICT営業推進部チーフマネージャー)盛満佳久
Web事業部マネージャー兼DX推進本部デジタルイノベーション推進部マネージャー兼エリア営業部マネージャー兼デジタルツーリズム推進部マネージャー(ICT営業推進部マネージャー兼DX推進本部IT部マネージャー兼エリア営業推進マネージャー兼デジタルツーリズム推進部マネージャー)冨永紘一郎
Web事業部マネージャー兼DX推進本部デジタルイノベーション推進部マネージャー(ICT営業推進部マネージャー兼DX推進本部デジタルイノベーション推進部マネージャー)稲葉典子
Web事業部東日本Webセンター支店長(システムトラベルセンター副支店長)原田政和
Web事業部東日本Webセンター副支店長(ICT営業推進部マネージャー兼デジタルイノベーション推進部マネージャー)小野大輔
Web事業部西日本Webセンター支店長兼エリア営業部関西統括部TiS梅田支店副支店長兼デジタルツーリズム推進部(関西駐在)マネージャー(メディア・アライアンス・トラベル営業部マネージャー兼メディアトラベルセンター副支店長兼関西統括部マネージャー兼デジタルツーリズム推進部〈関西駐在〉マネージャー)前田千春
Web事業部西日本Webセンター副支店長兼エリア営業部関西統括部TiS梅田支店長兼メディア・アライアンス・トラベル営業部副部長(メディア・アライアンス・トラベル営業部担当次長)阪田修
Web事業部九州Webセンター副支店長(九州個人旅行営業部副部長)宗裕美
エリア営業部長(東日本統括部長兼システムトラベルセンター支店長)梅村千尋
東日本統括部長(企画部チーフマネージャー)東海林勉
新浦安支店長兼東日本統括部マネージャー(新浦安支店長兼市川センターモール支店長)久保勝宏
イオンモール浦和美園支店担当次長(浦和コルソ支店担当次長)北島花陽
東日本エージェント支店長兼東北エージェントセンター所長兼大学生協事業連合内エージェントセンター所長兼エリア営業部マネージャー兼北海道チケットセンター所長(東日本エージェント支店副支店長兼旭化成内旅行コーナー所長兼アライアンスマーケティング推進部マネージャー)中村圭吾
東日本エージェント支店副支店長兼東日本統括部マネージャー(首都圏広域営業部〈埼玉駐在〉主任兼東日本広域営業部〈埼玉駐在〉主任)後藤敬子
東日本エージェント支店副支店長兼旭化成内旅行コーナー所長兼エリア営業部マネージャー(東日本エージェント支店課長兼システムトラベルセンター課長)田中謙一
金沢八景支店長(東京統括支店〈パルコヤ上野支店〉長)西村ひろみ
横浜ポルタ支店担当次長(新宿法人営業部担当次長)野口昌美
横浜ポルタ支店長(金沢八景支店長)松田翔太
横浜ポルタ支店担当次長(市川センターモール担当次長)渡邉新吾
都庁内支店長兼エリア営業部東日本統括部チーフマネージャー(東日本エージェント支店長兼東北エージェントセンター所長兼大学生協事業連合内エージェントセンター所長兼アライアンスマーケティング推進部チーフマネージャー兼北海道チケットセンター所長)齋藤忍
市川コルトンプラザセンターモール支店長(横浜ポルタ支店長)新屋万智子
東京統括支店(パルコヤ上野支店)長(システムトラベルセンター副支店長兼東京予約センター所長兼東日本統括部マネージャー)下野貴子
TiS金沢支店長兼MaaS事業推進本部マネージャー(名古屋予約センター所長兼中部エージェント支店副支店長)大東理江
関西エージェント支店長兼メディア・アライアンス・トラベル営業部副部長兼関西統括部マネージャー兼大阪東野田町営業所長兼大阪府旅行業協会内営業所長兼大阪旭化成内旅行コーナー所長(関西エージェント支店長兼アライアンスマーケティング推進部マネージャー兼メディア・アライアンス・トラベル営業部マネージャー兼関西統括部マネージャー兼大阪東野田町営業所長兼大阪府旅行業協会内営業所長兼大阪旭化成内旅行コーナー所長)八津裕子
メディア・アライアンス・トラベル営業部副部長兼MaaS事業推進本部マネージャー(メディア・アライアンス・トラベル営業部課長兼関西エージェント支店課長兼アライアンスマーケティング推進部主任)米森達哉
TiS京都西口支店長兼TiS京都支店長兼TiS高槻支店長兼関西統括部チーフマネージャー(TiS金沢支店長兼MaaS事業推進マネージャー)佐伯美里
TiS大阪支店長兼TiS京橋支店長兼関西統括部チーフマネージャー(TiS京都西口支店長兼TiS京都支店長兼TiS高槻支店長)神田路子
TiS大阪支店副支店長兼あまがさきキューズモール支店長(TiS梅田支店長兼あまがさきキューズモール支店長)中谷良輔
TiS天王寺支店長兼シャープ内旅行コーナー所長(TiS大阪支店副支店長)松田佳子
TiS三ノ宮支店長兼関西統括部チーフマネージャー(TiS天王寺支店長兼シャープ内旅行コーナー所長)清水幸子
広島エージェント支店長兼Web事業部中国Webセンター支店長兼中国統括部副部長兼エリア営業部チーフマネージャー(広島エージェント支店長兼中国統括部担当部長兼アライアンスマーケティング推進部チーフマネージャー兼広島予約センター所長)水野千佐子
中国統括部長兼九州統括部長兼四国統括部長兼MaaS事業推進本部担当部長兼九州CS推進室室長兼九州お客様相談室室長(中国統括部長兼九州統括部長兼MaaS事業推進本部担当部長兼九州CS推進室室長兼九州お客様相談室室長)中田森之
九州エージェント支店長兼九州Webセンター支店長兼九州統括部副部長兼九州CS推進室マネージャー兼九州お客様相談室マネージャー(九州個人旅行営業部長兼九州統括部副部長兼九州CS推進室マネージャー兼九州お客様相談室マネージャー)吉沢美香
笹丘支店長兼佐賀大和支店長(高の原支店長)白濱功志
国内旅行事業部(関西駐在)担当部長(TiS大阪支店長兼TiS京橋支店長)大西さゆり
国内旅行事業部チーフマネージャー(関東企画仕入センターチーフマネージャー)高橋賢
国内旅行事業部チーフマネージャー兼DX推進本部デジタルイノベーション推進部チーフマネージャー兼デジタルツーリズム推進部チーフマネージャー(国内旅行事業部マネージャー兼DX推進本部デジタルイノベーション推進部マネージャー兼デジタルツーリズム推進部マネージャー)石田和誠
国内旅行事業部マネージャー(伊豆箱根企画・仕入センター所長兼東日本広域営業部マネージャー)大野義樹
国内旅行事業部マネージャー(国内旅行事業部担当次長)岩崎秀一朗
北海道企画・仕入センター所長(国内旅行事業部チーフマネージャー兼MaaS事業推進チーフマネージャー)菅司
関東企画・仕入センターチーフマネージャー(北海道企画・仕入センター所長)近藤淳
伊豆箱根企画・仕入センター所長兼ソリューション事業本部東日本広域営業部マネージャー(国内旅行事業部マネージャー)多治見則子
北陸企画・仕入センター所長兼ソリューション事業本部北陸広域営業部チーフマネージャー(北陸企画・仕入センター所長兼ソリューション事業本部北陸広域営業部マネージャー)真崎裕代
関西企画・仕入センターマネージャー(関西企画・仕入センター主任)入江有香
山陰企画・仕入センター所長(山陰企画・仕入センター主任)田中裕美子
山陽企画・仕入センターマネージャー(山陽企画・仕入センター主任)音田大介
おとなび・ジパング商品事業部長兼おとなび・ジパング商品センター所長(おとなび・ジパング商品部長)武藤明道
おとなび・ジパング商品事業部マネージャー(企画部マネージャー兼都庁内支店)樗澤篤
おとなび・ジパング商品センターマネージャー兼コンテンツ開発チーム(関西駐在)マネージャー兼デジタルツーリズム推進部(関西駐在)マネージャー(おとなび・ジパング商品センター主任兼コンテンツ開発チーム〈関西駐在〉主任兼デジタルツーリズム推進部〈関西駐在〉主任)森田達矢
フレックスインタ-ナショナルツアーズチーフマネージャークラス兼海外旅行推進部(西日本駐在)チーフマネージャー兼BTN大阪発券センター副所長兼DX推進本部デジタルイノベーション推進部チーフマネージャー(フレックスインタ-ナショナルツアーズマネージャークラス兼DX推進本部デジタルイノベーション推進部マネージャー)桐山佳恵
フレックスインターナショナルツアーズ本社チーフマネージャークラス兼海外旅行事業部チーフマネージャー(フレックスインターナショナルツアーズ出向〈東日本営業本部駐在〉)宮方智広
フレックスインタ-ナショナルツアーズマネージャークラス(フレックスインターナショナルツアーズ出向〈西日本営業本部駐在〉)山田美由紀