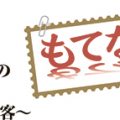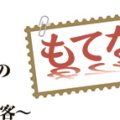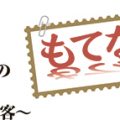「もてなし上手」~ホスピタリティによる創客~(173) 忘れ物のその先にある「おもてなし」の本質 「困る人を生まない」声掛け
2025年6月15日(日) 配信
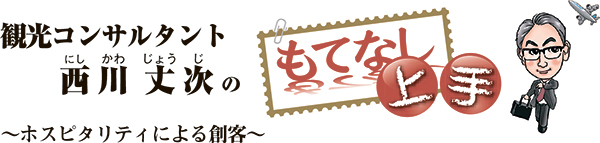
宿泊後の新幹線で移動するとき、「あれ、スマホの充電器がない」。そんな経験は、どなたにでもあるのではないでしょうか。気を付けていたはずなのに、気づいたときには「しまった!」と焦ったり、落ち込んだり……。それが楽しい旅の途中であれば、なおのことです。
多くのサービス提供者は、こうしたトラブルを減らすために「お忘れ物はありませんか」と声掛けをしています。しかし、そのひと言だけでは、人の行動はなかなか変わりません。
かつて海外に旅行される方々の多くが、パスポートなど貴重品をセイフティボックスに預けていました。朝、バスに乗って最初に多くの添乗員が話すことは「忘れ物はありませんか」でした。それでも空港に着いてから「セイフティボックスから取り出し忘れた」という声が少なくなかったのです。
そこで具体的に「セイフティボックスからパスポートは取り出されましたか」と案内します。しかし、うん、うんと頷かれていた方であっても、忘れ物に気づかなかったケースが多々ありました。
私自身が添乗員をしていたときに注意していたことがありました。バスに乗ったら「皆さん、パスポートはお持ちですね? 念のために、今、手に取り出して私に見せて下さい」と呼び掛けました。
「持ったつもり」の失敗を多くした経験から、何度もカバンから書類や財布を取り出して目で確認することをしていました。それを添乗業務時に生かしていたのです。
「忘れ物にご注意ください」と色々な場所で声を掛けられますが、ただのマニュアル上の言葉で終わっていては意味がありません。声を掛けることが仕事なのではなく、「困る人を生まない」ことが目的です。おもてなしとは、本来そうあるべきものなのです。
あるホテルでチェックアウトのためにエレベーターを待っているとき、ふと壁を見ると、目線の高さに「忘れ物はございませんか?」という案内が貼られていました。そこには、忘れやすい場所(枕の下、洗面所、机の上など)や、よくある忘れ物(ピアス、切符、携帯電話、充電器など)が、分かりやすいイラストとともに描かれていました。
その案内を見たとき、私は思わず自分のバッグの中を確認しました。さりげなく気づかせてくれるところに、このホテルの「おもてなしの哲学」が滲み出ていたように思います。人は注意されたから気を付けるのではなく、「自分に関係あること」と感じたときに、初めて行動が変わるのです。
忘れ物を防ぐという小さな行動の中にも、大きなおもてなしの精神が宿っていたと感じた事例です。
コラムニスト紹介

西川丈次(にしかわ・じょうじ)=8年間の旅行会社での勤務後、船井総合研究所に入社。観光ビジネスチームのリーダー・チーフ観光コンサルタントとして活躍。ホスピタリティをテーマとした講演、執筆、ブログ、メルマガは好評で多くのファンを持つ。20年間の観光コンサルタント業で養われた専門性と異業種の成功事例を融合させ、観光業界の新しい在り方とネットワークづくりを追求し、株式会社観光ビジネスコンサルタンツを起業。同社、代表取締役社長。