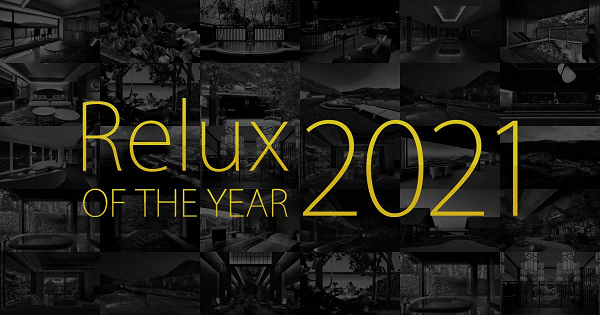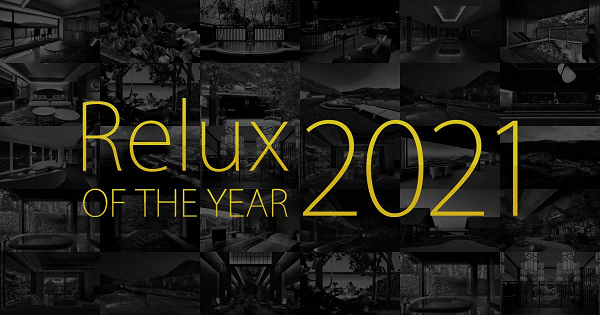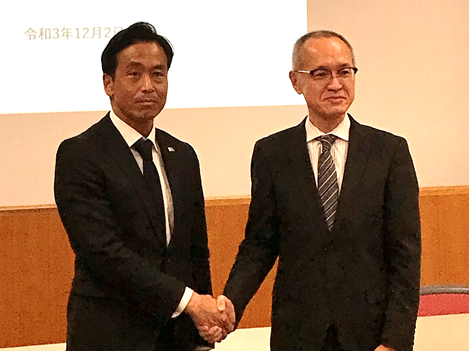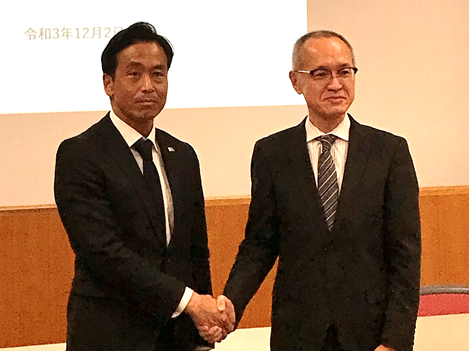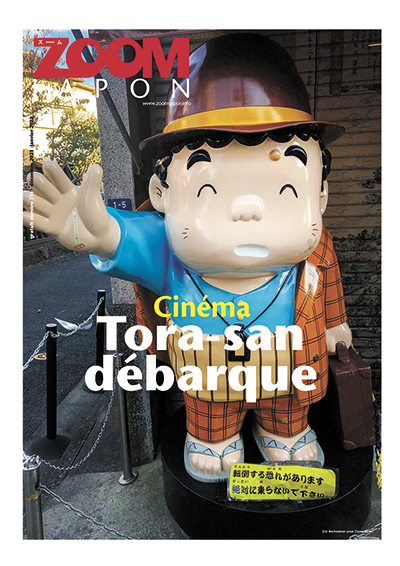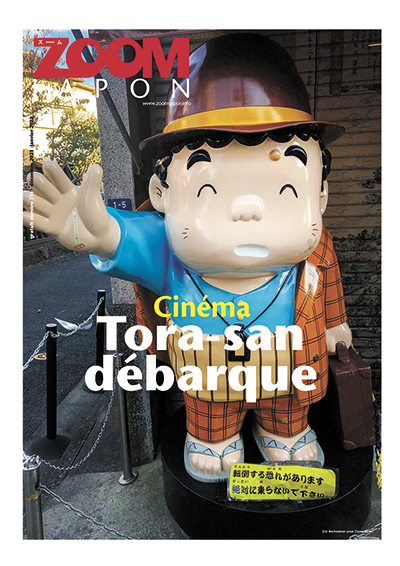2021年12月16日(木)配信
.png)
クラブツーリズム(酒井博社長、東京都新宿区)は2022年2月から、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)を活用した都市観光バスツアー「WOW RIDE(ワゥ ライド)」を始める。乗車中は車窓やモニターに映像を映し出し、陸海空、令和から江戸時代へと時空を移動するVR体験を楽しめる。
同ツアーは、同社とKNT-CTホールディングス(米田昭正社長)、フジ・メディア・ホールディングスの総合広告会社のクオラス(松下幸生社長)が共同で製作。従来のVR体験はVRゴーグルなどを装着して独りで楽しむものが多かったが、これはシートに座っているだけで非日常空間を体感でき、同乗者とリアルタイムで感動を共有できるようにした。
ツアーの総合演出は、映画監督・堤幸彦さんが務める。脚本は俳優・池田鉄洋さんが担当し、映像には池田さん本人をはじめ、俳優・温水洋一さん、お笑い芸人・ガンバレルーヤよしこさんが出演する。さらに、日本が世界に誇る大怪獣「ゴジラ」が登場。道中の歌舞伎座では、歌舞伎役者・片岡愛之助さんが歌舞伎の楽しみ方を紹介する。
また、人気声優の梶裕貴さん、日笠陽子さんが声の出演を務める、オリジナルショートアニメも登場。お笑い芸人やタレントがMCを務め、ツアーのガイド役を担う。
なお、ツアー設定日、旅行代金、販売受付方法などの詳細は22年1月に発表を予定している。
□「WOW RIDE」、バスツアー試乗会を行う

「WOW RIDE」のツアー開始に先立ち、12月15日(水)に報道関係者向けの試乗体験会を実施した。発着地は、東京・銀座の複合商業施設「GINZA SIX」に隣接する、銀座六丁目バス乗降所。出発すると日本橋や東京駅、皇居、国会議事堂、東京タワー、レインボーブリッジ、豊洲、勝鬨橋、歌舞伎座を約60分間掛けて周遊した。
当日はGINZA SIXを出発後、銀座の成り立ちを映像と演出で紹介し、車窓から見える老舗の「和光」と「山野楽器」の前を通る。そうすると温水さんが車窓正面に登場し、AR技術を用いた演出で乗客を盛り上げたあと、車窓左側でガンバレルーヤよしこさんとの“銀ブラ”するツーショットが撮影できる。

京橋交差点付近に着くと、江戸時代へタイムスリップする演出後、車窓全面が江戸の町の景色へと一変。池田さん演じる一心太助による江戸の町の紹介や、当時の魚河岸を再現した映像が見られる。常盤橋付近に着くと、全4話で構成されるショートアニメの第1話の上映が始まった。

そして、東京駅で再び温水さんが登場したり、皇居付近で池田さん演じる井伊直弼による桜田門外の変の事件のようすを体感するなどしたあと、折り返し地点となる国会議事堂へ向かう。その後も、東京のランドマークを上空や地下鉄、水中などアトラクションのような映像とともに周遊し、エンディングを迎えた。

今回、有名なランドマークを周遊する東京観光の定番を採用することで、初めて東京観光をする人に喜んでもらうと同時に、これまで知らなかった東京の魅力を再発見してもらうことを狙う。
.png)