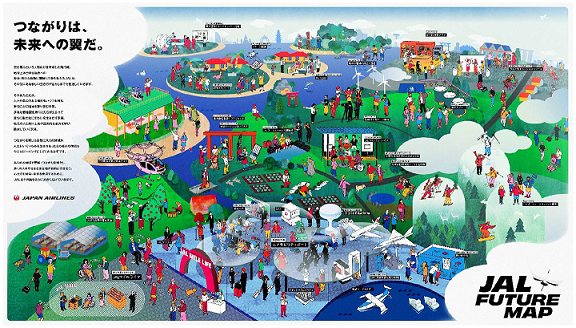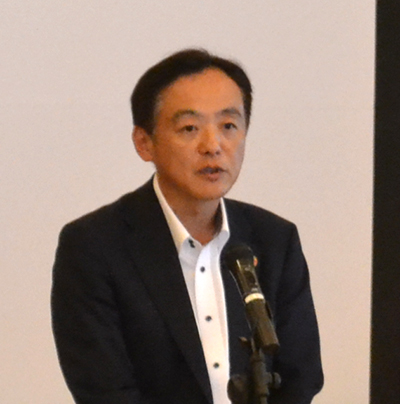2024年8月2日(金) 配信

新潟県の東京都内での新たなアンテナショップ「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」が8月8日(木)にオープンする。
地下鉄銀座駅から徒歩1分の複合ビルの1~3階、8階、そして地下1階を占める。
このうち1、2階がショップで約1000品目の商品を用意する。1階では野菜や米、米菓子、へぎそばなどの食料品を、2階では日本酒やワイン、地ビールといったアルコールと刃物、小千谷縮などの工芸品を販売するほか、日本酒コーナーには約40種の日本酒を試飲できる有料試飲機を設置、AIソムリエが気分や好みの酒を提案してくれる。また、1階では新潟産コシヒカリを使ったおにぎりも常時販売する。
3階はイベントスペース。県内の自治体や観光協会などの観光物産展に利用する。8階は燕三条を本拠地とするレストランが新潟の食材を中心としたイタリア料理を提供する。地下1階は移住相談窓口。
新潟県の都内でのアンテナショップは表参道で長らく「新潟館ネスパス」として営業していたが、老朽化したビルの取り壊しのため昨年末に閉館していた。
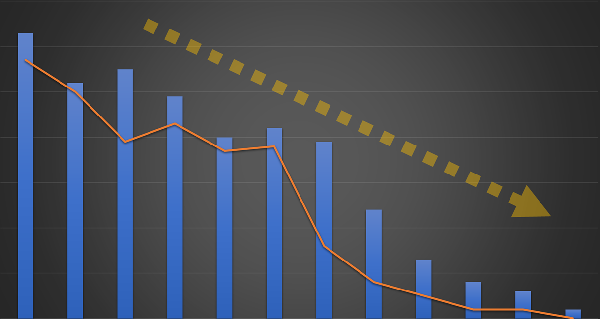


.jpg)