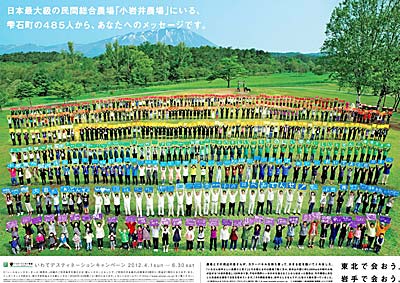東アジアの観光交流拡大へ
本紙は4月21日号で創刊1500号を迎えた。今号は記念企画として、提携紙である韓国「旅行新聞」発行人の韓政勳氏、台湾「旅奇週刊TRAVEL RICH」總栽の何昭璋氏にメッセージをいただいた。東アジアの観光交流が拡大するなか、韓国、台湾それぞれの観光業をリードする専門紙のトップによる提言を紹介する。
【編集部】
◇
 韓国旅行新聞
韓国旅行新聞
発行人 韓 政勳
(Hahn Jung-Hun)氏
文化交流と相互理解を促進、韓国 旅行新聞
「旬刊旅行新聞」の1500号発行を心よりお祝い申し上げます。
1500号を迎えるまでに旅行新聞が注いだ格別の努力と使命感にも敬意を表します。1975年創刊以来、これまでに発行された旅行新聞1500号は、日本の観光産業の歩みと歴史そのものです。旅行新聞の読者にも大きな名誉であり誇りだと思います。
韓国と日本は、歴史的、経済的、社会的に密接な関係に置かれており、観光産業の面でも同様です。何よりも両国はお互いに最大のインバウンド市場です。 2012年に韓国を訪問した全体外国人観光客1114万人のうち日本人観光客は351万人で32%を占め、最も高いシェアを示しました。
11年に日本を訪れた外来客621万人の中で最も多かった国も韓国人観光客(166万人)でありました。最近の円安に支えられ、日本を訪問する韓国人観光客が大幅に増えており、今年の訪日韓国人観光客の数は大幅な成長率を記録する見込みです。
両国間の観光交流は経済的な波及効果の面ではもちろん、文化交流と相互理解を促進するという点で非常に重要です。多くの韓国人観光客が日本旅行を通じ、日本の歴史や自然、文化や伝統、料理や芸術を体験して学んでいます。草津、別府、登別など、日本の豊かな温泉資源は韓国人なら誰もが一度は経験してみたいほど魅力的です。日本人観光客も同じ理由で韓流に熱狂し、韓国を旅行すると思います。政治や外交などの外部的な要因に影響を受けずに、観光交流それ自体が意味を持たなければならない理由です。
しかし、現実はそうではないのが事実です。外交紛争などで観光交流まで萎縮している事例が多く発生したためです。むしろそんなときこそ、観光交流はさらに活発になるべきだと思います。昨年10月末、日本の函館で開かれた第27回韓日観光振興協議会で韓日双方が合意したように、観光交流は両国を取り巻く諸状況の影響を受けず、原則的に推進されることをお勧めします。これにより、2013年の相互観光交流人数700万人という目標も達成することができます。
両国間の観光交流だけでなく、東アジアの域内交流の拡大も重要な課題です。昨年、訪韓外来客1114万人のうち62%が東アジアの上位3カ国である日本と中国(283万人)、台湾(54万人)の観光客だった点を見ても、東アジアの観光交流の活性化の価値を推測することができます。これは、日本の観光産業にとっても同様です。
東アジア域内の観光交流を拡大するためには、まず、地方の観光が活性化される必要があります。既存の首都圏および大都市中心の観光交流には限界があります。東アジア各国の地方観光活性化のために、ホテルなどインフラ構築に乗り出して、外国語対応態勢などを備えながら積極的に対応する場合は、各地方の観光インフラの改善効果も収め、地域観光を活性化させることができます。
このすべてのことを達成するには、旅行専門紙の役割は重大です。1500号を迎えるまでそうしてきたように、今後も平和産業である観光産業の発展を主導する旅行新聞になることを願っています。ありがとうございます。
双方の“報道と発信”が不足、台湾 旅奇週刊
 旅奇週刊 總栽 何 昭璋
旅奇週刊 總栽 何 昭璋
(James Ho)氏
「旬刊旅行新聞」1500号の発刊、誠におめでとうございます。
1975年に創刊されて以来、日本の旅行会社や、旅館・ホテルなど観光業界の総合専門紙として38年間にわたり、業界新聞を掲載、発信に努められ続け、同じく台湾の業界紙「旅奇週刊TRAVEL RICH」としては大先輩の存在であり、学ぶことがたくさんあります。このたび、海外の提携紙として選んでいただき、光栄に存じます。今後も日本国内のみならず、台湾観光業界との交流のオピニオンとしてもますます躍進されることを祈念いたします。
近年、台湾観光業界のインバウンド市場の状況は、中国観光客の解禁および直行便の就航とともに、中国観光客の数は飛躍的に伸びています。最初は対応しきれない問題点もしばしば発生し、クレームが多発していましたが、行政や民間施設の努力によって、改善しつつあります。交通部観光局も年間800万人の海外観光客の目標も掲げています。
アウトバンド市場も航空路線の増設、欧米のビザ緩和政策などの原因により、海外旅行目的地の選択肢が増えています。そのなかで、もちろん3・11、円高などの影響もありましたが、訪日旅行は依然不動の地位にあります。とくにこの2、3年は宮崎、鹿児島、岡山、小松、高松、静岡、新潟、函館、旭川など地方空港の定期便就航によって、さらに旅行路線の面が広がり、内容の多様化も感じられ、昔の広域周遊型から「ブロックエリアの滞在型」に変わってきています。広域のウィンドウ見物から、ブロックエリアの自然体験、大都会の繁華街のネオンから田舎の農家生活、量から質へと、訪日旅行の形態が変わりつつあります。
台湾は亜熱帯にある小さい島国であり、日本に求めるものは、台湾では味わえないものです。シーズン別に春の桜、秋の紅葉、冬の雪など伝統的なテーマに加え、この時期になると立山黒部のアルペンルートは大人気です。そして北海道が、台湾でリピーター率ナンバーワンと言われる理由としては、春、夏、秋、冬の自然景観、そして四季の食事内容、観光ポイントが多大な人気を持っているからです。
台湾における訪日旅行商品の主流は4泊5日です。就航路線の発着空港をベースに商品を組み合わせ、九州北部の阿蘇火山、ハウステンボスをメインとするツアー商品に対して、南九州の桜島、指宿砂風呂、宮崎の高千穂を構成した商品も人気を呼んでいます。とくに最近の九州の観光列車もJR九州の販促で、台湾での人気も高まっています。山陰山陽、四国なども似たような商品がたくさん造成されており、代表的なテーマを確立するのが絶対な条件だと思います。
そして、「旬刊旅行新聞」の影響力も台湾に広げています。この近年「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」に選ばれた旅館もツアー商品販売するときの宣伝用語となっています。
日本の観光立国宣言は小泉首相が掲げて10年、そして観光庁の設立も4年が経って、政府主導の動きを見せましたが、大きな問題点としては各所管の官と県庁の協調性および民間組織、施設との連係プレーが見えていないように思われます。そして人事制度も問題点があり、3年から4年で担当者が替わり、また一から出直す現象もしばしばあります。観光事業の成功は一気呵成ではなく、一貫性にあり、時間とともに実績、経歴の累積で発展していく事業であり、本当のプロを育てなければならないのです。
また、民間ホテル、旅館施設など対インバウンドの受け入れ態勢はもっと開放的な考えや態度を示していただきたいと思います。東京、大阪、福岡、名古屋など都市圏、北海道を除く、九州、中国、四国、北陸、中部、東北などの地域において、台湾観光客が宿泊しているホテル、旅館はごく一部に集中しており、まだ多くの宿泊施設は受け入れていません。シーズンになると、宿泊施設の予約は台湾旅行社の最大の悩みであります。安定的な宿泊施設の提供が観光事業発展に不可欠な条件です。インバウンドの受け入れを幅広く対応していくことと期待しています。
情報社会の現在とはいえ、台湾において、日本観光業界に対する報道、発信が依然不足しています。そして、同じく日本でも台湾に対する報道が全然足りないと思っています。日本、台湾とも国内の人口減少、高齢化などの問題があり、観光事業の振興は経済活性化に必要な項目であります。我われ観光業界専門紙の使命としては、業界の良いパートナーとして、お互いにさまざまな情報を提供し、日台観光交流の架け橋としてがんばって参ります。