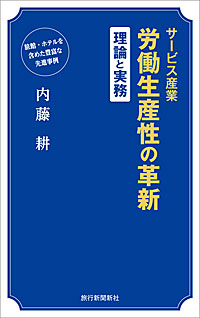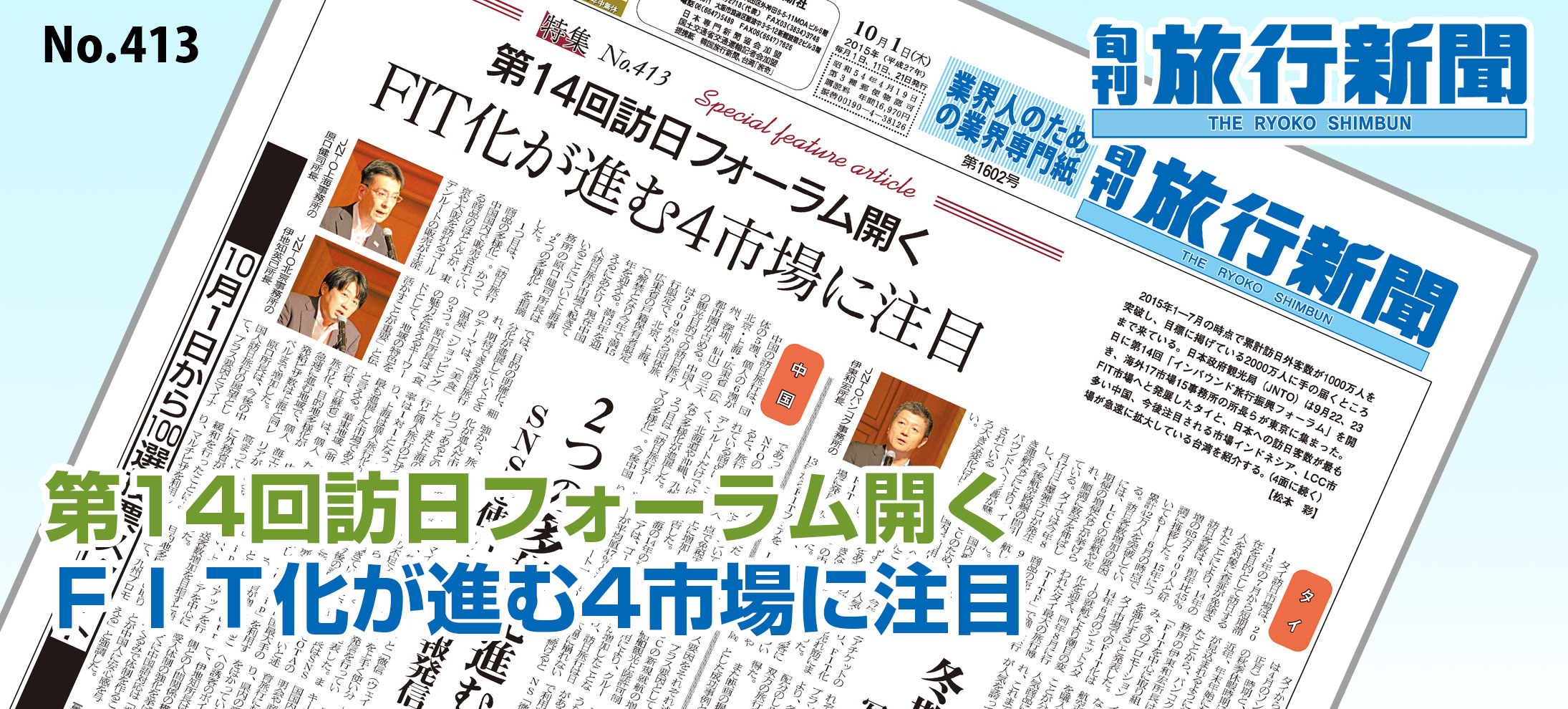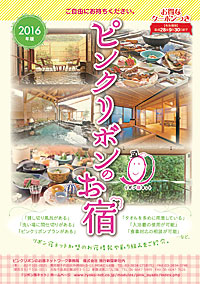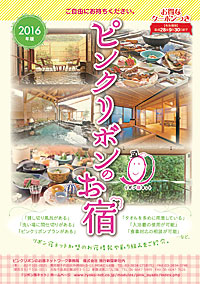秋になると、品良く薄いデニールのタイツにロングブーツを履いた女性が街を歩く姿を見かける。路上に銀杏の枯れ葉が舞うなか、コートに両手を突っ込んでマフラーに顎を埋め、髪が風に流れていく姿に、秋という季節を感じることができる。
タイやフィリピンなど東南アジアでは、「東京の銀座や表参道、原宿、代官山の街を秋のお洒落をして歩きたい」と夢見る女性が多いらしい。
この感覚は、日本人がパリやミラノ、ロンドン、ニューヨークで格好良く闊歩したいと思い描く感覚に似ている。
東京もそのような都市の一つに挙げられるのだと思うと、なんだか誇らしくなる。
¶
ヴォーグ米国版元編集長のアナ・ウインターが2011年に東京を訪れたとき、「日本のファッションについてどう思うか?」の質問に、「ニューヨーク以上に独創的で、個性的」と評し、「どんな格好が目についたか?」には、「髪型やカラーリングした髪」と答え、「実際、女性よりも若い男性の方が、ややリスクを厭わない傾向があり、素晴らしい」と絶賛している記事を読んだことがある。
¶
海外を旅するとき、一体我われは、何を目にするだろう。世界遺産に登録されるような歴史的な建造物に目を奪われることはしばしばある。しかし、それだけではない。表通りのピカピカに輝くガラスに覆われた超高層ビルディングなどの建築物や、煌びやかなショーウインドゥなどの街並み、メインストリートを駆け抜けるメルセデスやBMW、レクサス、アウディなどの高級車がどのくらい走っているのか、どこの国のメーカーが売れているのかなどにも目が行く。また、カフェや酒場、レストラン、定食屋などにも注意が向けられ、やがて少し裏通りに入り、その街にしかない、独特の匂いなどに心を奪われたりする。人によって関心の度合いが違うが、建築物であれ、クルマであれ、料理屋であれ、そこで生活している人々の文化に興味が魅かれていく。そのうち否応なく、この都市で生活している人たちはどのようなファッションや髪型をしているのかという核心部分に向い、着地する。
道行く人とすれ違うたびに大きな驚きがあり、発見がある。カフェでコーヒーを飲む時も、店内の客の姿を観察する。地下鉄に乗れば乗客を、バスに乗っても、街を歩く人ばかりを目にすることになる。
¶
東京は世界から「街並みが綺麗な都市」として認知されている。また、「グルメ都市」としての別の顔も持つ。都市観光は多面性が重要である。そして「ファッションシティ」としての顔は、実は最重要なアピールポイントなのである。
ファッションシティの主役は、自然でもなく、歴史的な建造物でもなく、人である。現在、生きている生活者が中心である。現在性の最先端を走り、世界の最新の思想、哲学、文化を生み出し、牽引していく力を持つ都市のことを指す。
アナ・ウインターが答えたように、都市の「独創性」はさまざまな分野のクリエーターたちにもインスピレーションを与える。だが、これは何も東京に限ったことではない。日本中の地域で資源探しをしているが、どこかの先端都市の「マネ」は尊敬を得られず、嘲笑の的となる。そこに生活する人々の「独創性」の価値に早く気づくべきである。
(編集長・増田 剛)