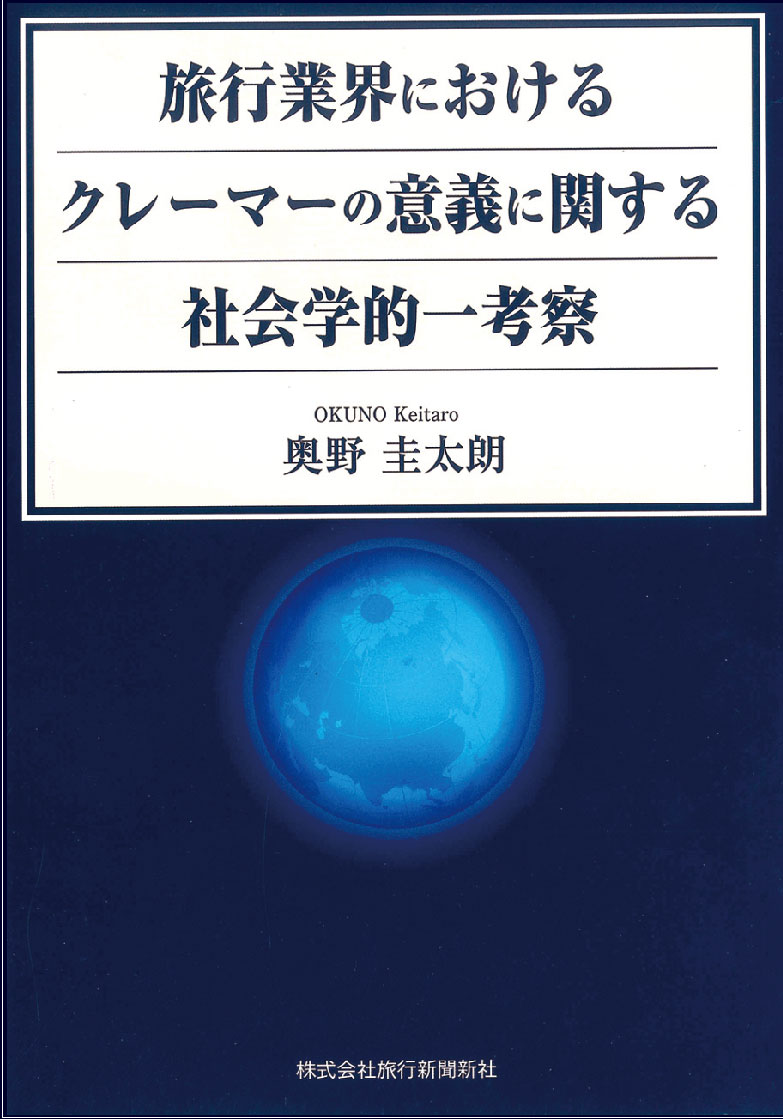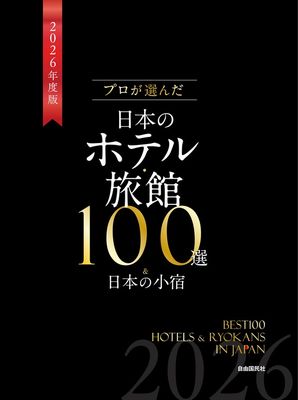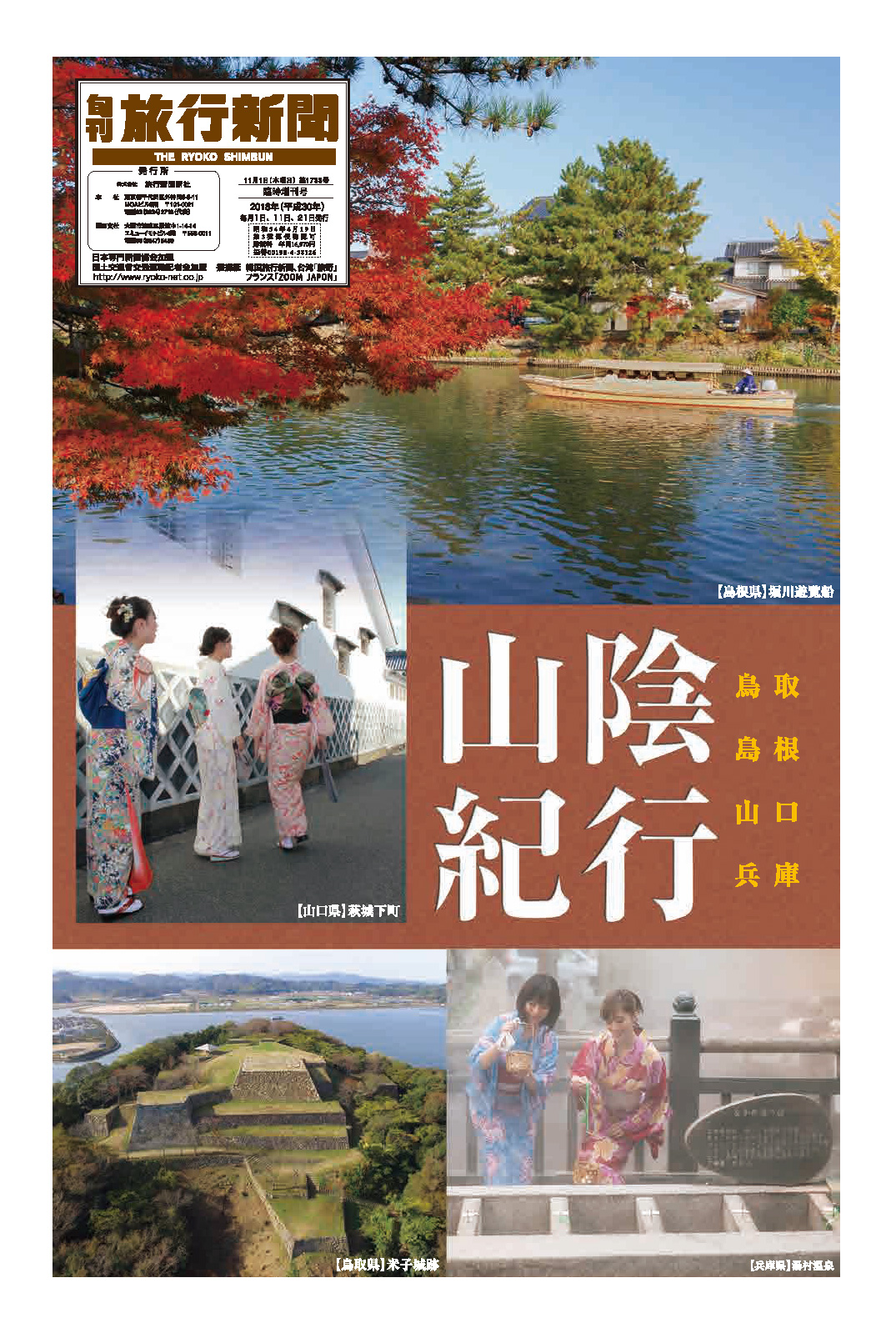『いい旅館にしよう!』
対談者・内藤 耕、コーディネーター・増田 剛
定価:1冊 1,980円(税込)
送料:実費(1部430円)
仕様:四文判232ページ
発売日:2014年7月1日 初版
<内容紹介>
「いい旅館にしよう!」の対談シリーズは、旬刊旅行新聞紙上で2012年3月21日号から2013年9月1日まで、15人の旅館・ホテル経営者が登場し、工学博士でサービス産業革新推進機構代表理事の内藤耕氏との対談スタイルで掲載していった人気シリーズ。読者の声を受け、書籍化された。
ここに登場する経営者の多くは、最初は失敗ばかりで何をやっても上手くいかず、さまざまな試行錯誤を繰り返すなかで、自分の目指す宿を作り上げていった方々である。
次世代の旅館文化を担う若きリーダーたちの「バイブル」として、ロングセラーを続けている。
本書に登場する経営者は次の各氏。
「時音の宿 湯主一條」代表取締役 一條一平氏(宮城県・鎌先温泉)
「向瀧」代表取締役 平田裕一氏(福島県・会津東山温泉)
「熱川プリンスホテル」代表取締役 嶋田愼一朗氏(静岡県・熱川温泉)
「一の湯」代表取締役 小川晴也氏(神奈川県・箱根搭ノ沢温泉)
「天空の森」主人 田島健夫氏(鹿児島県・南きりしま温泉)
「湯元舘」代表取締役会長 針谷了氏(滋賀県・おごと温泉)
「網元の宿ろくや」代表取締役 渡邉丈宏氏(千葉県・岩井湯元温泉)
「加賀屋」代表取締役相談役 小田禎彦氏(石川県・和倉温泉)
「鶴雅グループ」代表取締役社長 大西雅之氏(北海道・阿寒湖温泉)
「越後湯澤 HATAGO井仙」代表取締役 井口智裕氏(新潟県・越後湯沢温泉)
「ホテルナンカイ倉敷」代表取締役 田中安彦氏、支配人 田中正子氏(岡山県倉敷市水島)
「城崎山本屋」代表取締役 高宮浩之氏(兵庫県・城崎温泉)
「里海邸 大洗金波楼本邸」主人 石井盛志氏(茨城県・大洗町)
「割烹の宿 美鈴」主人 中野博樹氏(三重県・紀伊長島)
「ホテル風早」代表取締役 武内眞司氏(大分県日田市)