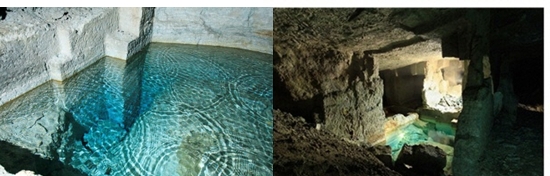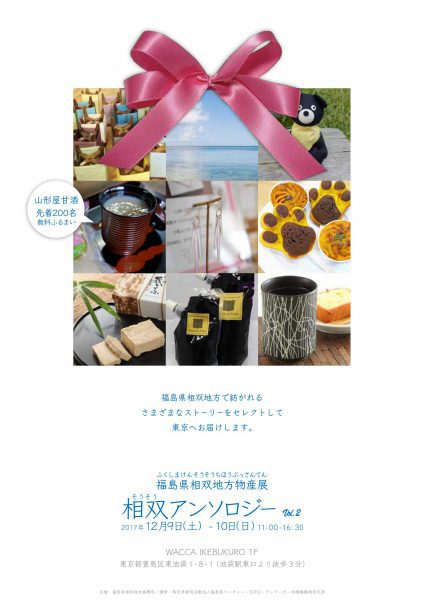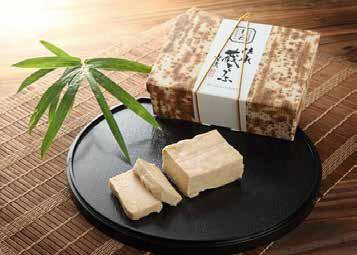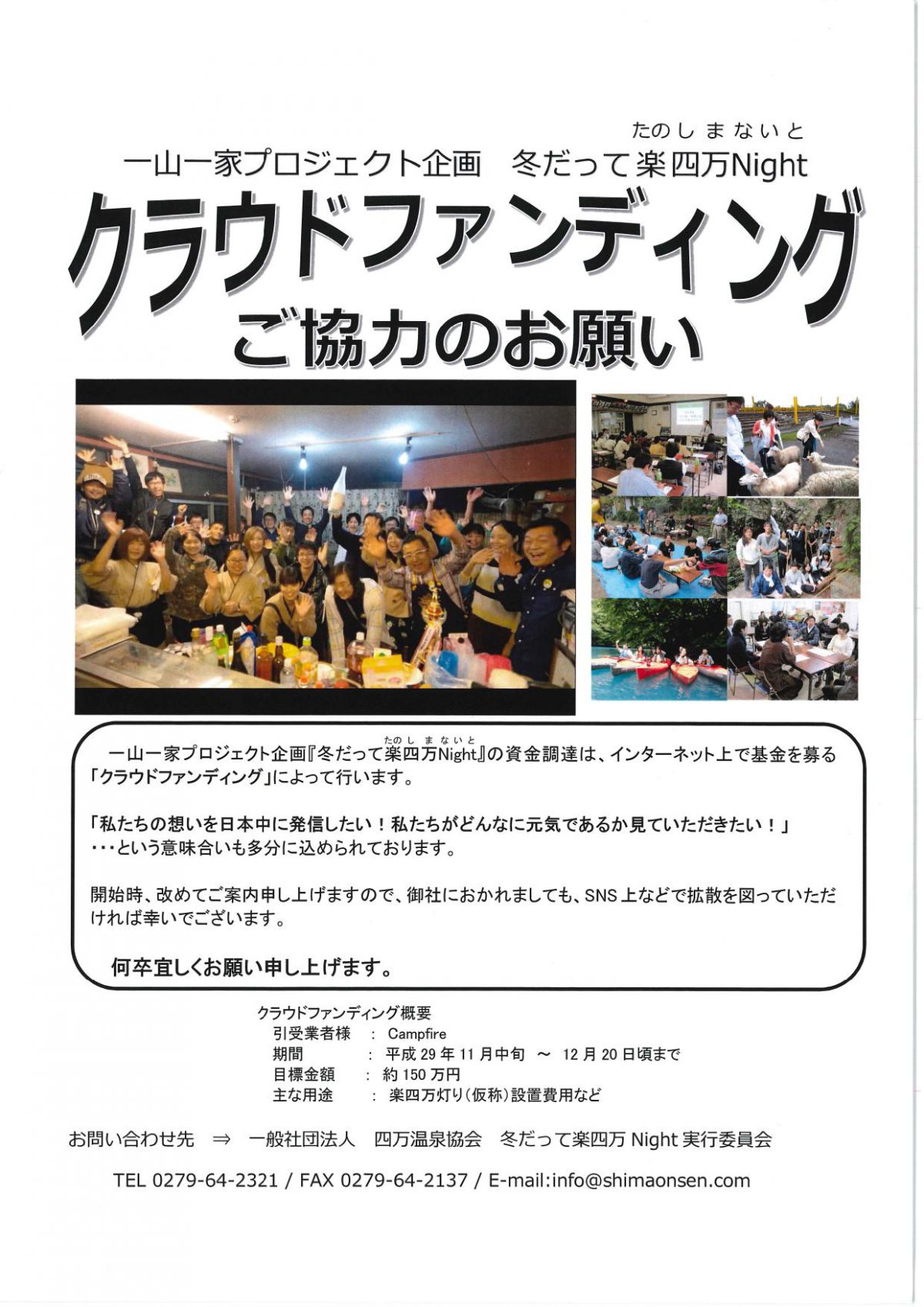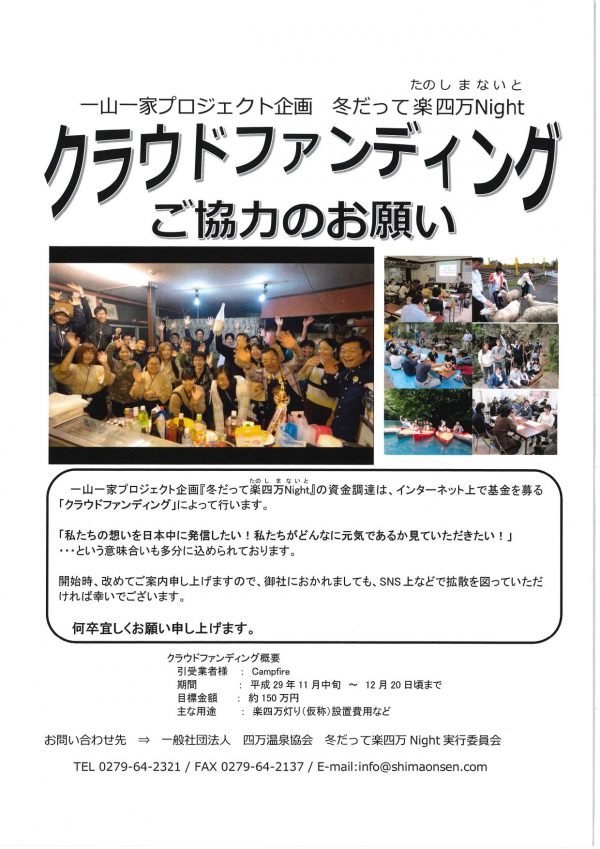2017年12月4日(月) 配信
 1位を獲得したマウイ島のハレアカラ国立公園
1位を獲得したマウイ島のハレアカラ国立公園
トリップアドバイザーは2017年12月1日(金)に、サイト上に投稿された過去1年間の口コミ評価をもとに、「日本人に人気のハワイ観光スポットランキング」を発表した。
今回は日本語の口コミ投稿をもとに、日本人にとくに人気が高かった観光スポットのランキング。同社は「メジャーな所からまだあまり知られていないスポットまで、ハワイの大自然や文化を楽しめるスポットが並ぶ、ハワイ旅行に参考になるリストになっています」とコメント。
□ランキングトピックス
1位を獲得したのは、マウイ島の「ハレアカラ国立公園」。標高3055㍍の世界最大級の休火山「ハレアカラ山」を有する国立公園。夕陽や満点の星空、そして雲海からゆっくり現れる朝日も最高と、ハワイの壮大な自然を体感できるスポットとして人気を集めた。
2位は4205㍍のハワイ島の「マウナケア山」。神々しく美しい壮大な自然に感動する口コミが多く投稿された。 3位以降はオアフ島の観光スポットが多く並んだが、なかでも「ラニカイビーチ」が3位、「カイルア ビーチ パーク」が4位、「ラニカイ ピルボックス トレイル」が7位に入り、カイルア地区が人気を集めていることが分かった。
「ラニカイ ピルボックス トレイル」の他にも、オアフ島でハイキングが楽しめる、「ココヘッド クレーター トレイル」と、「ダイヤモンドヘッド」、「マカプウ ライトハウス トレイル」がランクイン。オアフ島を訪れた際に、トレイルに挑戦している人も多いようだ。
□日本人に人気のハワイの観光スポット Top20
1位 ハレアカラ国立公園(マウイ島)
2位 マウナケア山(ハワイ島)
3位 ラニカイビーチ(オアフ島 カイルア)
4位 カイルア ビーチ パーク(オアフ島 カイルア)
5位 戦艦ミズーリ記念館(オアフ島 ホノルル)
6位 ワイマナロビーチ(オアフ島 ワイマナロ)
7位 ラニカイ ピルボックス トレイル(オアフ島 カイルア)
8位 ハワイ火山国立公園(ハワイ島)
9位 ココヘッド クレーター トレイル(オアフ島 ホノルル)
10位 シャングリラ(オアフ島 ホノルル)
11位 ダイヤモンドヘッド(オアフ島 ホノルル)
12位 ワイメア渓谷(カウアイ島 ワイメア)
13位 マカプウ ライトハウス トレイル(オアフ島 ホノルル)
14位 カピオラニ公園(オアフ島 ホノルル)
15位 マジックアイランド(オアフ島 ホノルル)
16位 コオリナビーチパーク(オアフ島 カポレイ)
17位 ビショップ博物館(オアフ島 ホノルル)
18位 ポリネシアカルチャーセンター(オアフ島 ライエ)
19位 マノア滝(オアフ島 ホノルル)
20位 ホノルル美術館(オアフ島 ホノルル)
※「日本人に人気のハワイ観光スポットランキング」は下記URLから閲覧可能
□オアフ島でアクティブに過ごしたいなら、トレイルに挑戦
トップ20にオアフ島でハイキングが楽しめる「ラニカイ ピルボックス トレイル」と、「ココヘッド クレーター トレイル」、「ダイヤモンドヘッド」、「マカプウ ライトハウス トレイル」がランクイン。「アクティブに過ごしたい方はトレイルに挑戦してみてはいかがでしょうか」(同社)。
「マカプウ ライトハウス トレイル」は道がアスファルトで舗装されているため歩きやすく、サンダルでも楽しめる「手ごろなトレッキングコース」。所要時間も往復で1時間半程度と、ほどよい距離となっている。
 マカプウライトハウストレイルで見れる灯台
マカプウライトハウストレイルで見れる灯台
オアフ島のシンボルである「ダイヤモンドヘッド」も、比較的気軽に登れるようだ。ただ、口コミでは「スニーカーは必須」とのコメントも。頂上の手前に急な階段があるが、抜ければ山頂に広がる絶景を望むことができる。
 ダイアモンドヘッド
ダイアモンドヘッド
「ラニカイ ピルボックス トレイル」は先と比べ体力のいるトレイルで、「小さな砂利があるような道なので、スニーカーでも滑ります。思いのほか急斜面なので、こけます」「初心者コースと言う割には大変でした」、との口コミが投稿されていた。なお、“ピルボックス”は、鉄筋コンクリート製の防御陣地のことで、このトレイルに2つある。
 ラニカイ ピルボックス トレイルのピルボックス
ラニカイ ピルボックス トレイルのピルボックス
「ココヘッド クレーター トレイル」は、ケーブルカーの線路跡が道になっており、麓から山頂まで一直線の道。「枕木の一段がすごく高くて、足の短い日本人にはなかなかしんどい」「一本道をずっと進み、景色に変化が無い為つらかったです」「ハワイの主要なトレッキングは行きましたがココヘッドが一番、辛かった」との口コミも。
 ココヘッド クレーター トレイルの線路跡
ココヘッド クレーター トレイルの線路跡
「いずれのトレッキングコースも、苦労した登った先に達成感と爽快感が待っています。自分のコンディションに合わせて準備を万端にして登ってみたいですね」(同社)。
□ハワイに行った日本人なら訪れておきたい、歴史を知る「戦艦ミズーリ記念館」が5位にランクイン
戦艦ミズーリは第二次世界対戦の真珠湾攻撃や、朝鮮戦争、湾岸戦争で服役し、日本の降伏文書調印式の場所にもなった。 1994年まで現役で活躍していたこの戦艦は、現在「戦艦ミズーリ記念館」として公開されている。太平洋戦争の始まりとされる真珠湾に浮かんでいるこの戦艦は、神風特攻機が衝突した跡も見ることができる、日本と深い関係のある歴史の舞台でもある。
 一度は訪れたい、戦艦ミズーリ記念館
一度は訪れたい、戦艦ミズーリ記念館
「戦艦ミズーリ記念館」: 口コミピックアップ紹介
・ハワイで、リゾート感にふけるのもいいですが、一度は、訪れてみるとハワイの見方、戦争に対する意識も変わるかもしれないです。
・歴史は背を向けやすいですが、旅先で少しずつ勉強するのも良いと思いました。
・神風特攻隊についての展示もあり、アメリカ視点だけの展示ではないことに感銘を受けました。ビーチだけを楽しむのもいいですが、この歴史に目を背けてはいけないと感じました。
・歴史も含め学べるし、神風特攻隊の説明は日本人として非常に考えさせられた。