2025年11月29日(土)配信
.png) エクステリアデザイン(イメージ)
エクステリアデザイン(イメージ)
近畿日本鉄道(近鉄、原恭社長)と近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングの3社は10月31日、三重県内で記者会見を開き、2026年秋から近鉄名古屋駅―賢島駅間で、上質な車内空間でフランス料理が楽しめるレストラン列車「Les Saveurs 志摩(レ・サヴール・しま)」を運行すると発表した。同社としては初のレストラン列車となる。
【塩野 俊誉】
◇
「サブール」はフランス語で「味」「風味」の意味。伊勢志摩の多様な食材が織りなす奥深い味わいをイメージしたネーミングとした。
コンセプトは「美食が誘う、優雅な列車旅」。提供する料理は、志摩観光ホテルの樋口宏江総料理長が監修した本格的なコース料理の「フレンチコース」と、近鉄・都ホテルズが監修したフレンチを手軽に楽しめる「フレンチ膳」の2種類を用意。食事やドリンク提供などの車内サービスは、近鉄リテーリングが担当する。
近鉄の原恭社長は「新たな観光列車を開発するにあたり市場調査をしたところ、食をコンセプトにした列車への要望が高いことが分かった。伊勢志摩は古くから『御食つ国』と称される食材の宝庫であり、志摩エリアには高品質な食事を提供する志摩観光ホテルがある。この2つの要素がレストラン列車実現の決め手となった」と開発に至る経緯を説明した。
.png) フレンチコース(イメージ)
フレンチコース(イメージ)
「フレンチコース」は、「熊野地鶏のコンフィとあおさのキッシュ」や、伊勢海老・伊勢まだい・ハマグリを使った「海の幸のパピヨット」など、三重県の豊かな自然が育んだ食材を堪能できる本格的なフレンチのコース料理が楽しめる。
「フレンチ膳」は、「三重県産和牛のパルマンティエ風 キャベツのルーロー」や「伊勢あかりのポーク ローストポーク」など、地元食材をふんだんに使用した彩り豊かなフレンチを木箱に詰め込んで提供する。
樋口総料理長は「旅の時間のなかで、地域の食を味わうことをテーマに、五感で楽しめるメニューを考えた」と料理に込めた想いを語った。
列車は4両編成で、「フレンチコース」は4号車、「フレンチ膳」は1、2号車で提供する。3号車はキッチン車となる。座席は、50席で全席指定。4号車が4人席×2卓、2人席×4卓の計16席。1、2号車は、2人席×15卓、1人席×4卓の計34席。1号車には車イススペースも3台分設ける。
外観デザインは、志摩の「海・白砂・太陽」が醸し出すさわやかな開放感を、深みのある青と光を感じる白で表現。青のメタリック塗装やゴールドのラインにより高級感を演出する。
4号車のイスは、革張りの家具調でゆったり寛げるほか、1、2号車は車窓が楽しめるように席を斜め向きに配置。各席は木目調の大きな仕切りでプライベート感をもたせるなど、車内デザインにもこだわる。キッチン車には、限られたスペースで多彩な料理を調理するため、スチームコンベクションオーブンを2台設置。水回りも充実させた。
運行は週6日を予定(季節により週7日の場合あり)。途中、伊勢市・宇治山田・五十鈴川・鳥羽・鵜方駅に停車する。ダイヤは、往路が昼食を想定し、午前11時ごろ近鉄名古屋駅発、午後1時30分ごろ賢島駅着。復路は夕食を想定し、午後4時30分ごろ賢島発、午後7時30分ごろ近鉄名古屋着を予定する。
、高井隆光社長(右端).png)



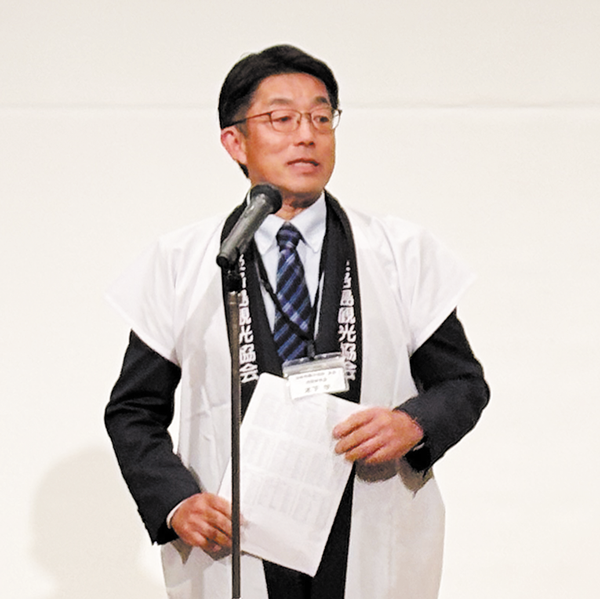
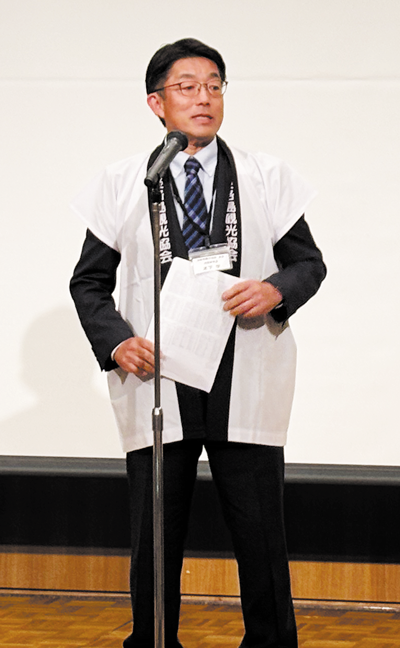
.png)
.png)











