2023年12月5日(火) 配信
 熱唱する宇徳敬子さん
熱唱する宇徳敬子さん
シンガーソングライターの宇徳敬子さんが11月11日、島根県出雲市の出雲大社「神楽殿」で御奉納公演を行った。ソロデビュー30周年を記念した公演で、全国から抽選で選ばれた約60人が神聖な空間に響いた宇徳さんの歌声を堪能した。
宇徳さんは1990年に国民的大ヒット曲「おどるポンポコリン」のB.B.クィーンズのバッキングボーカルでデビュー。91年にガールズユニット「Mi―Ke」を結成。デビュー曲の「想い出の九十九里浜」がヒットし、メインボーカルとして活躍した。93年にソロデビューを果たし、翌年に発表したファーストアルバム「砂時計」はオリコンチャート1位を獲得。以来、ライブ活動や楽曲制作などに精力的に取り組んでいる。
鹿児島県出身の宇徳さんが初めて島根を訪れたのは2019年11月。八百万の神々が出雲に集う出雲大社の神在祭の神聖な雰囲気に魅了され、毎年神在月に出雲を訪れるほど島根ファンとなった。
大社での公演前日には松江市の島根県庁を訪れ、県からふるさと親善大使「遣島使」の委嘱を受けた。今後、県外で島根のアピールに力を入れる。
.png) 委嘱状を受け取る宇徳さん(右)
委嘱状を受け取る宇徳さん(右)
◇
念願の出雲大社での御奉納公演を実現した宇徳さんに話を聞いた。
――神在祭のどのようなところに魅了されたのか。
無性に行きたい、行かねばならないとばかりに心動かされ、弾丸で神在祭の最終日に島根に向かいました。本殿の東西にある十九社を歩いたときに空を見上げると一本筋に連なって空へ昇っていく光が見えました。その奇跡の瞬間を目の当たりにして、感銘を受けました。
――御奉納公演を終えて。
昨年、参拝に訪れた際に御奉納公演のお話を直接、出雲大社様へお願いしたあの日から実現したこの日までが奇跡の連続でした。夢が現実となり歌手冥利に尽きます。新しい希望の光と心が豊かで幸せでありますようにと祈りを込めて歌いました。
――今後、島根の魅力をどのように伝えていくか。
聖地巡礼の旅、美肌の旅、美味しいモノの旅、生かされて生きている命の輝きを蘇らせる“健幸美活”の旅。私なりに島根で学びながら、感じたことをお伝えできればと思っています。
【土橋 孝秀】
~26日(火)まで.png)


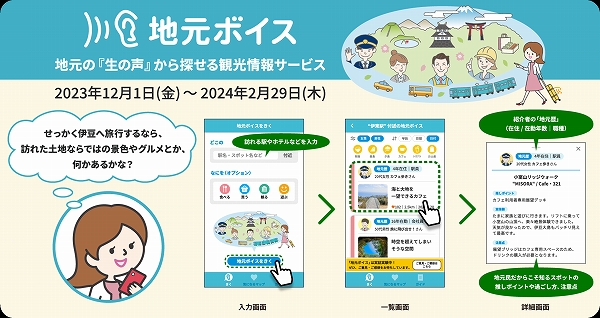

.png)





