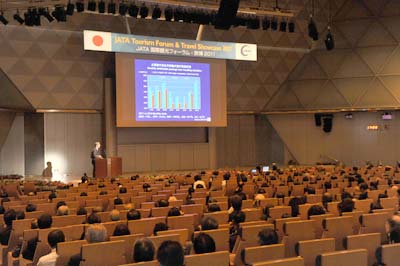ビジネス客が増加、FITは「再訪意向」高い〈震災前年同期と比較〉
観光庁はこのほど、2012年4―6月期の訪日外国人消費動向調査の結果から10年4―6月期と比較し、震災前後の訪日外国人客の属性変化と観光目的の個別手配客の特徴をまとめた。それによると、12年4―6月期の訪日外客は前々年と比べてビジネス客・リピーター・個別手配客が増加。個別手配率は韓国で56%、台湾で37%、中国で23%にのぼる。また、個別手配客は再訪意向の「必ず来たい」が多い傾向にある。
日本政府観光局(JNTO)が発表する訪日外客数によると、12年4―6月期はおおむね震災前の10年並みの水準に回復している。国別では台湾・中国・タイ・マレーシアが10年と比べて増加。一方、韓国・香港・シンガポール・インド・英国・ドイツ・フランス・ロシア・米国・カナダ・オーストラリアは震災前の水準まで回復していない。
訪日外国人の1人当たりの旅行中支出額をみると、震災前の10年と震災直後の11年を上回る11万4千円。国籍別では中国・英国・カナダで年々増加傾向にある。ほとんどの国籍で宿泊料金・飲食費・交通費が10年より増えているほか、中国では買い物代も増加した。
属性をみると、12年のビジネス客は74万4千人と10年の1・4倍に増え、とくに台湾・中国・韓国での増加が顕著。 来訪目的では「その他ビジネス」や「親族・知人訪問」が増加し、「観光・レジャー」が大きく減少した。来訪目的別の消費単価では「観光・レジャー」で1万6千円、「展示会・見本市」で2万8千円増加し、「その他ビジネス」「親族・知人訪問」では単価が下落している。
同行者をみると、ビジネス客増加の影響で「自分ひとり」「職場の同僚」が増え、観光・レジャー客減少の影響で「家族・親族」「友人」が減った。
訪日回数では「10回以上」のリピーター客が41万1千人で10年の1・3倍に増え、「1回目」が減少。「10回以上」のリピーターは韓国・台湾でとくに増えている。
手配方法をみると、パッケージツアーを利用しない個別手配客は150万3千人で、10年の1・1倍に増加。パッケージツアー利用客は10年より18万3千人減っている。とくに中国・台湾での個別手配客の増加が顕著。個別手配客の比率をみると、韓国が56%、台湾が37%、中国が23%となった。手配方法別の消費単価では、パッケージツアー利用客では大きな変化はないが、個別手配客の単価は年々増加し、12年は13万7千円と、10年に比べ1万2千円アップしている。
個別手配観光客の特徴をみると、20―30代の訪日リピーターが多い。訪問先は東京・大阪に集中し、買い物では服・かばん・靴の支出額が高い。情報源は個人ブログや日本在住の知人に頼ることが多く、現地情報のニーズでは交通手段情報のニーズが高い。
再訪意向はツアー客に比べて高く、韓国では個別手配客の42%、台湾では個別手配客の73%、中国では個別手配客の61%が、「必ずまた来たい」と答えている。