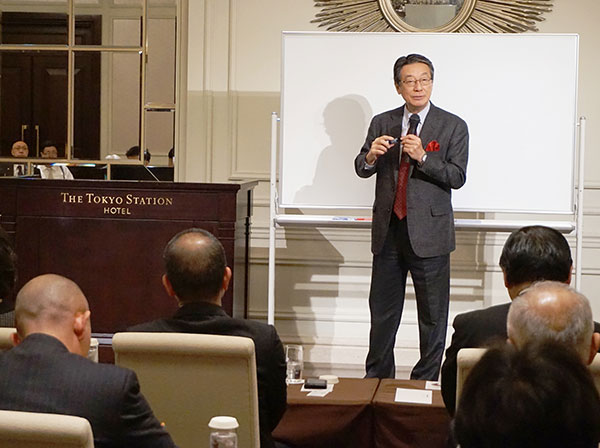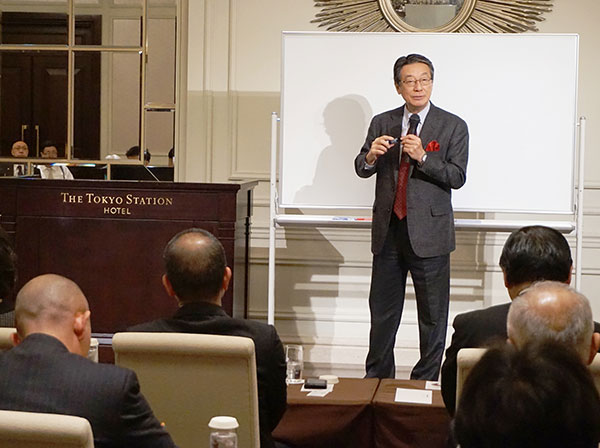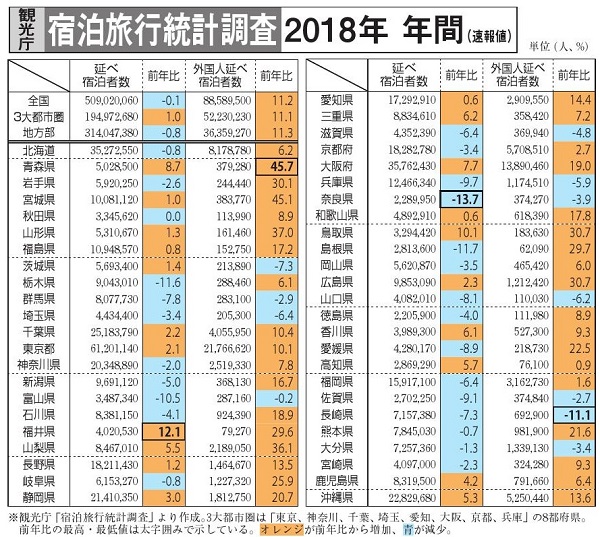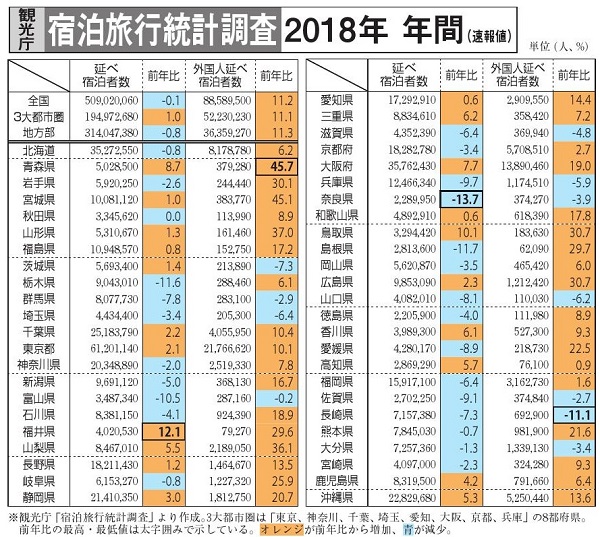2019年3月12日(火) 配信

長野県・阿智村のスタービレッジ阿智誘客促進協議会(会長=熊谷秀樹・阿智村長)は、映画「君は月夜に光り輝く」とタイアップし、村内のイベント会場にフォトブースの設置やパネル展示を実施する。さらに、SNSに投稿した人の中から抽選で非売品グッズが当たるキャンペーンを開催する。期間は2019年3月15日(金)~31日(日)まで。
□阿智村に「君は月夜に光り輝く」フォトブースが登場
3月15日(金)に公開される、永野芽郁さんと北村匠海さん出演の映画「君は月夜に光り輝く」は、不治の病と戦うヒロインが同級生に代行体験を依頼し、叶えられない願いを実行してもらううちに惹かれ合っていく感動のストーリー。
映画の公開にあわせて、日本一の星空「阿智村」にある富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはらで開催されている、冬季限定星空エンターテインメントイベント「天空の楽園 Winter Night Tour STARS BY NAKED」会場内に、ポスタービジュアルのような写真が撮影できる映画「君は月夜に光り輝く」フォトブースが登場する。
また、阿智村の観光拠点施設「ACHI BASE(アチ ベース)」内のBARで、映画「君は月夜に光り輝く」公開記念特別パネル展が開催される。ACHI BASEには、天空の楽園 Winter Night Tour STARS BY NAKED会場同様、映画「君は月夜に光り輝く」フォトブースも設置される。
さらに、阿智村のフォトブース(天空の楽園 Winter Night Tour STARS BY NAKED会場、またはACHI BASE)で、投影された月の前でポスタービジュアルのポーズを撮影し、Instagramに投稿した人の中から抽選で、映画「君は月夜に光り輝く」非売品グッズがプレゼントされる。
□「タイアップキャンペーン」概要
「天空の楽園 Winter Night Tour STARS BY NAKED」会場内
映画「君は月夜に光り輝く」フォトブース
・ポスタービジュアルのような写真が撮影できるフォトブースが登場
開催日程:2019年3月15日(金)~31日(日)
開催時間:午後7:00~10:00
会場:富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら
〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4
問い合わせ:阿智☆昼神観光局 0265-43-3001(午前9:00~午後6:00)
ホームページ:
観光拠点施設「ACHI BASE」内のBAR
映画「君は月夜に光り輝く」公開記念特別パネル展
・映画ポスターと劇中のシーン写真のパネルが展示される。
映画「君は月夜に光り輝く」フォトブース
・ポスタービジュアルのような写真が撮影できるフォトブースが登場
開催日程:2019年3月15日(金)~31日(日)
開催時間:午後7:00~11:30
会場:ACHI BASE
〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里338-25
問い合わせ:ACHI BASE 0265-49-3177(午前9:00~午後11:30)
ホームページ:
□「Instagram投稿キャンペーン」概要
プレゼント内容:
A賞 1人=映画出演者サイン入り映画プレスシート
B賞 5人=映画プレスシート
C賞 5人=「君月」オリジナル満月ブランケット
投稿期間:
2019年3月15日(金)~3月31日(日)
投稿方法:
①Instagramで日本一の星空スタービレッジ阿智公式アカウント「@star_achimura」をフォロー
②阿智村のフォトブース(天空の楽園 Winter Night Tour STARS BY NAKED会場またはACHI BASE)で、投影された月の前でポスタービジュアルのポーズを撮影
③ハッシュタグ「#君月×スタービレッジ阿智」をつけて投稿
当選発表:
当選された人にはダイレクトメッセージで連絡が届く。







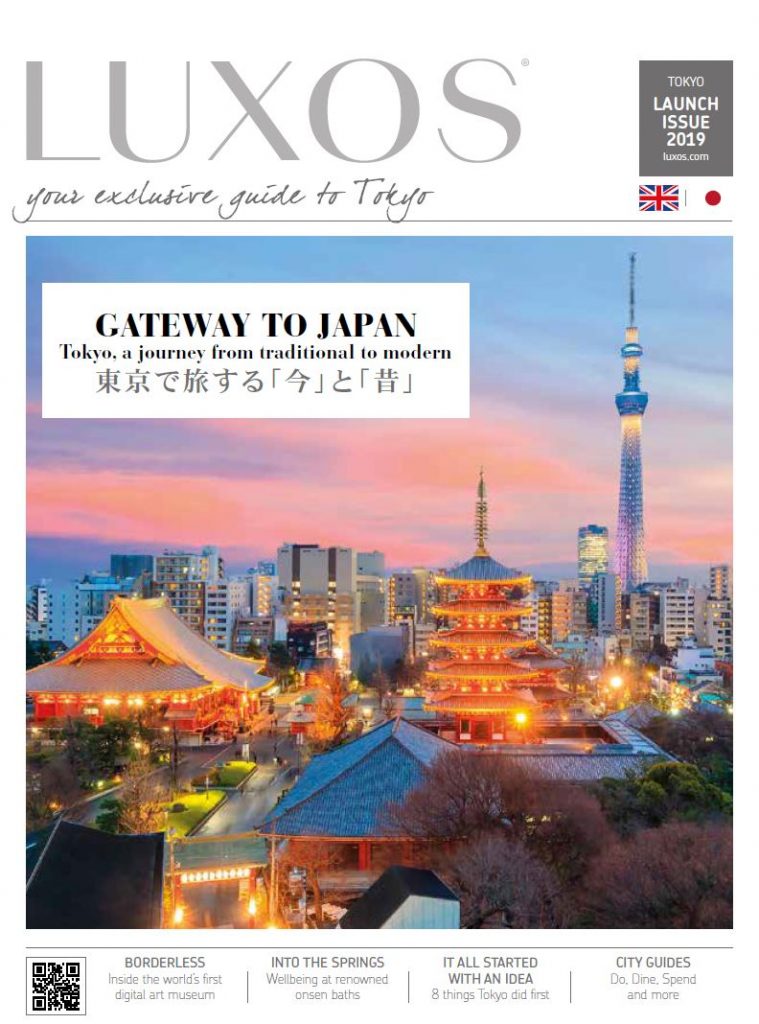


-web用.jpg)
-web用.jpg)