2017年12月12日(火) 配信

エイチ・アイ・エス(澤田秀雄会長兼社長、HIS)は2017 年12 月21 日(木)に、HISオリジナル世界一周疑似体験ができるVR(ヴァーチャル・リアリティ)を利用した「世界一周カレッジ」を開く。今回は、東京・西池袋にあるファーストクラスをモチーフにした空間やサービスを提供するエンタテイメント施設「FIRST AIRLINES」(阿部宏晃代表)と連携して行う。
HISが展開する専門店「世界一周旅行デスク」では、世界一周に伴う、おすすめの観光ルートや世界の航空会社・空港事情などを紹介する、「世界一周カレッジ」を毎月開開催。HIS世界一周旅行デスクの取扱人数は、前年と比べ3割増と需要が拡大している。ビジネスクラスやファーストクラスを利用して巡る世界一周旅行が、シニア世代を中心に人気が高まっている。
新たな取り組みとして、世界初のヴァーチャル航空施設の「FIRST AIRLINES」とタッグを組み、実際にビジネスクラス・ファーストクラスのシートでの搭乗体験と、VR を利用した世界一周の観光地を巡る疑似体験を提供する。
世界一周をモチーフとした特製料理も提供し、食事しながらHIS世界一周旅行デスクのスタッフよる説明会を実施。同社は、「世界一周旅行をより身近に感じもらい、実際の旅を検討する際の参考になれば」とコメントした。
□HIS×FIRSTAIRLINS 世界一周カレッジ概要
日時:2017 年12 月21 日(木)午後1時開始
会場:FIRST AIRLINES(http://firstairlines.jp/)JR 池袋駅から徒歩5 分(池袋駅C3 出口を出て徒歩1 分)
定員:8人(先着順)
申込方法:世界一周旅行デスクホームページから
参加費用:2千円
<イベントスケジュール(予定)>
午後12:45~午後1:00 搭乗手続き
午後1:00~午後1:15 プロジェクションマッピングを使用した離陸体験
午後1:15~午後1:30 VR 体験①…イタリア(ローマ・ヴェネチア)、フランス(パリ)
午後1:30~午後2:30 お食事(※1)/世界一周旅行説明会
<休憩(15 分)>
午後2:45~午後3:00 VR 体験②…アメリカ(ニューヨーク)、カナダ(イエローナイフ)、ハワイ
午後3:00~午後3:10 プロジェクションマッピングを使用した着陸体験
午後3:10~午後3:15 着陸
(※1)食事内容:
前菜3 種盛り…カラフルトマトカプレーゼ(イタリア)、ホンモス(エジプト)、セビーチェ(ペルー)
スープ…カブのポタージュ(フランス)
メイン2種…ソーセージ(ドイツ)、タンドリーチキン(インド)
デザート…ニューヨークチーズケーキ(アメリカ)
なお、同イベントは月に1 回のペースで実施を予定。
5月までの日程:毎月第三木曜日、(1 月18 日、2 月15 日、3 月15 日、4 月19 日、5 月17 日)
HIS世界一周旅行デスク:TEL 03-6836-2548
営業時間:平日/午前10:00~午後6:00 土日祝/午前11:00~午後6:00(電話 午前10:30~)








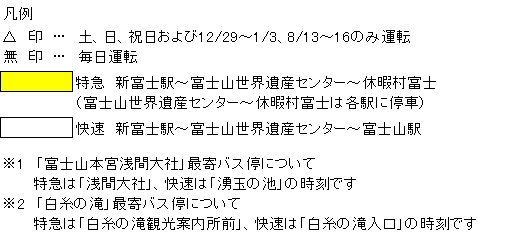
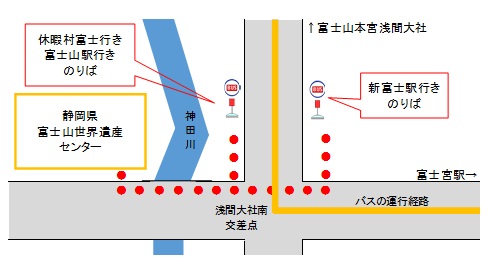
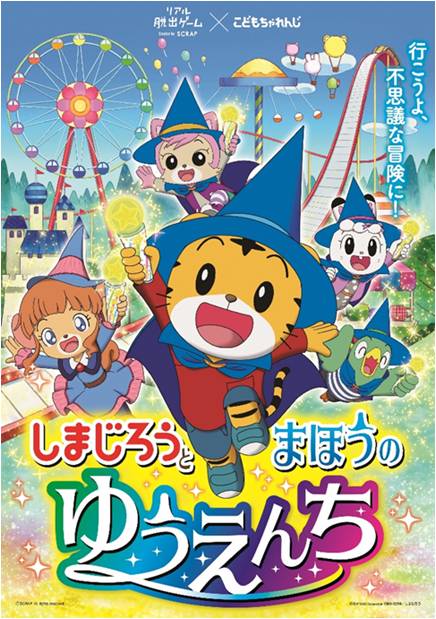
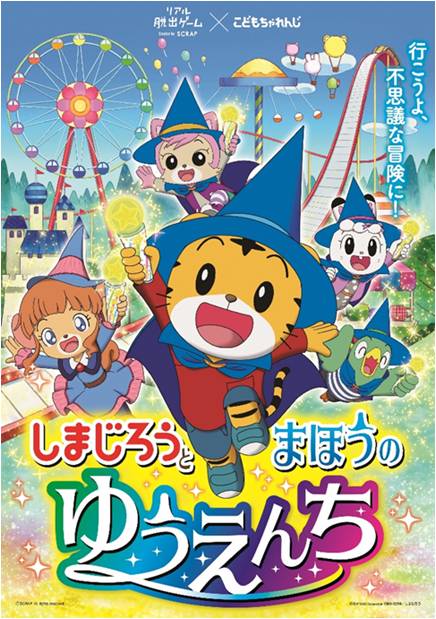











.jpg)
.jpg)