2017年12月25日(月) 配信

新島村商工会(東京都新島村)は、「東京の島を知らない若い世代へ向けて島の魅力を発信して欲しい!」とのテーマを掲げ、東京都内で映像を学ぶ学生らを募り、コンテスト形式による新島・式根島のPRイベントを開く。
2018年1月20日(土)には、伊豆諸島・小笠原諸島のアンテナショップ「東京愛らんど」で授賞式を開催。これに伴い、同コンテストのようすをSNSなどで発信する一般審査員10人の募集を開始した。
□学生による映像で東京の島を知らない若者たちへ向けて伝えるコンテスト
授賞式では、未来の金の卵になり得る新人クリエイターらの作品づくりに込めた想いや秘話を聴くことが可能。事前に参加表明をした人には、「世界最香峰セット」でお馴染みのくさや&ファブリーズ、新島・式根島の温泉セットをプレゼントする。2018年1月13日(土)までに東京愛らんどHPから応募する。
審査員には事前投票を含めて、東京宝島推進委員会委員長を務めるグラムコの山田敦郎社長をはじめ、東海汽船の山崎潤一社長のほか、プロの制作者として脚本家・演出家でもあるフジテレビ「ナースのお仕事」両沢和幸監督、「THE LAST MESSAGE 海猿」ラインプロデューサーの森井輝氏、日本テレビ「はじめてのおつかい」プロデューサーの福与雅子氏など。そのほか、「東京R不動産」林厚見氏、「日本仕事百貨」ナカムラケンタ氏など多岐にわたる豪華な顔ぶれ総勢17人を予定している。
□開催概要
日時:2018年1月20日(土)午後5:00~7:30 作品発表&表彰式
午後7:30~8:30 試食会
場所:伊豆諸島・小笠原諸島のアンテナショップ「東京愛らんど」
東京都港区海岸1丁目12-2 竹芝客船ターミナル
□5作品/4チーム
作品名:Follow me
チーム名:BUZZ(東洋大学×城西国際大学)
作品名:また来たいと思ってもらえる、島でありたい
作品名:式根島ベイベー
チーム名:東京デザイナー学院
作品名:式根島姉妹旅
チーム名:コンタクト(日本工学院専門学校)
作品名:きっと出会える、新しい自分
チーム名:STAND UP!!(日本工学院専門学校)
□「映像のチカラコンテスト2017」公式サイト
.jpg)

-e1514163847843.jpg)
-e1514163847843.jpg)
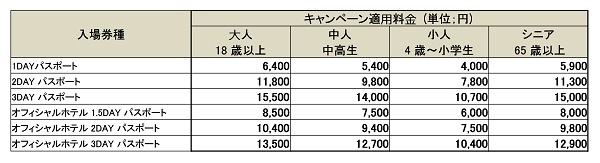






のイメージ.jpg)
のイメージ.jpg)



、下竹原成美女将(同3人目)が運営委員長に-e1514165584379.jpg)
、下竹原成美女将(同3人目)が運営委員長に-e1514165584379.jpg)
.jpg)
.jpg)
