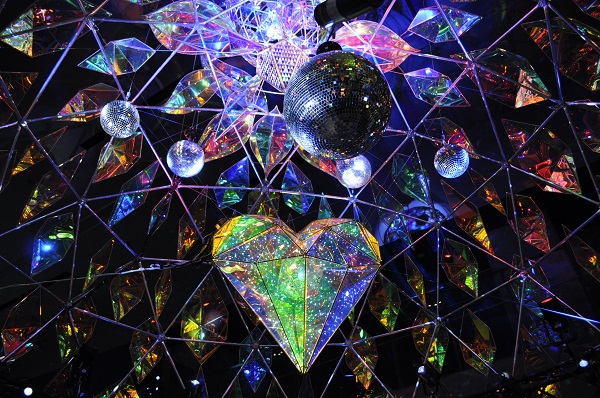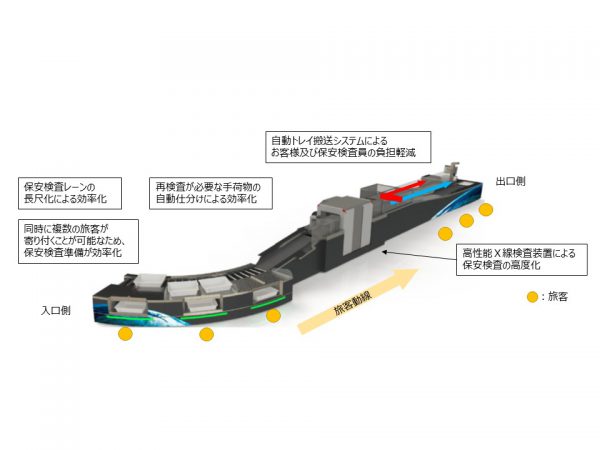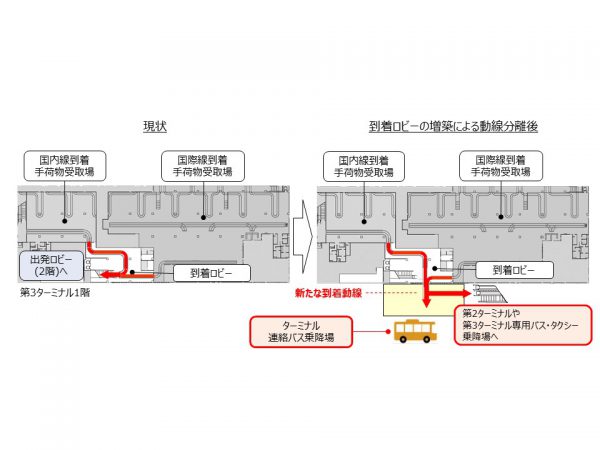2017年12月2日(土) 配信
.jpg) 一つひとつに異なるメッセージ(画像はイメージ)
一つひとつに異なるメッセージ(画像はイメージ)
1年前に発足したプロジェクトチームのメンバーと1年間かけて創り上げたのが、クレドでした。リッツカールトンが企業の信条、理念、大切にすべきものを明確にして日本企業に広め、社員がその想いを受けて実行するものとして多くの方に知られています。
ただ、残念ながら数カ月するとそれを失くしたり、数年後にはつくったことすら忘れてしまう企業も多いと聞きます。その原因は、つくることそのものが目標となっているからです。
そこで、クレドの完成は手段であって、その先のスタートラインであることをプロジェクトチームの最初の会議で伝えました。つくる過程は、組織の枠を越え目標に向かって社員が1つになることです。
そのために、プロジェクトメンバー全スタッフを集め、全社集会を何度も開いて語りかけてもらいました。役員への報告会などを経て、1年がかりでクレドを完成させたのです。その項目数は30にのぼり、リッツの20を超える多さです。
発表は完成から数週間後に予定されている周年パーティーの席場です。クレドを覚えると同時に、そのクレドの想いを実現するための行動を取らなければなりません。どんな行動を参加者にお見せするか、夜遅くまで会議が続きました。
そして、当日の参加者から「これはすごい」と驚かれる行動が1つあります。それは、参加者の席札です。参加者一人ひとりの情報を得て、その席札に個別のメッセージを書いたもので、誰もが手に取ると、すぐに隣の人と見せ合いました。
「これってみんな違うの」「すごいね」。参加者200人の一つひとつに異なるメッセージが書かれていたのです。持ち帰りのプレゼントに、200個用意した袋を順番に渡せば簡単ですが、袋の中には個別の名前で書かれたお礼状が入っています。間違わないように渡すのは、本当に大変な行動だったと思います。
しかし、手間を掛けた分は確実にお客様の笑顔につながりました。大切な記念のパーティーでミスは許されません。難しいことを企画して、もし失敗したらどうすると、一般的には考えてしまいます。だから、失敗のない無難な取り組みしかできないのが普通の企業ですが、彼らは果敢にもその難しいミッションに取り組んで行きました。
そして、幹部はそんなスタッフの想いを理解して、その行動に許可を出したのです。できあがったクレドからの初めての行動です。お客様の笑顔を本当にうれしそうに見るスタッフたちの表情からは、達成感と安心感、そして未来に向けての勇気を感じました。新潟グランドホテルのこれからの行動が本当に楽しみです。
コラムニスト紹介
 西川丈次氏
西川丈次氏
西川丈次(にしかわ・じょうじ)=8年間の旅行会社での勤務後、船井総合研究所に入社。観光ビジネスチームのリーダー・チーフ観光コンサルタントとして活躍。ホスピタリティをテーマとした講演、執筆、ブログ、メルマガは好評で多くのファンを持つ。20年間の観光コンサルタント業で養われた専門性と異業種の成功事例を融合させ、観光業界の新しい在り方とネットワークづくりを追求し、株式会社観光ビジネスコンサルタンツを起業。同社、代表取締役社長。
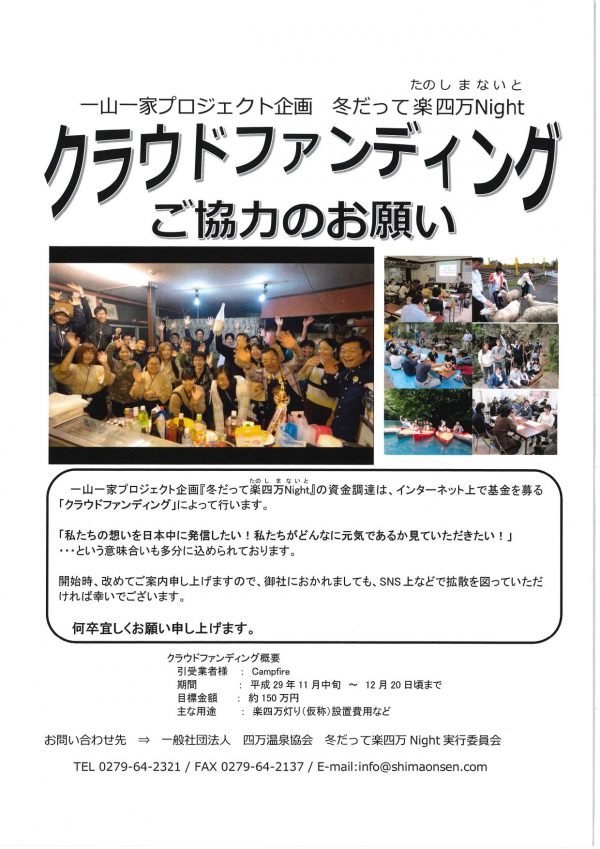
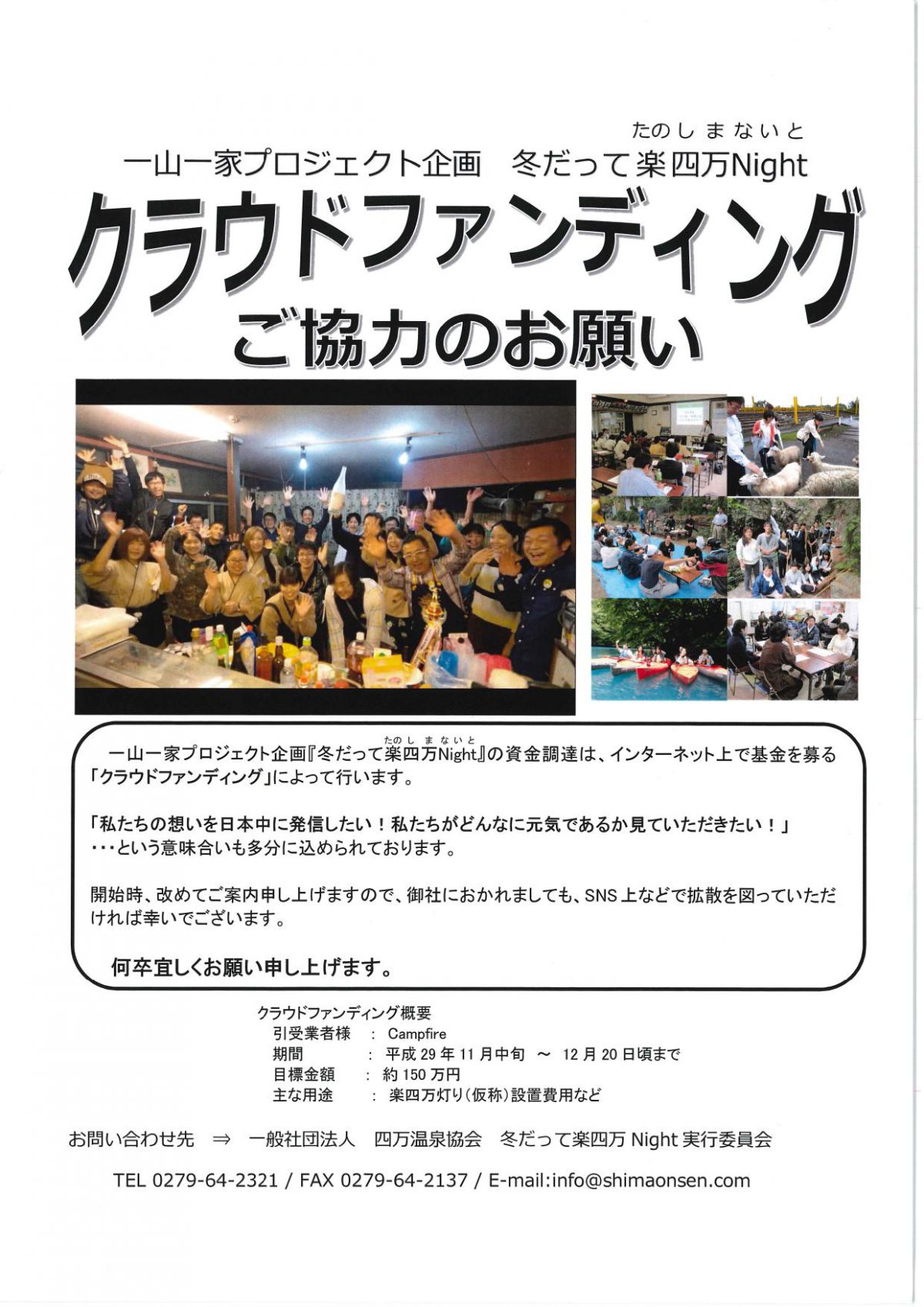








.jpg)
.jpg)