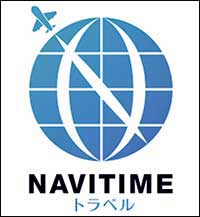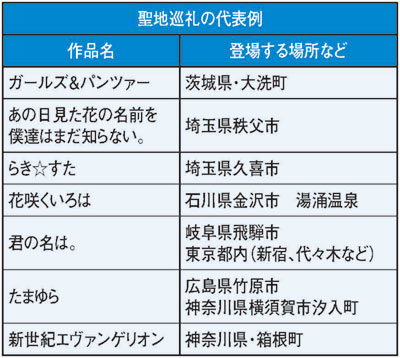情報通信技術(ICT)を活用し、飲食店の経営サポートに取り組んできたぐるなび(滝久雄会長)は近年、“LIVE JAPAN”や“ぐるたび”など、観光客を対象としたサービスにも尽力している。今回、インバウンド事業を中心に、同社執行役員の杉山尚美氏に話を聞いた。スピーディーかつ丁寧な事業展開に注目したい。
【謝 谷楓】
――力を入れているインバウンドについて、始めたキッカケや、ぐるなびの役割について教えてください。
ぐるなびは、2013年にインバウンド室を創設し、本格的な活動をはじめました。一方、その前年には、ぐるなびの関連会社のぐるなび総研でインバウンド研究会を立ち上げており、知見を深めていました。13年は、富士山と和食がユネスコの文化遺産と無形文化遺産となり、オリンピック・パラリンピック東京大会が決定した年で、インバウンドブームよりも一足早く準備を進めることができました。
ぐるなびの役割は、サポーターとして、加盟店をはじめとした飲食店の継続経営を手助けすることです。インバウンドの取り込みは、国内消費が減少しているなか、外食産業活性化のために必要不可欠だと考えています。
インバウンド室を設立した年から、加盟店向けのインバウンドセミナーを行ってきました。当初は、「本当に必要なのか」といった声も上がりました。しかし今では、年間で331回(15年実績)のセミナーを開催するまでになりました。とくに昨年は、外食チェーン各社を含め、多くの加盟店が、「インバウンドの取り込みをやらなくてはならない」という意識を持つに至った、機運の年だったと思います。
――流れが大きく変わっていったのですね。具体的に行っている取り組みは。
外国人が日本に来る大きな理由の1つに、日本の“食”があります。それを楽しめる環境を目指して、15年1月に、ぐるなび外国語版サイトをリニューアルしました。
多言語での情報発信は、04年から行っていますが、これを機にメニュー名だけでなく、食材や調理方法、調味料、アルコールの度数などといったお酒の情報も多言語で発信できるようにしました。多言語化は、コース料理やメニュー数にもおよぶため、リニューアルしたWebサイトは、飲食店が発信する情報すべてを網羅したことになります。
――日々忙しい加盟店にとって、日本語のメニュー名を外国語に翻訳してもらえることは、とても便利で助かることだと思います。
日本語のメニュー名はとても複雑なため、直訳しただけでは、外国人観光客に理解してもらえません。また、加盟店にとっても、自店のメニュー名がどのように翻訳されているのかということはとても気にかかることです。
ぐるなびには、20年間培ってきたビッグデータがあり、それを活用することで、意味や言い回しが似たものを整理することができました。その結果、900万もあった日本語のメニュー名を、現在では2800の名で表現できるようになりました。翻訳をするうえで、担保となるメニュー名ができたのです。これは、加盟店であれば利用できるオリジナル辞書変換システムとして、Webサイトに搭載しています。加盟店が、日本語の操作だけで、自店のメニュー名から食材や調理方法、調味料などを多言語で情報発信できるインフラを整えたのです。
――多言語での情報発信は、どれくらいの加盟店で行われていますか。
開始してから1年半経った現在、2万店以上の加盟店が行っています。
――取り組みのスピードがとても速いと思います。ビジネスにおいて、常にそのようなスピード感を重視しているのでしょうか。
現在の状況は、私たちがぐるなびを立ち上げたときにとても良く似ています。1996年当時、インターネットはあまり普及しておらず、「なぜインターネットなのか」と考える飲食店も多くあり、そのような状況下で、活動していました。インバウンドの時代がすでにやって来た現在、19年のラグビーワールドカップや、20年のオリンピック・パラリンピック大会などを考えれば、一刻も早く準備をしていかなくてはなりません。スピードの速さは、加盟店をはじめとした飲食店の売上や利益につながるものを、どこよりも早くつくっていかなくてはならないという使命感の結果なのです。
“食”が、外国人観光客にとって、日本を訪れる目的であるなか、飲食店自らが情報発信するすべを持たないことは、リピーター獲得の大きな機会を失うことを意味します。日本の、四季ごとの旬な食材を使ったメニューを各店からリアルタイムに発信できれば、自然と正しい情報が海外に伝わり、「今回は春に訪れたけど、次は秋に訪れてみよう」という“食”を通じたリピーターづくりが期待できます。また、全国の各地域に根付いた郷土料理を発信できれば、「今回は北海道で、次回は愛媛県に行こう」という“食”を通じた地方誘客もできるのです。
――ぐるなびは、加盟店自身が主体的に情報発信できる環境を用意しているのですね。環境を提供する側として、加盟店に求めることは。
インバウンドで言えば、国籍でお客様を選ばず、“インバウンド、歓迎”の意識をつくってほしいという想いがあります。外国語を話せる以上に、受け入れる気持ちをしっかり持つことの方が重要なのです。あとは、ぐるなびのWebサイトを使った英語のメニューづくりや、よくあるトラブルの対応といった準備をすれば十分ではないでしょうか。
――13年当時、インバウンドへの関心は今ほど高くありませんでした。“食”を通じてインバウンドに取り組む発想の原点とは何ですか。
03年にはビジット・ジャパン・キャンペーンが始まっており、06年の観光立国推進基本法制定や、それから2年後の観光庁設立というように、観光に対する政府の考え方は一貫しています。日本の産業が発展していくためには、観光が必要だということは既知の事実だったと思います。その当時から、外国人観光客の主な訪日目的は“食”にありましたから、先んじて準備をしていくという考え方がぐるなびにはありました。そのことが、発想の原点だと思います。
――スピーディーに情報をキャッチしているのですね。アジアなど積極的に展開していますが、今後の展望は。
現在、ぐるなびはシンガポールと台湾、香港、上海の4地域に拠点を構えています。今後は、ぐるなびが海外レストランを組織化して、インバウンドの取り込みと食材輸出の促進に貢献できるのではないかと考えています。
農林水産省の発表によれば、世界には9万店の和食レストランがあります。インバウンドの取り込みの点では、現地のレストランや料理人を組織化することで、レストランを媒体とした訪日プロモーションの可能性に注目しています。組織化はすでに行っており、例えば、10月18―31日間に、台湾で東北推進機構(清野智会長)と連携したイベントを開催する予定で、現地和食レストランを通して、東北食材のPRや東北へのインバウンド増加を促します。
また、和食レストランにかぎらず、日本の食材に興味を持つ料理人は多いため、海外のレストランは、日本の食材の輸出先になると考えています。
観光と食材の輸出は必ずつながっているものです。例えば、海外のレストランで東北の食材に興味を持った方は、東北にも訪れたいと思うはずですから、双方向でシナジーを生むことができるのです。
――加盟店と食材生産者をつなぐからこそできることだと思います。旅館など宿泊施設へのアドバイスがあれば教えてください。
加盟店には、日本と地域の食文化を発信するのだという視座の高い使命感を持ってほしいということを伝えています。ぜひ宿泊施設にも、このような使命感を持ってほしいと思います。とくに旅館は、日本の文化や考え方、感じ方を伝えるといった使命も持っているのではないでしょうか。
――ぐるなびでは、“食”と旅行をつなぐサービスが充実しています。今後の活躍にも期待がかかります。ありがとうございました。