2020年7月13日(月) 配信
.jpg)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、実施が危ぶまれていた毎年恒例の「諏訪湖サマーナイト花火」の開催が決定した。8月1―22日の22日間(雨天決行、荒天時中止の場合あり)。時間は毎晩午後8時30分から約15分間。玉数は1日約800発、打ち上げ場所は諏訪湖初島。
今年5月には、8月15日に開催を予定していた「第72回諏訪湖祭湖上花火大会」と、9月5日に開催を予定していた「第38回全国新作花火競技大会」の中止が既に決まっていた。
5月25日に開催された政府の第36回新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、7月10日から県をまたぐ観光目的の移動の緩和、イベント開催についても8月1日以降は人数制限の上限がなくなることが発表された。
そこで3密対策を実施しながら、諏訪での経済活動へのレベルを引き上げる取り組みを行うことにしたという。
具体的な3密対策は、「15分間(短時間)での打ち上げ」や、「諏訪湖畔でのスピーカーを通じての音楽放送は行わない」など。今回新たにイベントスタッフを配置し、発熱や感冒症状のある人の参加自粛や、行事の前後における3密の生じる交流の自粛、手指の消毒、マスク着用などの協力要請を行う。諏訪湖畔には注意看板を設置する。
さらに、地元ケーブルテレビのエルシーブイとの協業により、サマーナイト花火打ち上げに伴う注意事項や、諏訪湖畔でのスピーカーを使用しない代わりに音楽をFMラジオから放送する。FM放送はスマートフォンアプリ「FMプラプラ」を事前にダウンロード(無料)することでも聴くことが可能という。
地元ケーブルテレビのエルシーブイで毎日サマーナイト花火の生中継を行う。クラウドファンディングを実施し、花火打ち上げや諏訪市内の観光業界への支援を募る――などに取り組む。
なお、政府の緊急事態宣言などにより、イベント期間前、途中に関わらず中止する場合もある。
問い合わせ=サマーナイト花火実行委員会事務局(諏訪湖温泉旅館組合内) 





.jpg)






列車」家ージ.jpg)
列車」家ージ.jpg)
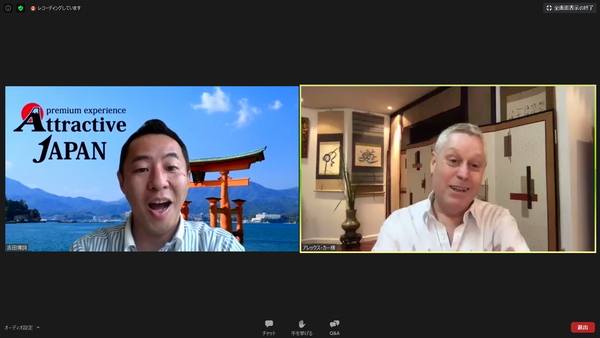
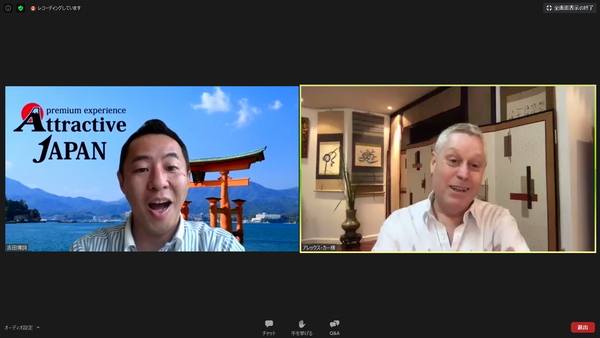













と野老朝雄氏(右端)ら.jpg)

