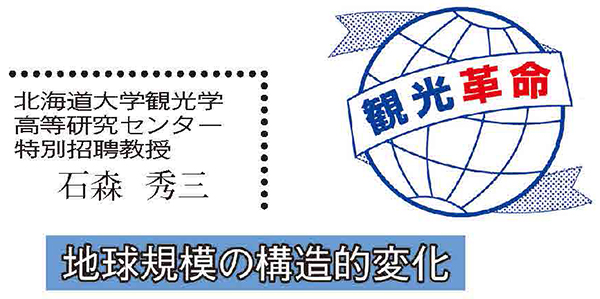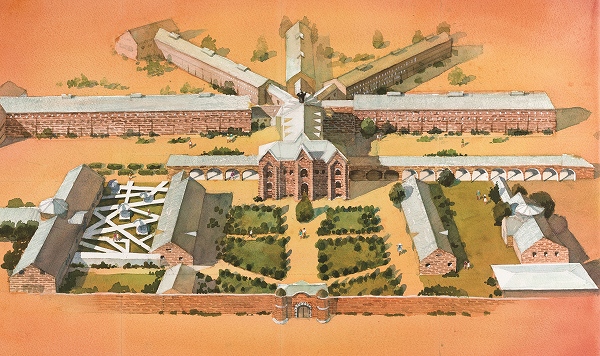2023年9月15日(金) 配信
 行動宣言書を国に手渡した
行動宣言書を国に手渡した
日本旅館協会(大西雅之会長)は9月7日(木)、伝承千年の宿 佐勘(宮城県・秋保温泉)で宿泊業界における観光と金融に関する全国懇談会を初めて開催した。会員宿の約4割が債務超過となるなか、同協会の会員や金融機関、行政の関係者など計300人が意見を交わした。基調講演には菅義偉前首相が登壇。コロナ禍からの完全脱却をはかり、夢のある宿泊業界の実現に向けて、行動宣言を採択した。
大西会長は「コロナ禍で宿泊業界は存亡の危機に追い込まれた。経営努力では対応しきれないコロナ禍からの立ち直りに向けた息の長い支援が欠かせない」と語った。
 大西雅之会長
大西雅之会長
そのうえで、「コロナ禍から立ち直り、夢のある宿泊業界の実現に向けた具体策を打ち出すために、活発に議論してほしい」と呼び掛けた。
また、「震災の影響が残るなか、処理水の問題で風評被害の解決をはかるため、魚介類の消費拡大に取り組む」と力を込めた。
来賓の西村明宏環境大臣(当時)は、環境省で国立公園へ誘客する国立公園満喫プロジェクトを実施していることを説明。これまで国立公園は人の手を触れさせない方針だったが、自然保護の理念だけでは、国民の理解は得にくいという。
これを踏まえ、「素晴らしい自然を知ってもらうことで、保護への理解を促したい。国立公園訪問時に宿泊施設は欠かせない。国としてできる限りの支援をする」と話した。
地元から村井嘉浩宮城県知事と、郡和子仙台市長も出席し、祝辞を述べた。
基調講演では、菅前首相が「これからのインバウンド観光と期待」をテーマに登壇。菅氏は「地方創生を訴える我が国で、地方を支えているのは観光業界の皆さんだ。苦難の中にあることは承知している。政府は中小企業応援パッケージなどで広く要望を受け止めているところ」と述べた。
 菅義偉前首相
菅義偉前首相
訪日旅行については、「宿泊客数が10の県で6割以上を占めており、それ以外の地域で拡大の余地が残っている。インバウンドの受入環境を地方の隅々まで広げる必要がある」と話した。受入強化で、国内旅行の閑散期にも需要を獲得できるため、「事業や雇用の安定につながる。全国の宿泊施設でインバウンドの受入環境が整備されることを期待する」と語った。
全国でタクシーなどの交通手段が不足し、日常生活に影響をもたらしていることにも触れ、「解決に向け、ライドシェアを含めた交通手段のあり方の結論を先送りするべきでない」と強調した。
「観光立国推進基本計画と今後の観光政策」をテーマに掲げた観光庁の髙橋一郎長官は、3月に閣議決定した観光立国推進基本計画で「持続可能な観光」、「消費額拡大」、「地方誘客促進」の3点をキーワードに掲げていることを説明。「(訪日観光客数などによる)オーバーツーリズム対策やマナー啓発、交通手段の機動的な確保に努め、持続可能なあり方で観光を再生する」と語った。
 髙橋一郎長官
髙橋一郎長官
これを踏まえた24年度の概算要求では、「宿泊業界が強く要望していた宿泊施設の改修や景観改善に資する廃屋の撤去の予算を計上した。面的に徹底的に改善してほしい」と話した。
処理水の放出による風評被害対策のための予算を要求したことについて、髙橋長官は「宿泊施設での水産物の提供イベントも対象になる。消費拡大を全面的にサポートする」と強調した。
□借換で融資期間延長 負担減で業績も改善 中小企業庁
「地域再生と中小企業政策」をテーマに掲げた中小企業庁の須藤治長官は、日本公庫のコロナ融資の返済開始時期のピークは21年と22年の6月、民間のコロナ関連の融資の返済開始時期は23年7月~24年4月に集中していることを説明した。
このうち、宿泊業については「6月末時点で約5割が返済中となっている。厳しい財務状況を受け、24年3月までコロナ借換保証制度を取り扱っている」と紹介した。
同制度は最長10年の融資に借り換えられ、そのうち最長5年を元本の返済が猶予される据置期間に設定できるため、融資期間や据置期間を延ばす効果を発揮する。
業績改善事例として、全国旅行支援の効果によって、コロナ禍前の90%ほどまで業績が回復した一方、光熱費のなどの高騰で経費負担が増で、運転資金の調達と資金繰りの安定のため同制度を利用した旅館を紹介。同旅館は返済負担の減少で業績の回復につながったという。
須藤長官は「コロナ借換保証制度の活用で業績改善事例も挙がっている。皆様の状況を注視しながら、資金需要に応えていきたい」と話した。
□金融機関と未来へ 「深い融資の話を」 金融庁
金融庁の伊藤豊監督局長は「アフターコロナにおける金融行政」について語った。「宿泊業界は設備改修や人手の確保に向けての投資が求められるが、財務は厳しい状況だ」と指摘。「金融機関は融資によって共に未来へ進んでいくことが非常に重要になるので、宿泊業の皆様は出席している金融機関と深い話をしてほしい」と呼び掛けた。
パネルディスカッションは第1分科会で「今後の持続可能な観光振興のあり方」と第2分科会で「コロナ禍を乗り越えるための地域の金融機関との連携」、第3分科会で「東北の復興と観光振興に向けて」をテーマにそれぞれ実施した。
 第1分科会
第1分科会  第3分科会
第3分科会
このうち、「コロナ禍を乗り越えるための地域の金融機関との連携」では、日本旅館協会新型コロナウイルス対策本部副本部長の永山久徳氏が冒頭、登壇した各金融機関の観光振興に対する取り組みを聞いた。
 第2分科会
第2分科会
商工組合中央金庫常務執行役員の中塩浩幸氏は「22年10月、専門人材が在籍するコンサルティング室を設置し、集客力の向上に努めている。変化に強い社会の実現へ、精一杯取り組んでいく」と語った。
日本政策金融公庫常務取締役の佐々木祐介氏は「20年8月に新型コロナ対策資本性劣後ローンを始めた。これまで事業者8335先、1兆296億円融資した」と話した。
仙台を中心とした地域の事業を支援する七十七銀行頭取の小林英文氏は「コロナ関連融資は162件、67億円となる。個人客へのシフトをはかるための集客力強化へ事業再構築補助金の活用支援を講じた」と説明。「宮城県の人口が減るなか、県外の需要を取り込める観光業への支援に力を入れていく」とした。
これを受け、中小企業庁事業部金融課長の神崎忠彦氏は「旅館業は幅広く地域経済を支えている。各金融機関と連携して支援したい」と語った。
財務省大臣官房政策金融課長の芹生太朗氏は「(金融機関は)宿泊業に金利に納得してもらうため、経営改善ノウハウを指導するなど付加価値の提供することが求められる」とした。
金融庁監督局長の伊藤豊氏は「コロナ禍からの回復への希望が見えるなか、今は再起に向けた知恵を絞るとき。旅館業、金融機関と連携していきたい」と述べた。
日本旅館協会の永山氏は「官民一体となった金融課題の解決へ連携し、支援の充実に努めていくことを確認できた」とまとめた。
会の最後には、地域における宿泊業界の役割は大きいことから、官民一体となった金融問題の解決でコロナ禍からの完全脱却をはかり、「再び夢のある業界」にすることを目指して、それぞれの立場で最大限努力をする行動宣言を採択した。