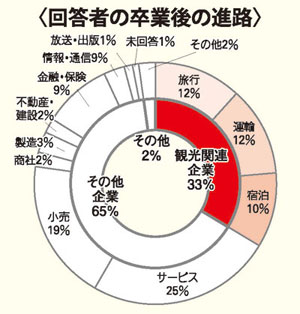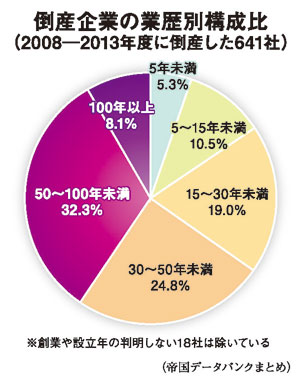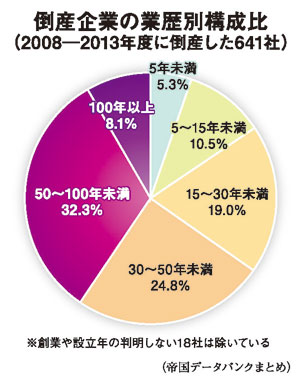先日、正午少し前に、丼物のチェーン店で安い牛丼を食べていると、店員が「いらっしゃいませ~。あちらの席で、合い席でお願いします」と来店してくる客に向かって指示した。1分置きくらいにお客が1人で入ってくると、また同じように1人で座っている客の席を指差し、「合い席」へと誘導した。
まだ正午まで時間があったので、店内の半分以上が空席になっているなか、オートマチックに、義務感強く「合い席」を叫んでいたが、大きな荷物を持つ客が「こんなに荷物が多いので合い席は勘弁してくださいよ」と隣の空席に移動すると険悪な雰囲気が店内に流れた。そして別のスタッフが水を持って来て一言、「お客さんが来たら合い席でお願いします」。
この店のスタッフは「いらっしゃいませ」のほかには、「合い席でお願いします」しか言っていない。大混雑時なら分かるが、まだまだ店内はガラ空き状態で、来るべき正午に向け、オモチャのように狭いテーブルにお客を「合い席」へと誘う。「合い席」はどうしても席が足りなく、お客に詰めて座ってもらう最終手段ではないのかと思うのだが、そのチェーン店の方針は違うらしい。テトリスの競技のように客を「まずは合い席で埋めていく」仕方だ。
¶
会社が秋葉原に近いせいか、周りにはインド人やトルコ人などの外国人が経営するエスニック料理店も多い。どのレストランや居酒屋に入っても今や外国人スタッフが接客する姿が自然に見られるが、エスニック料理店はその国を代表している意識が強いのか、テーブルも広く、ゆっくりと過ごせる空間づくりをしている。料金設定も価格競争に参入せず、母国人のスタッフは、すぐに辞めないで長く続いているようだ。昨今、日本の「おもてなし」がやたらと話題になっているが、日本のおもてなしと比べても遜色ないし、むしろ上である。当たり前のことだが、どの国であっても他国に負けない、自国文化の誇りである「ホスピタリティ」の心を持ち合わせているのだ。
¶
サービス業では、社員やアルバイトが集まらないとか、長続きしないという話をよく聞く。
知識や技術の習得まで時間がかかる専門職は、一度スキルを習得すると、一生食べていける職種もあれば、重宝される人材として長く雇用される傾向が強い。また、営業職では仕事内容よりも、お付き合いしている顧客との人間関係を一生大切にし、そこに自分の成長と存在価値を見出していく人も多い。
¶
サービス業も日々の接客のなかで、コミュニケーション能力に磨きをかけていけば、待遇も年々厚くなり、プロとして重宝され、長続きもするはずである。しかし、なぜサービス業ではスタッフが慢性的に不足する人材難に悩まされ、長続きしない難局が続く企業が多いのか。
最大の要因は働く人のモチベーションが上がらないからである。では、なぜスタッフの働く意欲が上がらないのか。この店でサービスするのが自分でない他の誰であっても変わらないことに「空しさ」を感じるからである。自分でない誰であっても、店の売上に大きな影響がない状況に、サービス業で働く人の誇りが得られるはずがない。自社の経営の勝敗が値引きなど価格競争が主で、「サービスはオートマチックでいい」では、慢性的な人材難は永久化するだろう。
(編集長・増田 剛)