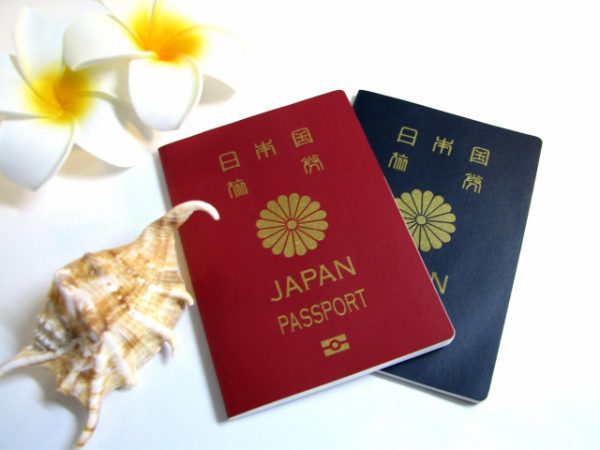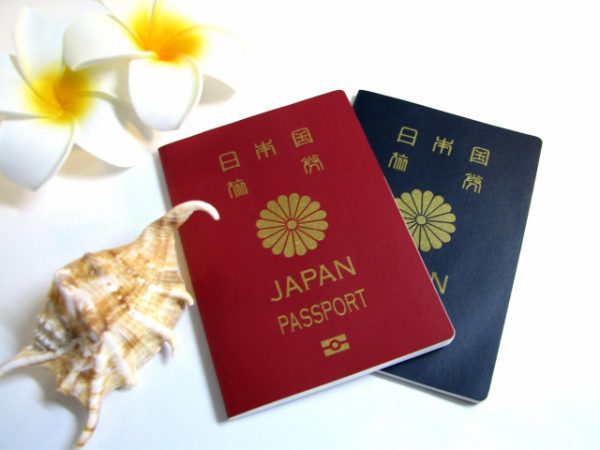2017年11月15日(水) 配信
 アパホテル岡山駅東口 新館 完成予想外観パース
アパホテル岡山駅東口 新館 完成予想外観パース
全国でホテルネットワークを展開する総合都市開発のアパグループは2017年11月13日(月)、「アパホテル岡山駅東口」に隣接する計画地で、新館の起工式を執り行った。
 アパホテル岡山駅東口 新館増築起工式
アパホテル岡山駅東口 新館増築起工式
アパグループの元谷一志代表は、「本ホテルは山陽新幹線の停車するJR岡山駅から徒歩圏内で、四国の玄関口としての役割も担っている立地である。新館149室増築後は総客室数287室となり、露天風呂付き大浴場を有するランドマークホテルとなる。ホテル建設により宿泊需要の増加は多くの観光客を取りこみ、新たな需要を生み出すことで地域のにぎわい創出に貢献していきたい」と発言した。
アパホテル岡山駅東口は、旧ホテルサンルート岡山を買収し、2010年10月19日にオープン。客室、共用部のリニューアルなどを行い、2012年7月20日にリニューアルオープンし、本年で7周年を迎えた。昨今の国内観光需要やインバウンドの増加、年間稼働率が順調に伸び続けていることも相まって、今回の新館増築を決定した。新館増築後は総客室数287室、客室総収容人数498人となり、新たに大浴場・露天風呂を設置し、「癒し」と「くつろぎ」を提供する。
アパホテル岡山駅東口の新館は、ホテルグリーン・ドゥ(本社・東京都港区)が事業用地を賃借し、ホテルを建設、施設竣工後、アパホテルに当該建物を賃貸し、アパホテルがホテル運営を行う土地有効活用プロジェクトとなる。構造・規模は鉄骨造、地上7階、全149室(ダブル148室、デラックスツイン1室)。設計はIAO竹田設計、施工は熊谷組、デザイン監修は辻本デザイン事務所が担当し、2018(平成30)年冬の開業を予定している。
□アパホテル岡山駅東口新館の主な特徴
① 2階に大浴場・露天風呂を設置
準天然温泉「光明石温泉」導入予定。
② 地球環境に配慮した「エコ仕様」
全館LED照明採用。ガスヒートポンプエアコンにより電気使用量を削減。高効率ガス給湯器、ガス・コージェネレーションシステムにより排熱を有効利用。複層ガラス・遮熱カーテンにより断熱効果を向上。
③ 全客室にエコと快適性を兼ね備えた「アパホテルオリジナルユニットバス」導入
ゆったり入浴できる卵形浴槽(通常より約20%節水)、サーモスタット付定量止水栓、節水シャワーを採用。
④ 全客室に眠りへのこだわり「アパホテルオリジナルベッド『Cloud fit (クラウド フィット)』」導入
さらに、ベッドとの相性を科学的に検証し開発したオリジナル3Dメッシュまくら(エアーリラックス)、高級羽毛布団(デュベ仕様)を採用し、「眠りへのこだわり」を追求。
⑤ 全客室に50型以上の大型テレビを設置
さらに、最上階のデラックスツインルームに60型クラスの大型テレビを採用予定。
全客室にVODアパルームシアター(1泊1千円で162タイトル以上見放題)完備。
⑥ 「明るいホテル」をコンセプトとして、全客室にLEDシーリング照明を設置
⑦ 客室の照明・エアコンのスイッチ・リモコン・USB充電専用コンセントをすべてベッド枕元に集約
⑧ 無料Wi-Fi接続サービスの導入
ロビー及び全客室に通信速度とセキュリティ面で優れたWi-Fi無料接続完備。
⑨ ハイグレードアメニティの導入
⑩ BBCワールドニュース 無料放映






.jpg)