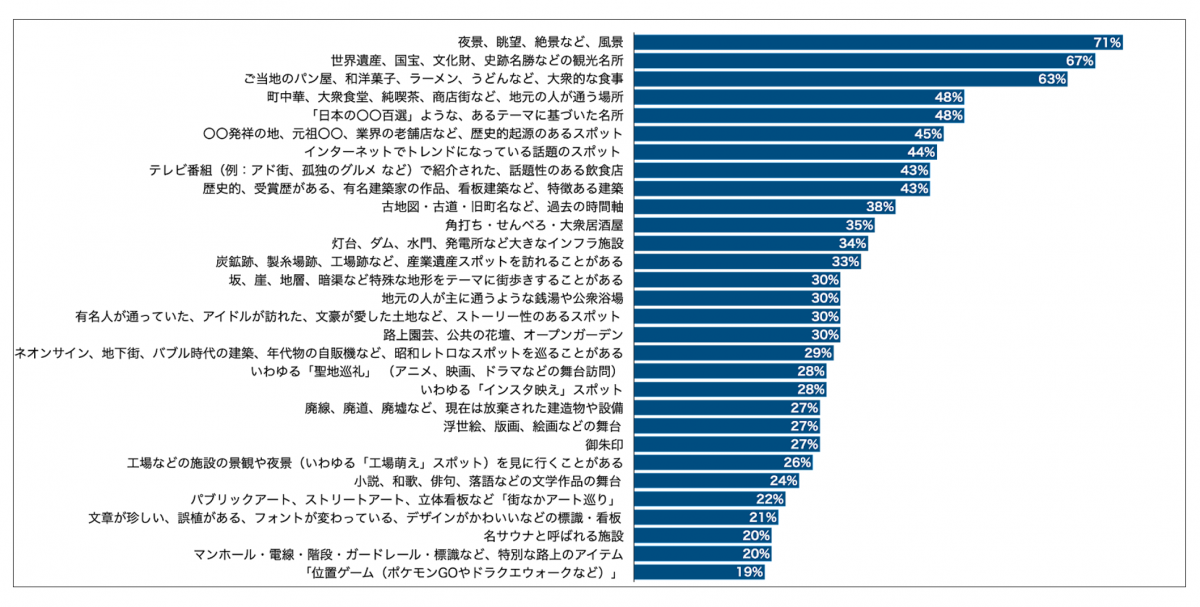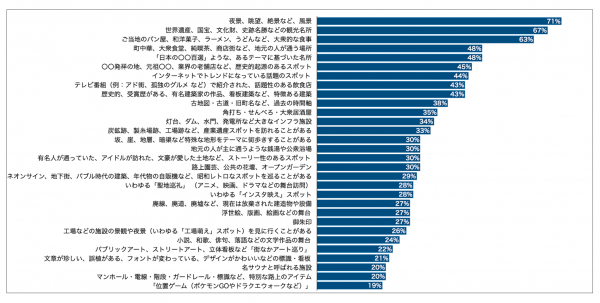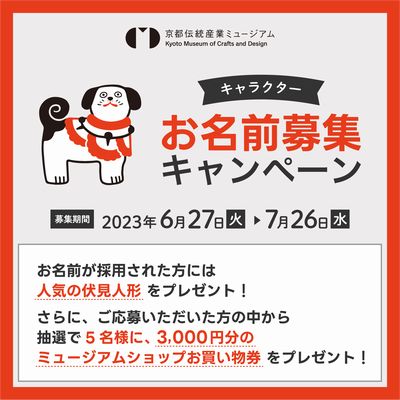2023年6月27日(火) 配信

ジェットスター・ジャパン(片岡優社長、千葉県成田市)はこのほど、7月3日(月)に就航11周年を迎えるにあたり、「11」にちなんだセールやキャンペーンなどを開始した。
11周年を迎える4つの就航地の商品が毎日11人に当たるTwitterフォロー&リツイートキャンペーンを7月1日(土)まで実施。また、6月30日(金)~7月3日(月)まで、運航開始年にちなんだ2012席限定で、往復購入時に復路が1111円になるセールを行う。
このほか、「VELTRA」との連携を開始し、対象「ジェットスター・アクティビティ」が11%オフになるキャンペーンを7月3日(月)~31日(月)まで展開する。
11周年当日は成田国際空港で就航11周年記念イベントを開く。公式キャラクター「ジェッ太」や成田市観光キャラクターの「うなりくん」が搭乗客を迎える。