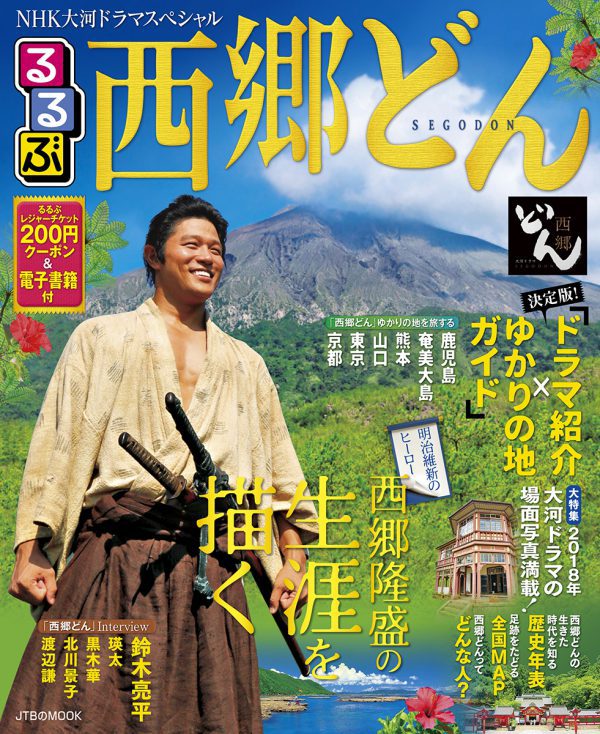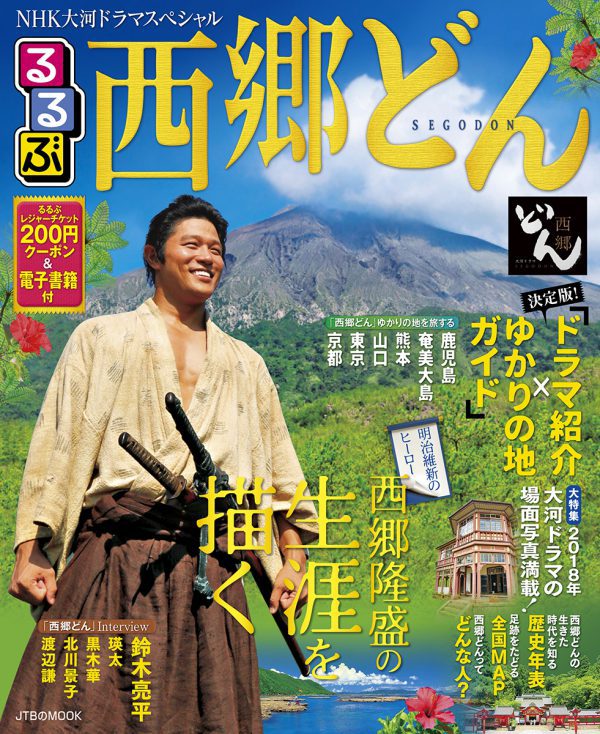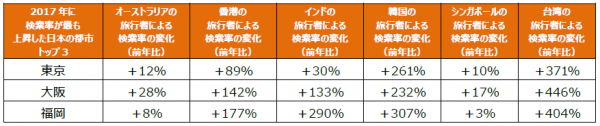2017年12月21日(木) 配信

ホテル イル・パラッツォ(福岡県)が12月21日(木)、楽天トラベル朝ごはんフェスティバル2017でグランプリを獲得した。4度目の挑戦で、栄冠を手にした。
全国の宿が、自慢の朝ごはんを競う「朝ごはんフェスティバル」。8回目となる今年は、47都道府県・1900を超える施設が参戦。最終審査には6宿が進出し、12月21日(木)東京・代々木にある服部栄養専門学校で決勝戦が行われた。
「アイデアや構成は得意でした。一方、パティシエということもあり、味の部分は仲間の料理人の助けがなければ実現できませんでした。感謝しています。フレンチとパティシエとしての技法をいかに応用できるかが課題で、地域の食材を取り入れる際にも一苦労しました」と、ホテル イル・パラッツォの山本大輔チーフ・パティシエ(パティシエシェフ)はインタビューに答える。
4年目の挑戦で栄冠を手にしたが、ここまでの道のりは順風満帆とは言えなかった。「初年は3位となったが、それ以降はなかなか思うような結果を出せなかった。昨年は一度チームからも外れた」と、今年はその悔しさをバネに参戦を決意した。創意工夫と仲間との協力プレーが、「モンブラン仕立ての明太子ポテサラ」を生み出し、最高の結果を導いた。


モンブラン風の見た目をしたポテトサラダは、甘くとろけるデザートのよう。パティシエとしての経験を取り入れることで、オリジナリティの高い「朝ごはん」が完成した。和食ならお米、洋食ならパンという固定概念を打ち砕く発想は、パティシエならではのもの。見た目へのこだわりは、審査委員の1人坂井宏行氏〈ラ・ロシェルオーナーシェフ〉からも高い評価を得た。
「一見してデザートという見た目には、とくにこだわりました。女性の方の興味を惹くだけでなく、普段朝食を食べないビジネスパーソンにも抵抗なく食べてほしいという思いがありました」。
なお、2位には、淡路島洲本温泉 海月舘(兵庫県)が選ばれた。淡路島の幸を取り入れた「島の朝鍋スープ~鯛と島野菜の鍋スープ」は、「子供も喜ぶ味付け。酢橘塩の旨味も抜群だ」と審査委員の神田川俊郎氏〈「神田川本店」店主〉が絶賛した。
箱根の名門、花紋は3位となった。決勝に臨んだ「富士山ポークと下仁田葱の香味汁」は、味噌を一切使わずに調理したもの。浜内千波氏〈料理研究家〉と坂井氏揃って、「味噌を使わないにもかかわらず、これだけ味がでるのはすごい」と驚きを隠さなかった。
□“ハイレベルな戦い”、コンマ3点を競う
全4人(神田川俊郎氏、坂井宏行氏、浜内千波氏、武田和徳氏〈楽天常務執行役員 ライフ&レジャーカンパニープレジデント〉)が審査委員を務めた今回の朝ごはんフェスティバル。プレゼンテーション後、「例年になくレベルが高かった」、「ハイレベルな戦いだった」という声が自然と湧き上がってきた。「コンマ3点を争う展開となった。ここにいることを誇りにしてほしい」と、神田川氏が審査委員を代表して、料理人らを激励した。

最終審査では、試食のほか、各施設のシェフと担当者によるプレゼンテーションも行われた。審査項目は7つ(美味しさ・コンセプト・表現力・独創性・地域性・朝ごはんとしての適切性・技術)で、多方面から高評価を得なくてはならない。
美味しさはもちろん、料理に対するこだわりといった独創性も重んじ、地域への密着度についても採点対象となる。プレゼンテーション中、多くの宿が「地産池消」をキーワードに据えて、料理を紹介している。地域のオリジナリティは、旅行者を惹きつける大切な要素であるだけに、欠かすことのできないものといえよう。
以下、2~6位の朝ごはんを紹介する。
山形県・ホテルイン鶴岡・「鳥海山伏流水で煮込んだ芋っこぼた餅汁」・小野 孝 調理長(5位)


郷土料理「芋っこぼた餅」の汁物に、三元豚や野菜を入れた。優しい味付けが特徴で、料理研究家の浜内氏は、「汁に雑味がなく、甘みがふんだん。とても感動した」と評価した。「もう少しご飯があっても良い」という声もあり、里芋とご飯の相性の高さが、好印象を呼んだ。
神奈川県・箱根湯本温泉 箱根 花紋・「富士山ポークと下仁田葱の香味汁」・岡田 和幸 料理長(3位)


味噌を使わず、ネギなど素材の甘みを生かしたという香味汁。具材のこんにゃくは、独特の匂いを抑える工夫を施した。調味料に頼らない、引き算の料理を目指した調理法に対し、「作っている方の人情味も感じる」という声が審査委員から上がった。暖かいものは暖かいうちに提供するなど、配膳時のおもてなしにも力を入れている。
兵庫県・淡路島洲本温泉 海月舘・「島の朝鍋スープ~鯛と島野菜の鍋スープ」・河津 啓佑 料理長(準優勝、2位)


淡路島の野菜と鯛をベースに、丁寧につくられたスープ。野菜は、栽培する畑に直接足を運び、料理長自らが厳選するこだわりようだ。なお最終審査前日、持参したお皿が割れるというアクシデントに見舞われてしまうも、無事準優勝(2位)に輝いた。宿は家族連れにも人気で、神田川氏は、「子供も喜ぶ味付け。酢橘塩の旨味も抜群だ」と絶賛した。今後も、朝から笑顔になれる料理をこれからも提供していきたいという。
三重県・ホテル 季の座・「三重の旬材・伊勢海老ふんわり出し巻き」・中西 眞 総料理長(6位)

宿では、ビュッフェスタイルで提供しているという出し巻き。地元のブランド卵「紀伊の鶏」は、桑の葉などを食べ、放し飼いされた鶏が産んだもの。伊勢海老と貝柱も入っており、三重県自慢の冬の食材をふんだんに使用した。子供からシニア、どの世代でも食べやすい料理を追求した。
福島県・磐梯熱海温泉 離れの隠れ宿 オーベルジュ鈴鐘・「メイプルサーモンとホタテの木の実焼き」・槻田 知己 料理長(4位)

地元では、生で食されることが多いというサーモン。体を冷やしてほしくないと考え、敢えて加熱したものを提供するのだという。試食中、坂井シェフが「サーモンが本当に美味しい」と思わず感嘆の声を上げた。ホタテと「阿武隈川メイプルサーモン」が口のなかで絡み合い、独特の旨味を生み出す。
| 順位 | 朝ごはん名 | 施設名 |
|---|---|---|
| 1位 | 「モンブラン仕立ての明太子ポテサラ」 | ホテル イル・パラッツォ |
| 2位 | 「島の朝鍋スープ~鯛と島野菜の鍋スープ」 | 淡路島洲本温泉 海月舘 |
| 3位 | 「富士山ポークと下仁田葱の香味汁」 | 箱根湯本温泉 箱根 花紋 |
| 4位 | 「メイプルサーモンとホタテの木の実焼き」 | 磐梯熱海温泉 離れの隠れ宿 オーベルジュ鈴鐘 |
| 5位 | 「鳥海山伏流水で煮込んだ芋っこぼた餅汁」 | ホテルイン鶴岡 |
| 6位 | 「三重の旬材・伊勢海老ふんわり出し巻き」 | ホテル 季の座 |