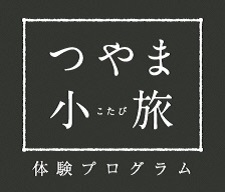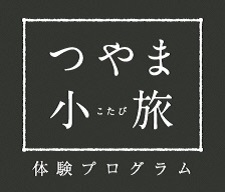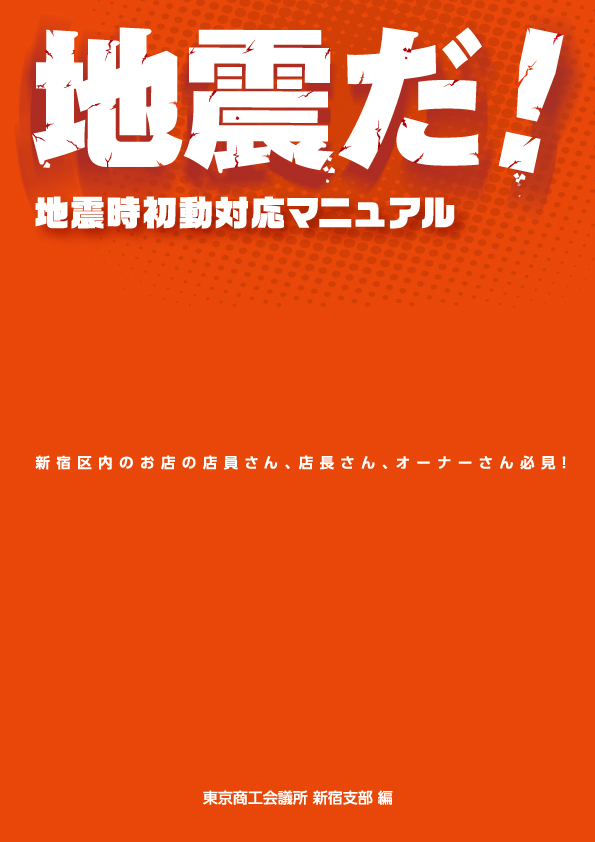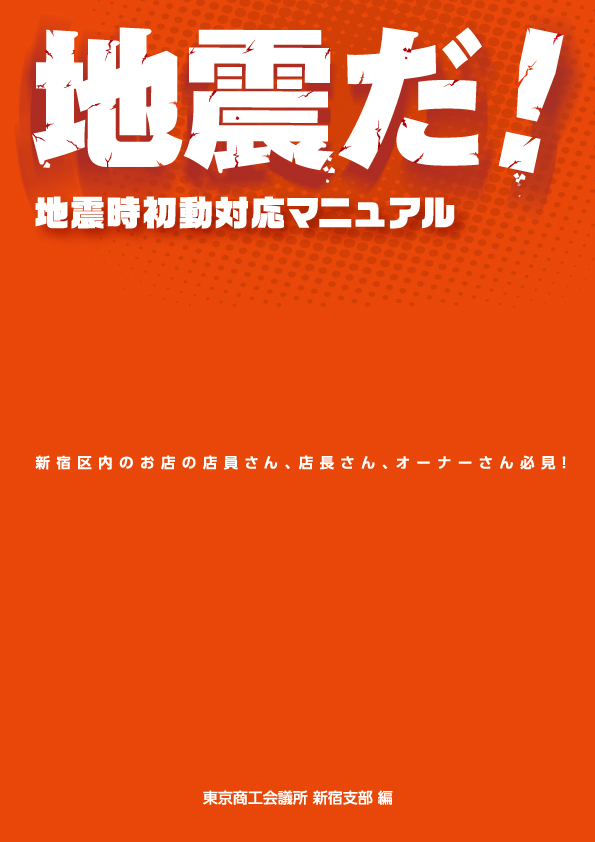2017年12月8日(金) 配信
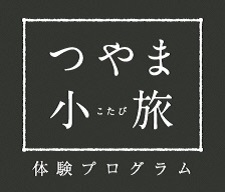 津山で特別な体験してみませんか
津山で特別な体験してみませんか
岡山県北部に位置する津山市は、2018年1月27日(土)~2月27日(火)の期間中、津山市の歴史・文化・グルメを1ランク上の楽しみ方ができる7つの体験プランを開催する。
着物姿で小京都・津山をまち歩きしたり、津山ジーンズでデニムポケット縫い付け体験をしたりなど、特別な体験プログラムを用意。よりディープな津山旅を楽しもう。
□3つのこだわりを紹介!
同プログラムは、次の3つのこだわりをコンセプトに、旅を盛り上げていく。
1.「楽しい!おもしろい!」
個人ツアー旅行では、味わえない特別な体験をすることができる。
2.「なるほど」
プログラムごとに“津山アドバイザー”が案内するので、より深く旅を楽しめる。
3.「感動した!美味しい!」
地元の人だからこそ知るグルメや文化に触れてここでしか得られない感動を手に入れよう!
□7つの体験プログラム
「着物で”小京都・津山”を散策&撮影会と古民家カフェで絶品のピザランチ!」
 着物を着て津山をぶらり
着物を着て津山をぶらり
好きな着物に着替えて、レトロな町並みが残る“城東町並み保存地区”をまち歩き。小京都と呼ばれる津山ならではの、インスタ映えする写真が撮れるかも……。古民家を改築した和風の内装と、津山産小麦を使用したこだわりのピザランチ(限定アレンジメニュー)も楽しんで。
開催日:2018年1月27日(土)、2月10日(土)
時間:午前9:30~午後2:10(午前の部) 正午~午後4:40(午後の部)
会場:町屋着物レンタル古都小町、水のや(津山市東新町)
参加費:7500円(着物レンタル一式、着付け、昼食、写真データ付)
定員:各日6人(各部3人)
「地元情報誌”JAKEN”ライターとめぐる津山カフェ・スイーツ食べ歩き」
 津山のカフェで美味しいスイーツを堪能
津山のカフェで美味しいスイーツを堪能
地元情報誌“JAKEN”。そのライターが発掘したスイーツ店やカフェを3カ所ピックアップして、食べ歩き。“JAKEN”のライターだからこそ用意できた今回だけの特別メニューも味わえる!
開催日:2018年2月22日(木)
時間:午前11:00~午後1:45
会場:
Bonheur(ボヌール)、SLOW CLOTHING AND CAFE´(スロウクロージングアンドカフェ)、モンレーヴカフェ(津山市大田ほか)
参加費:4800円(スープ・ランチ・ケーキ付)
定員:8人
「“珈琲”の名付け親“宇田川榕菴”の地、“津山”にてゴストーゾ!(おいしい!)淹れ方を学ぼう!」
 津山で珈琲の入れ方を学ぶ
津山で珈琲の入れ方を学ぶ
“珈琲”の漢字を考案した津山市出身の“宇田川榕菴(うだがわようあん)”にちなみ、津山ならではのディープな珈琲プログラムを開催!珈琲へのこだわりや自家焙煎にこだわりつづける、津山アドバイザーが、珈琲の説明や、美味しい珈琲の淹れ方を伝授。普段はあまり行わない、手網を使った自家焙煎作業や、ハンドドリップを実践!古民家を改修した、Ziba Platformで開催!
開催日:2018年2月4日(日)
時間:午後1:00~午後3:00
会場:Ziba Platform(津山市山下)
参加費:3500円(珈琲、津山ロール1カット付)
定員:10人
「作州絣工芸館で伝統文化を体験!絣織講座と卓上手織機でコースター作り」
 自分だけのコースターを作ろう
自分だけのコースターを作ろう
海外からも近年注目されている、日本の繊維文化。今回は、岡山県北部を中心に伝承されてきた手織り「作州絣(かすり)」の体験を行う。木綿の糸で織り上げた、鮮やかな紺と白の生地のやさしい色合いが特徴。作州絣の歴史、文化や織体験を学んだ後は、卓上手織機で自分だけのコースター作りに挑戦!普段は味わえない伝統文化を体験してみては。
開催日:2018年2月12日(祝・月)
時間:午後1:30~午後4:00
会場:作州絣工芸館(津山市西今町)
参加費:3500円(コースター持ち帰り付)
定員:8人
※英語通訳対応可
「“津山藩主”森家の菩提寺〔本源寺〕にて座禅・パワースポット体験で心身をリフレッシュ!」
 パワースポットで心身共にリラックス
パワースポットで心身共にリラックス
津山藩主・“森忠政”は、なんとあの“森蘭丸”の弟。津山には森家との深い縁があるという。今回は、森家の貴重な“守り本尊”を特別に公開!住職の温かい人柄に触れながら、初心者向けの座禅体験をすることもできる。パワースポットである森家の菩提寺、「本源寺」(ほんげんじ)で心身ともにリフレッシュしてみては。
開催日:2018年2月12日(祝・月)
時間:午前9:30~正午
会場:本源寺(津山市小田中)
参加費:2800円
定員:20人
「こだわり素材の津山ジーンズ・内田縫製にてデニムポケット縫い付け体験!」
 津山ジーンズのポケット縫い付けを体験
津山ジーンズのポケット縫い付けを体験
おしゃれにこだわる人たちに根強い人気の岡山デニム。そのなかでも、最近注目される“津山ジーンズ”。こだわりの津山ジーンズを作る「内田縫製」の陽気で真っ直ぐな社長がジーンズへの熱い想いを語る。さらにミニデニムウォールポケットに、ポケットの縫い付け体験をすることができる。(完成品は持ち帰り)
開催日:2018年2月27日(火)
時間:午後2:00~午後4:00
会場:内田縫製(津山市新野山形)
参加費:1500円(ミニデニムウォールポケット持ち帰り付)
定員:6人
「~全国的にブームの“山城”が津山にも!~戦国時代の拠点!岩屋城址歴史トレッキング」
 戦国時代の大名に想いを馳せる
戦国時代の大名に想いを馳せる
近年盛り上がりを見せる、各地の山城。津山にも毛利、宇喜多といった戦国時代の大名が奪い合った「岩屋城址」がある。その山城をトレッキングしながら山城の特長や歴史的な遺構などをめぐる。この機会に“兵どもの跡”に想いを馳せてみては。天気が良ければ山頂からは、津山市や真庭市を一望することもできる。
開催日:2月24日(土)
時間:午前10:00~午後2:00
会場:岩屋城城址・夢広場(津山市中北上)
参加費:1200円
定員:30人
お申し込み:
体験プログラムには公式ホームページから申し込み可能。
「新規会員登録」をしたうえで、該当するプログラムのページで参加費や日程を確認のうえ、所定の手続きにしたがってフォームに入力を行う。
※事前に登録すると、キャンセルによる空席情報をメールでお知らせ。
【注意事項】
※「つやま小旅 体験プログラム」への参加は事前申し込み制。
※各コースとも定員となり次第締め切り。
※キャンセルの場合、連絡時期によってキャンセル料が発生。
※プログラムは、天候や最少人員に満たない場合など都合により内容の変更及び中止する場合あり。
※児童の参加・同伴、ペットの同伴は不可。
※掲載している写真はすべてイメージ。
※掲載されている金額はすべて消費税込価格。
※申し込み後、詳細なプログラム概要や地図をお届け。
公式ホームページ
「つやま小旅 体験プログラム」
問い合わせ
「つやま小旅 体験プログラム」運営事務局(株式会社プロアクティブ内)
tel:078-392-1515
-e1512554727791.jpg)






-1200x1262.jpg)