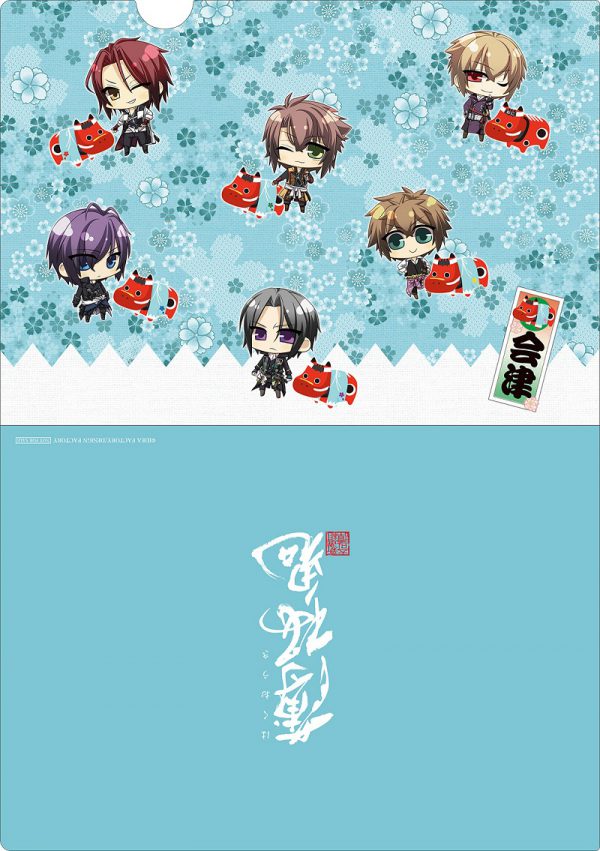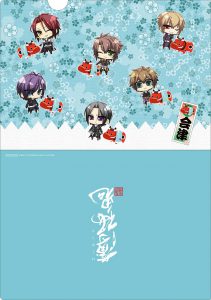2018年5月31日(木) 配信
 各県のゆるキャラも登場し盛り上げた
各県のゆるキャラも登場し盛り上げた
全日本空輸(ANA、志岐隆史社長)は6月から、地域活性化プログラム「Tastes of JAPAN by ANA KYUSHU―Explore the regions」を展開する。九州の特集期間は11月まで。
同プログラムは2013年から開始。航空機が就航していない地域や他社路線の地域も含め、4年3カ月をかけ1都道府県ごとに、全国47都道府県の魅力を機内などを通じて国内外に発信してきた。その第2弾として、昨年12月から広域の地域を対象とした特集を展開。期間も3カ月から6カ月に伸ばし、より旅行者のニーズにあった地域の情報を発信している。初回の対象は北海道のため、今回の九州が実質、県境を越えた初の地域特集となる。
5月29日(火)に東京都内で開いた会見で、自身も九州の出身だという志岐社長は「今回は6月から11月ということで、九州のさまざまな良いシーズンを紹介できると思う。広域の特集になり県を越えるのは初めてだが、九州は連携プレーが取れている。タッグの良さを示したい」と意気込んだ。
会見には各県の行政担当者も参加し、地域の魅力や特集への期待などを語った。九州観光推進機構専務理事の渡邉太志事業本部長は「我われは少子高齢化時代の九州の経済活性化を目指し、2022年に観光消費額4兆円を目標に掲げている。国内は災害が続きやや苦戦はしているが、安心して送客して欲しい。一方、訪日外国人観光客は目標に対し110%で推移している。今年の九州は話題が豊富。このキャンペーンが大成功するよう我われも精一杯努力していく」と述べた。
特集はANAグループあげて、機内や空港サービス、Webサイトなどあらゆる顧客との接点で多様な資源をPRするほか、旅行商品も展開する。また、伝統的工芸品産業振興協会と連携をはかり、伝統工芸品の発信も行う。
□「Tastes of JAPAN by ANA KYUSHU-Explore the regions-」
【旅行商品】
Tastes of JAPAN by ANAと連携した、九州各地の観光・グルメ・体験メニュー(九州満喫メニュー)が付いたWeb限定商品を発売。
設定期間:2018年6月1日(金)~10月31日(水)出発
設定発地:東京・名古屋・大阪
【機内や空港ラウンジで特産品を使った食事を提供】
国際線の機内食や空港ラウンジで、九州の特産品を使用した食事やデザートを提供する。会見では志岐社長らが試食し、「ぞれぞれの良さが出ていて美味しい。酒の肴としても合いそう」など感想を述べた。
 渡邉事業本部長(左)と志岐社長が試食
渡邉事業本部長(左)と志岐社長が試食
〈国際線ファーストクラス〉
・軽いスモークの紋甲烏賊と茄子のタルタル カレーとライム風味 宮崎キャビア1983添え
→欧米路線(日本発)※一部路線を除く/2018年6月~8月
・安納芋のスイートポテト(鹿児島)
→欧米路線(日本発)※一部路線を除く/2018年6月~8月
・和牛つくねと茄子の合い盛り(熊本)
→欧米路線(日本発)※一部路線を除く/2018年8月
〈国際線ビジネスクラス〉
・金星佐賀豚と茄子 胡瓜の葱塩浸し
→欧米・メキシコ・バンクーバー路線(日本発)※一部路線を除く/2018年6月~8月
〈羽田空港国際線 ANA SUITE LOUNGE 内 DINING h〉
・長崎県産 イサキのムニエル フレッシュトマトとガーリックフレーバーピストゥ―
→2018年6月
・大分県産 香菇の太刀魚挟み焼き
→2018年7月
・はかた地どりのソテー ココナッツの香り クレオール(福岡)
→2018年8月
【WEBでの通販・空港販売】
インターネット通販サイト「ANAショッピングA-style」特設ページで、各県の名産品・特産品を販売する。
【空港ラウンジで提供する日本の酒 “國酒”】
羽田・成田・関西の各空港のANAラウンジにて、6カ月間で合計76銘柄の九州の國酒を提供する。
【機内番組 『SELECTRAVEL』】

「SELECT(選択)」と「TRAVEL(旅)」を掛け合わせており、旅のおすすめルートを特集する番組。外国人タレントが同じエリア内の2パターンの地元ならではの旅を紹介する。外国人にとっては新発見、日本人にとっては再発見の完全オリジナルな旅となっている。
※国内線・国際線の機内の他に、YouTubeのANAグローバルチャンネルでも閲覧できる。
【機内誌 国内線『翼の王国』 国際線『WINGSPAN』での特集】
各月でテーマを設定し、九州の多様な資源を感じられる食材や観光地などを特集する。
【特集サイト】
特集する各エリアの情報や観光の魅力をWebサイトで紹介する。
(日本語サイト)
(英語サイト)
※英語サイトについては、6月下旬に訪日旅客向けの新サイト「JAPAN TRAVEL PLANNER」と統合予定のため、下記URLへ変更となる。(https://www.ana.co.jp/en/us/japan-travel-planner/tastesofjapan/kyushu/)











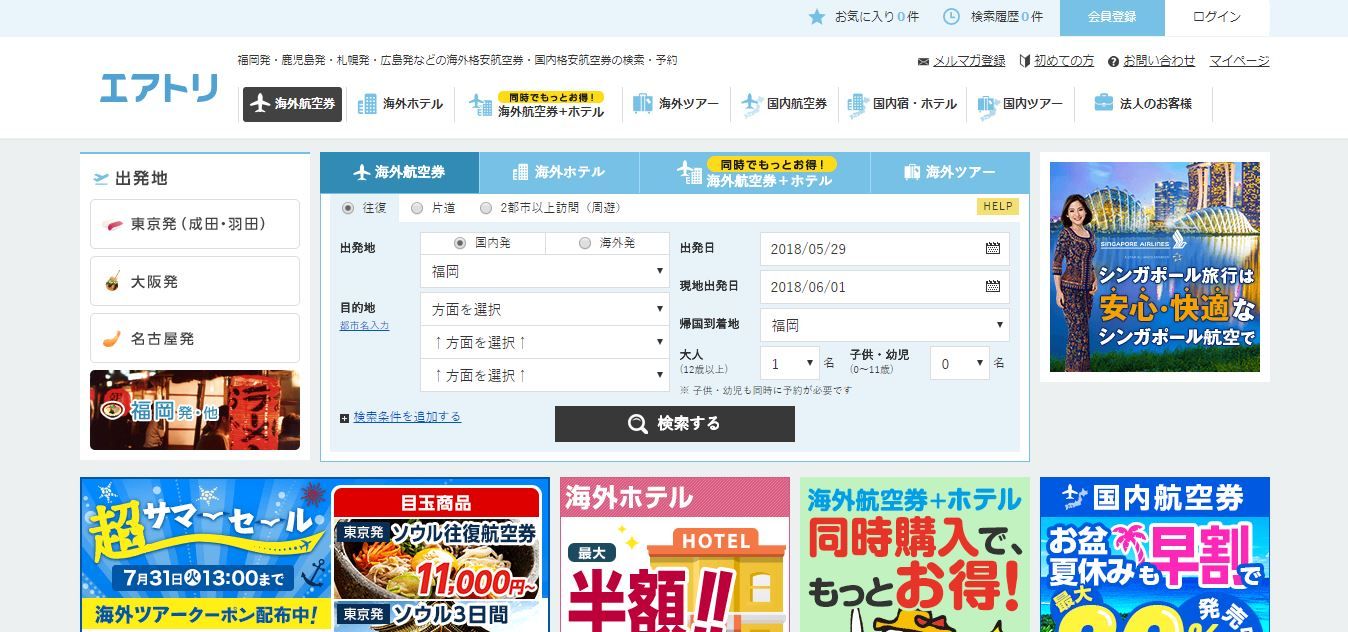


.jpg)
.jpg)
.jpg)