2020年3月7日(土) 配信
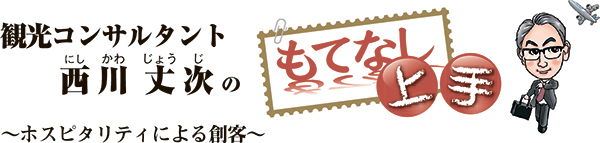
広島の講演で参加者に「広島のお土産を買って帰りたいのですが、何がいいでしょうか」と質問しました。すると、会場からは「もみじ饅頭」というたくさんの声が聞こえてきました。「もみじ饅頭」は広島の代表的な銘菓でしょうから、誰もが納得される回答だと思います。
ただ、実際に駅で買い求めようとすると、売り場には多くのメーカーのもみじ饅頭が種類豊富に並び、多くの人はどれが良いのかと、迷ってしまうと思います。一体何種類のもみじ饅頭があって、その味はどのように違うのでしょうか。それを、講演会の参加者に続けて質問をしてみると、当然のことですが、皆さん首をかしげていました。
よく聞くのは「お客様の好みはそれぞれ違いますからね」。確かにそうですが、お客様の質問に、こうした言葉で逃げてはならないと話しています。
「Aは老舗メーカーのもので、多くの方に人気です」。「Bは比較的新しいメーカーですが、バリエーションが豊かで、若い方々に人気です」。「Cは生地がおいしくて、私がよくお土産に買い求めるものです」。
このように、それぞれの特徴を伝えることで、お客様への応えに価値が生まれてくるのです。会場を出るときに、参加者の1人から「西川さん、今日の帰りに色々な種類のもみじ饅頭を買って、食べ比べをしてみます」と言われました。本当にうれしい言葉です。
ネットや雑誌で違いを調べるのではなく、実際に食べ比べをして、自身の言葉で目の前のお客様に伝えることが、最も説得力のあるものになるのです。
その言葉は「もの」であるお土産を、言葉を添えて渡すことで「こと」にもなるのです。「このもみじ饅頭は、〇〇なんだって」と、その土産の価値を高めるものとなるのです。
佐賀県の武雄で講演したときのことです。武雄図書館に行き、講演前のひとときを、軽食を兼ねたコーヒー休憩にしようと、図書館の中にあるスターバックスに行き、目に止まったサンドウィッチを頼みました。
「こちらでお食べになるのであれば、温めますが」と聞かれたので、お願いをしました。しばらくして、温められた商品を受け取るときのことです。スタッフが商品の載ったトレーを渡しながら、笑顔で「これおいしいですよ」と言葉を掛けてきました。
素晴らしい言葉に出逢えて、本当にわくわくしました。おかげでより以上にそのサンドウィッチをおいしくいただくことができたのです。
言葉のチカラとは、その商品の価値をも変えるのです。お客様の質問に応えられる「言葉」を、接客の武器を持てるようにしましょう。



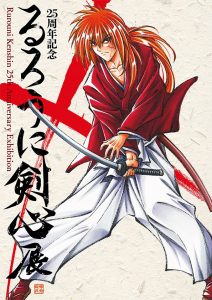
-web.jpg)
-web.jpg)










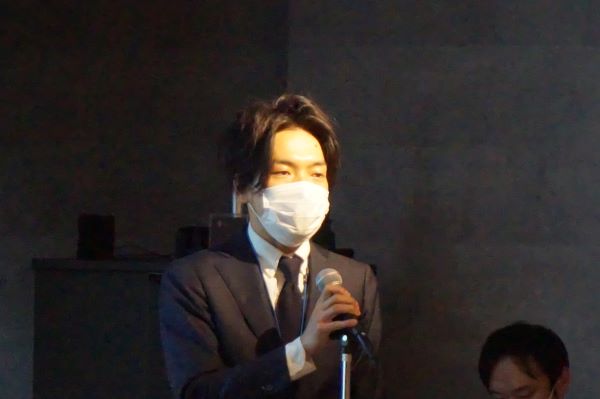
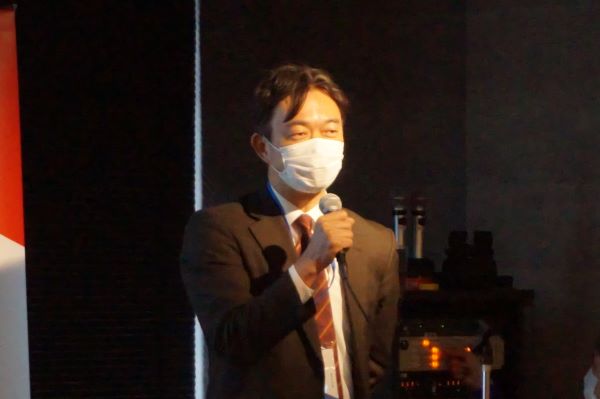

森ビルの洞田貫晉一郎氏、京阪レジャーサービスの馬淵勝久氏、横浜八景島の吉澤右耕氏、ラスイートの中川大輔氏、アソビューの野々松秀和氏.jpg)
を囲んでの写真撮影-web.jpg)
を囲んでの写真撮影-web.jpg)



.jpg)
.jpg)


 -1200x800.jpg)