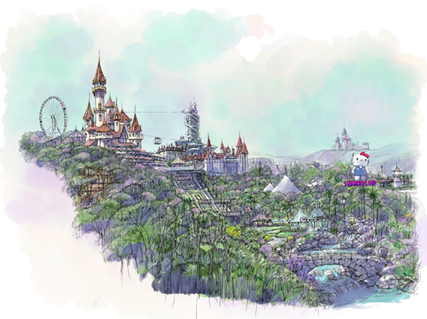2025年12月14日(日) 配信
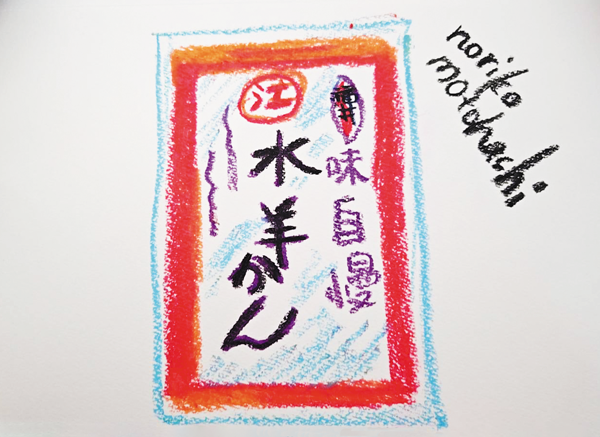
福井県では、木枯らしが吹く季節になると食べるのが「水ようかん」なのだ。「水ようかんって夏に食べる冷菓じゃないの?」と私のように都会に住む者は想う。
福井の水ようかんの起源は諸説あるが、その歴史は江戸時代まで遡る。奉公に出た年少者は「丁稚」と呼ばれ、働く代わりに商人や職人に衣食住の面倒を見てもらっていた。年末の帰省時に丁稚が奉公先から持ち帰った手土産が、水ようかんだったと記されている。
水ようかんは、練りようかんや蒸しようかんに比べて水分量が多いだけでなく、糖度が低いため、あまり日持ちがしない。江戸時代には冷蔵庫はなく、暖かい気候のもとでは水ようかんがすぐに腐敗してしまうため、寒い冬の菓子として好まれたともいわれている。
さて今回紹介する1937年開業の和菓子店「えがわ」のそれは福井のお土産の定番として愛され続けている。厳選されたきめの細かいこしあんを使っているので、滑らかでつるんとした食感を生み出している。さらに沖縄県産の黒糖を使用。上品な風味なので、いくつでも食べられる。ゆっくりゆっくり丁寧に混ぜ合わせ、途中寒天が分離しないようにこまめにかき混ぜるのもポイントだという。
出来上がった水ようかんを適温に冷まして専用の機械を使い、容器に流し込む。添加物を一切使用しておらず常に新鮮な水ようかんを提供してくれているというわけだ。えがわの水羊かんは11月から翌年3月までの製造限定販売なので、決して夏には買うことはできない。福井の「冬だけの味」を頑固に守り続けている。
えがわの水羊かんが密封容器になってから、お取り寄せが可能になり地方発送もできるようになった。そのことで全国に名が知れ渡りどこにいても黒砂糖特有のさらっとした味と香りが楽しめるようになった。今、アツアツの日本茶とともにヘラを使って食べている。思ったより薄味であっさりしていて後を引く。銀座にある福井県のアンテナショップでも買うことができる。福井好きの私には実にありがたい。
(トラベルキャスター)
津田 令子 氏
社団法人日本観光協会旅番組室長を経てフリーの旅行ジャーナリストに。全国約3000カ所を旅する経験から、旅の楽しさを伝えるトラベルキャスターとしてテレビ・ラジオなどに出演する。観光大使や市町村などのアドバイザー、カルチャースクールの講師も務める。NPO法人ふるさとオンリーワンのまち理事長。著書多数。

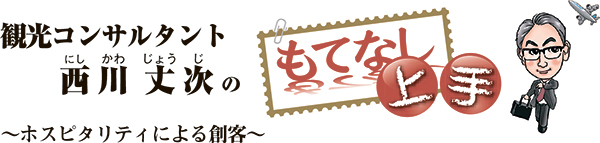

、JTBの森口浩紀取締役常務執行役員.png)



国土交通省関東地方整備局の山下副所長がバスタ新宿を説明した.jpg)