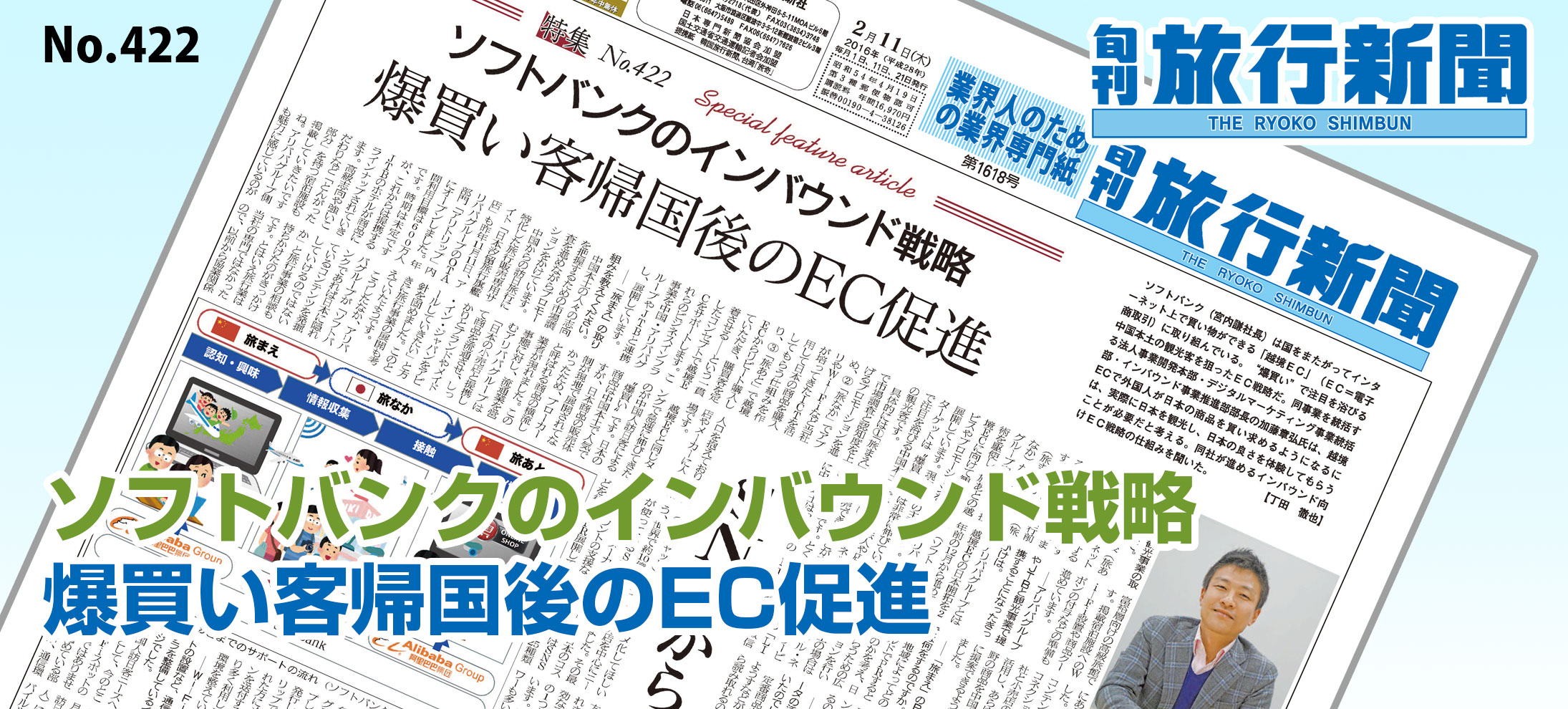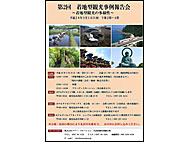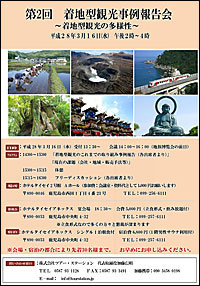ジャルパック(藤田克己社長)は2月2日、東京都内で2016年度上期の商品発表会見を開き、藤田社長は国内、海外ともに“JALパックならでは”の新企画を商品造成のポイントに据えたことなどを語った。上期の計画人数は国内旅行が前年同期比6%増の84万9千人、海外旅行が同3%減の10万1千人。
冒頭、藤田社長は「インバウンドとアウトバウンドが逆転したエポック的な年」と昨年を振り返り、インバウンドの好調で国内はホテルの仕入れに苦戦したことや海外の不調などを語った。国内は東京ディズニーリゾート(TDR)やユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)などを中心に観光需要は堅調に推移したが、「国内の好調で海外の不調をカバーできるほどではなかった」と述べた。15年度下期の国内旅行は同9%増の81万人、海外旅行は同7%減の10万1千人の見込み。
16年の見通しについては、国内は東京ディズニーシー(TDS)の15周年などが牽引し、引き続き好調とみる。北海道新幹線の開業は、「(飛行機と)競合するとは思っていない。相乗効果はある」と前向きに捉えた。一方、仕入環境については、インバウンドは予約が早く「昨年以上にひっ迫する。日本国内の予約の立ち上げを早くしないと埋まってしまう」と危機感を示した。対応として沖縄と北海道商品は「早決」の割引額を増額し、早期予約を強化していく。
また、沖縄・奄美大島商品に「復路欠航お見舞金サービス」を導入。台風などの天候不良で復路の航空便が欠航になった場合に1人1万円ずつ見舞金を払い、ストレスを緩和する。このほか、JALパックならではの企画として、TDS15周年の新イベントを一般公開より前に楽しめるツアーなどを設定した。方面別の計画人数は北海道が2%増の13万6千人、関東が9%増の27万2千人など。沖縄は仕入れが厳しいため増減なしの15万5千人。
海外旅行は、円安や人件費、地上費の高騰、インバウンド需要で日本発航空座席の確保困難、政情不安などマイナス要素が大きく「15年の傾向が続き環境は厳しい」とした。このなかで、大きなポイントとして「ハワイ強化」「ヨーロッパの復活」「アジアの開拓・増強」を挙げ、海外旅行の復活を念頭に取り組んでいく。しかし、ハワイはJAL機材の使用変更で計画人数は14%減の3万9千人と大幅減を見込む。このほか、ヨーロッパは4%増の1万3千人、アジアは10%増の1万5千人など。