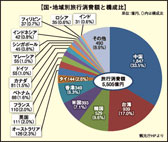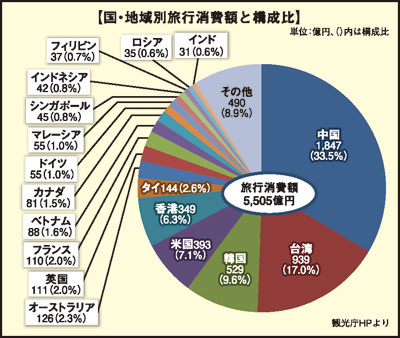2027年にリニア中央新幹線東京―名古屋間が約40分、45年には東京―大阪間が約67分で結ばれる計画という。首都圏と中部圏、関西圏が約1時間でつながり、世界に類を見ない巨大な経済圏の誕生を目指している。国際間で激化する都市競争を見据えた場合に、リニアは大きな武器になるだろう。しかし、交通網が整備され便利になる度に「都市間の激しい生き残りトーナメントの様相」のようだと思う。たとえ1回戦で隣町に勝っても、2回戦、3回戦と勝ち組同士が結びつく生き残り戦のどこかの段階で敗退していく。敗れたときどうするかがあまり考えられていない。
日本各地に高速道路が整備されるなかで、各県庁所在地クラスの都市間の移動は便利になった。一方で、古くからの街道が寂れ、小規模で知名度の高くない市町村は素通りされるようになった。勝ち組になったはずの地方中核都市もその後、札幌、仙台、名古屋、新潟、金沢、京都、大阪、神戸、広島、福岡など各ブロックの大都市に若者が吸い取られ、人口減少や地域経済の停滞という流れができている。今後、北陸新幹線金沢延伸や北海道新幹線の開業によって、観光業界では新たな人の流れが生まれることが期待されているが、より大規模な勝ち組の都市に一方的に吸収されていくストロー現象が起こらないことを願うばかりだ。
¶
来るべきリニア時代には、首都圏、中部圏、関西圏の3つの大都市エリアに人や文化、資本が集中することが予想されるし、最終的には東京一極集中化がさらに加速しそうである。唯一、日本の勝ち組である東京ですら、世界的な都市間競争や、ネットワークの中心から外れる危機感を抱いているのも皮肉である。もちろん、国際的な大都市同士の競争には洗練度を上げ、勝たなければならない。しかし、高度な交通網から外れ、早々と敗退してしまったエリアはどのようにまちを維持し、発展していけばいいのか。勝ち残ることばかりを考えてきたので、一度交通ネットワークから外れてしまうと、一瞬思考停止状態になる。しかし、これら地域が今後取り組むべき最重要課題は、二次交通の整備だ。
¶
旅行には交通費の占める割合が大きい。LCCの参入により、空の旅は価格帯の選択肢が広がった。陸の旅では高速バスがその役割を果たしている。では、レンタカーを含め、個人のクルマ旅はどうだろうか。交通費が節約できれば、旅先で美味しいものを食べ、土産物を買う余裕も生まれ、地方にお金が落ちる。旅行回数も宿泊数も思うように伸びていないのは、交通費が高いことも大きな原因の一つと考えて間違いない。なかでも高速道路がつながることは地域の人たちにとって利便性が高まるが、果たして大都市圏から地方へ人の移動が行われているだろうか。さまざまな高速道路を走ってきたが、「もしかしたらこの世からすべての人や車が消えてしまったのかもしれない」と不安になるほど通行量が少ない高速道路もある。道路は走るために作られる。都市部から訪れないのなら、あまり意味がない。むしろ地方から都市部への移動に使われ、過疎化が進む結果になるのなら、地域活性化とは逆行する。
地方創生は双方向の人的交流が不可欠である。衆議院が解散する。地方活性化へ高速道路の低料金化は論点にはならないだろうか。
(編集長・増田 剛)