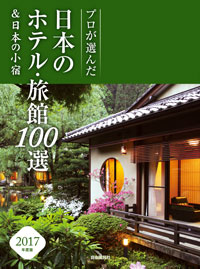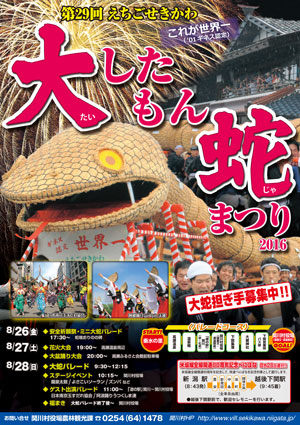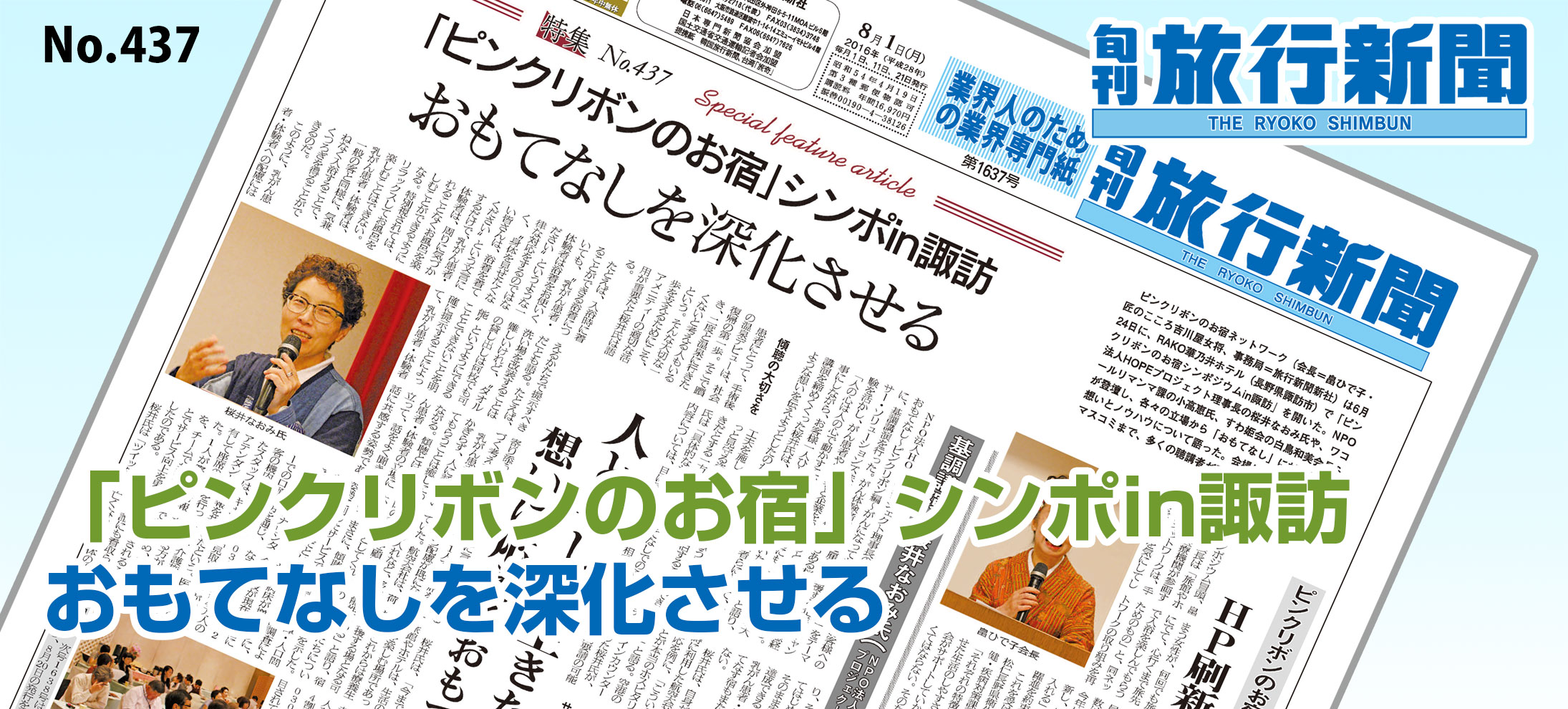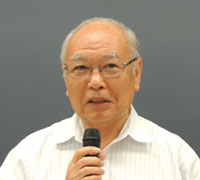「祈る皇女斎王のみやこ 斎宮」パンフレット
「祈る皇女斎王のみやこ 斎宮」パンフレット
「日本遺産」という言葉を聞いて、それがなにかを答えられる人はどれだけいるだろうか。この文化庁の新事業は文化財を「保存」から「活用」へと方針転換し、地域主体で活用と発信を行い、地域の活性化をはかるもので、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに100カ所が認定される予定。“認定後がスタート”ともいわれる日本遺産について、7月1日岐阜県岐阜市で行われた「日本遺産サミットin岐阜」の内容を中心に、その取り組みを紹介していく。
【後藤 文昭】
◇
「保存」から「活用」へ、物語で地域を活性化
■日本遺産の目的と2種のストーリー
今まで文化財は、国指定史跡や県指定無形文化財のように一つひとつで保存・活用されていた。その結果、文化財同士のつながりが無く、まちの振興や観光では非常に扱いにくい状態になっていた。これらの文化財をストーリーで結び付け、面で活用できるようにしたものが「日本遺産」だ。ストーリーを語るうえで不可欠な“魅力ある有形・無形の文化財群”を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信することにより、地域の活性化をはかる目的がある。認定後には、文化庁も「日本遺産魅力発信推進事業」として、人材育成などのソフト事業への経費補助を行うほか、今年度から日本遺産プロデューサーの派遣を開始。
 岐阜市「川原町」のまちなみ
岐阜市「川原町」のまちなみ
日本遺産には単独の市町村内で完結する「地域型」と、複数の市町村にまたがって展開する「シリアル型」の2つのストーリータイプがある。「地域型」の場合は、その地方自治体の歴史文化基本構想、文化でまちづくりをする基本方針を用意することが必要になる。現在日本遺産には37のストーリーが認定されており、内訳は「地域型」が12、「シリアル型」が25となっている。シリアル型には隣接する愛媛県と高知県、徳島県、香川県内57市町村が一体となってストーリーを紡ぐ「『四国遍路』~回遊型巡礼路と独自の巡礼文化~」や、宮城県仙台市と塩竈市、多賀城市、松島町など県内のいくつかの市町村が一体となってストーリーを紡ぐ「政宗が育んだ“伊達”な文化」。さらに茨城県水戸市と栃木県足利市、岡山県備前市、大分県日田市のように隣接していない地域が紡ぐ「近世日本の教育遺産群―学ぶ心・礼節の本源―」とさまざまな結びつき、展開がある。このシリアル型は「今後も増えていくのではないか」との声が多く、また隣接していない市町村同士が共通する素材で結び付いて紡ぐストーリーへの関心も高い。
しかし、隣接していない市町村が共同でストーリー認定を受けた場合、「文化や風習などが違うので、他の地域の考え方も聞けることが新鮮」というメリットがある一方、離れているから日程調整などが難しく、共同PRイベントなどが行いにくいといったデメリットもある。シリアル型は1度に完結できない分、次の土地への来訪が促され、人の流れが広域に広がることも予想できる。実際認定されたストーリーのなかでは、隣接する県との連携や同じ県内にある世界遺産との連携を模索する動きもあり、効果的な誘客手段の確立も大きな課題として挙がっていた。
 認定書の交付
認定書の交付
(左)馳文科大臣
■PR展開は色々な視点で
「日本遺産サミットin岐阜」では、認定37団体すべてがブースを出していた。そのなかでも鳥取県三朝町の「六根清浄と六感治癒の地~日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉~」のように、タイトルに人を惹きつけるワードが加わっているものや、ストーリーに登場する額田王に「仕事も恋もモテ系女史」というフレーズを加えてわかりやすく紹介している奈良県明日香村と橿原市、高取町の「日本国創成のとき―飛鳥を翔た女性たち―」などのブースは来場者の関心が高かった。三重県明和町の「祈る皇女斎王のみやこ 斎宮」のパンフレットは、個々の写真が大きく、情報が最低限であるため、内容情景がイメージしやすい。また広島県尾道市の「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」のパンフレットも、尾道市の日常風景の写真が多く、まち全体が日本遺産だと一目で実感できるようになっている。ほかにも女性向けの旅の提案をしているものなどがあり、配布されている情報誌に関しては、「読みやすさ」が1つのカギになるのではないかと感じた。
今回の取材では見ることができなかったが、今美術館のなかには子供向けの解説シートや、プレゼント付きクイズラリーなどを用意し、楽しみながら美術に触れる機会を提供しているところも多い。「ストーリーがあると、知識が無い人にも興味を持ってもらえる」という声の通り、今後はいろいろな層に分けたPRを展開していくことも重要になると感じた。
日本遺産に認定されたストーリーを構成する文化財は建築物だけではなく、山や川、料理や器、祭など多岐に渡る。
例えば島根県津和野町の「津和野今昔~百景図を歩く~」は、栗本里治(号・格齋)の描いた百枚の絵とその詳細な解説をまとめた「津和野百景図」に描かれている町の風景や伝統、風習などの多くが今も守られている津和野が舞台。自然と歴史文化、四季、食文化の4つで津和野を旅できるようになっていて、暮らす人も含めて日本遺産であると、紹介している。このように五感すべてで楽しめるのも1つの魅力ではないだろうか。
 細江茂光岐阜市長
細江茂光岐阜市長
■見えてきた次なる課題
日本遺産の現状で最大の課題は、認知度の低さである。昨年認定された団体は、ボランティアガイドの育成や紹介施設の開館、多言語アプリの開発などの環境整備とフォーラムの開催やパンフレット作成などの周知活動を行っている。また、住民への周知拡大のために、日本遺産認定記念イベントを開催している場所もある。
岐阜市では「市内の外国人観光客の宿泊者数が前年度比約8%増えた」という報告があり、ほかにも「観光消費額が増えた」などの良い報告もあったが、取材した多くのブースでは、地域住民への浸透、観光資源としての浸透の難しさなどを理由に、「認知度の低さを改善するための活動が難しい」という声も聞かれた。また、数が増えることで目立たなくなることを心配する声や、「日本遺産全体での情報発信の機会を増やしてほしい」などの要望も聞かれた。ただ、見方を変えれば「世界遺産だって、今は登録されたら話題になるが、はじめのころは話題にもならなかった」という声があるように、始まって2年目であることを考えると、色々な挑戦ができる段階だともいえる。
座談会の中で多くの団体が観光庁との連携を期待するなか、観光庁の蝦名邦晴次長は「理解してもらうことが地域の魅力を高めることにつながる。相手側にとってどう受け取ってもらえるかを考え、外国人、新しい日本の観光客の発掘をしていかなければならない」と発言した。文化庁の宮田亮平長官はPRに関してしたたかさが大切であるとの考えを示し、「掘り起こしたときに出てきたものを大切にし、文化財を活用していくべきだ」と語った。また、細江茂光岐阜市長は観光地整備に関して「外国人と日本人の感じる魅力は、生活の背景、歴史、文化が違うので必ずしも一致するとは限らない。日本人が自分でみて良いと思ったものが必ず海外の人にも良いはずだと思い込まないことが大切」と話し、「本当の日本の良さはありのままの良さと認識し、外国人受けするために手を加える、または観光客に迎合するのではなく、ありのままの良さで勝負する感覚も個人が持たなくてならない」と強調した。「おもてなしレベルの向上のために日本遺産申請をした」という言葉が取材の中で一番心に残ったのは、そこに通ずるものだからかもしれない。そこに住む人が自分のまちの良さに気が付き、自信と誇りを持ち、磨き上げる。多くの人がそう話すように、まち全体での取り組みが大きなカギとなる日本遺産。次回サミットは、京都府で開催される。その場ではサミットの座談会の最後にもあったように、課題や成果の発表がさらに挙がることを期待したい。