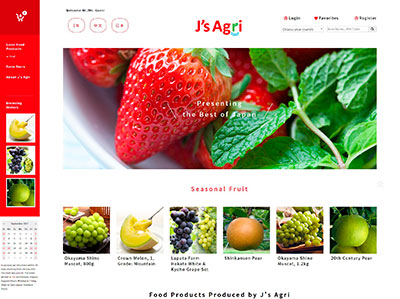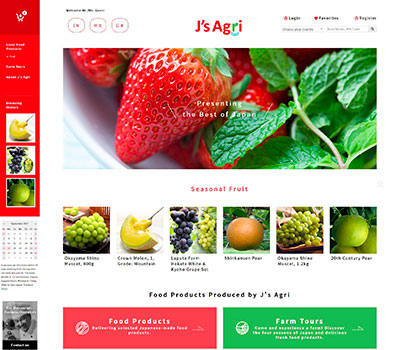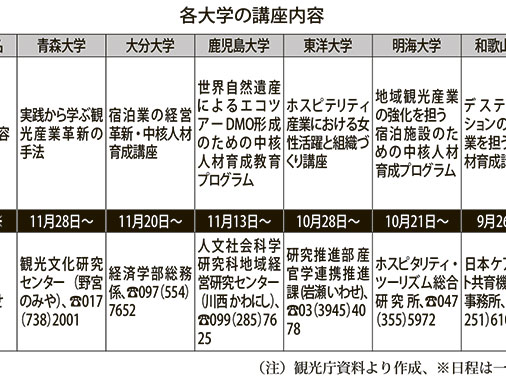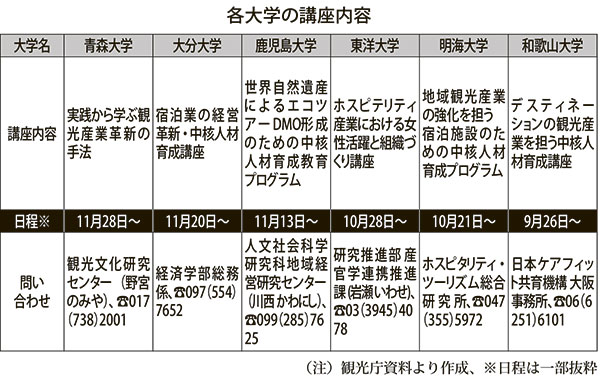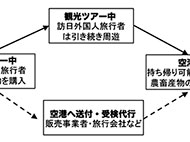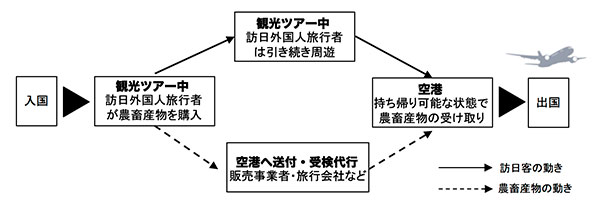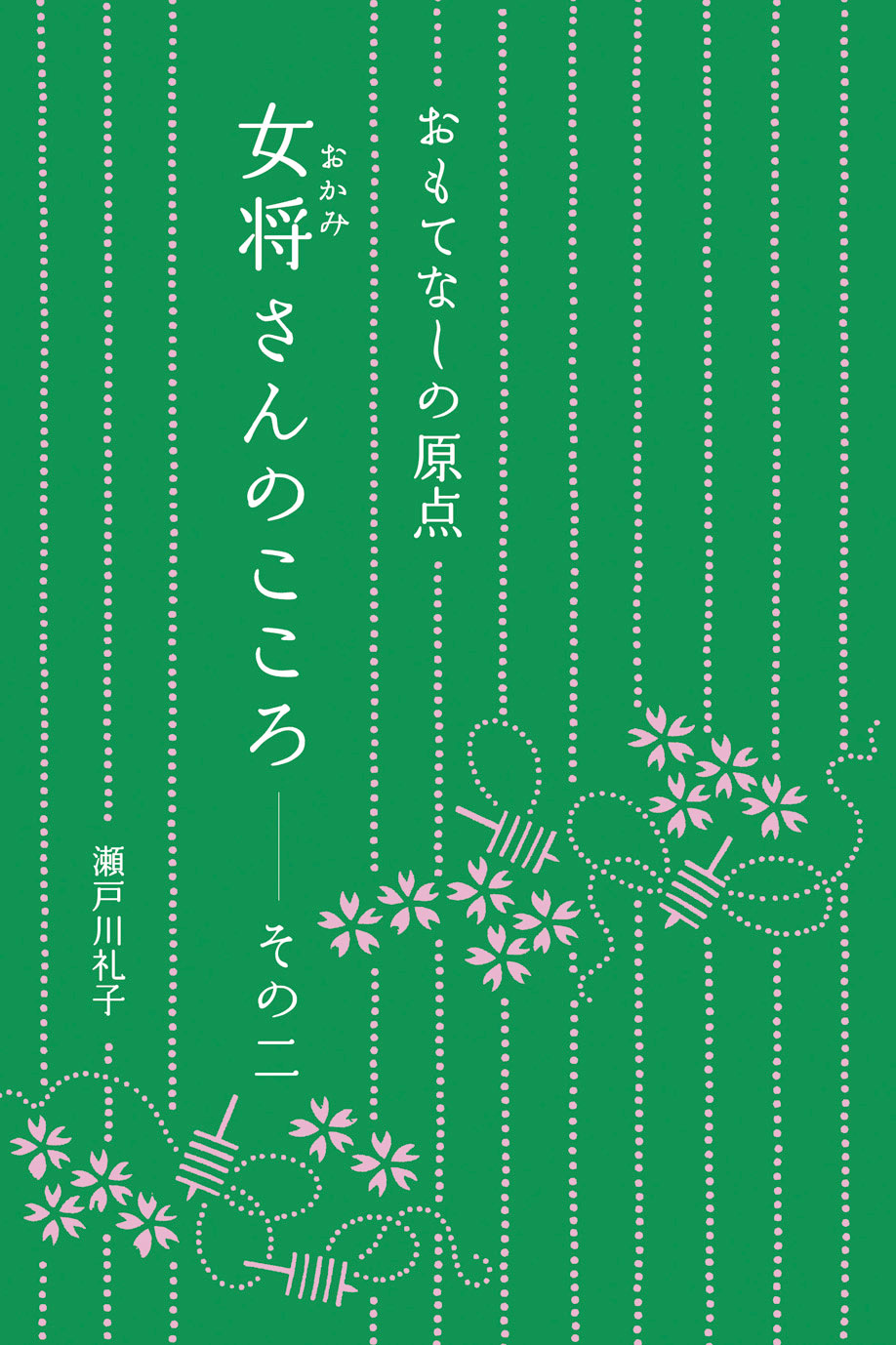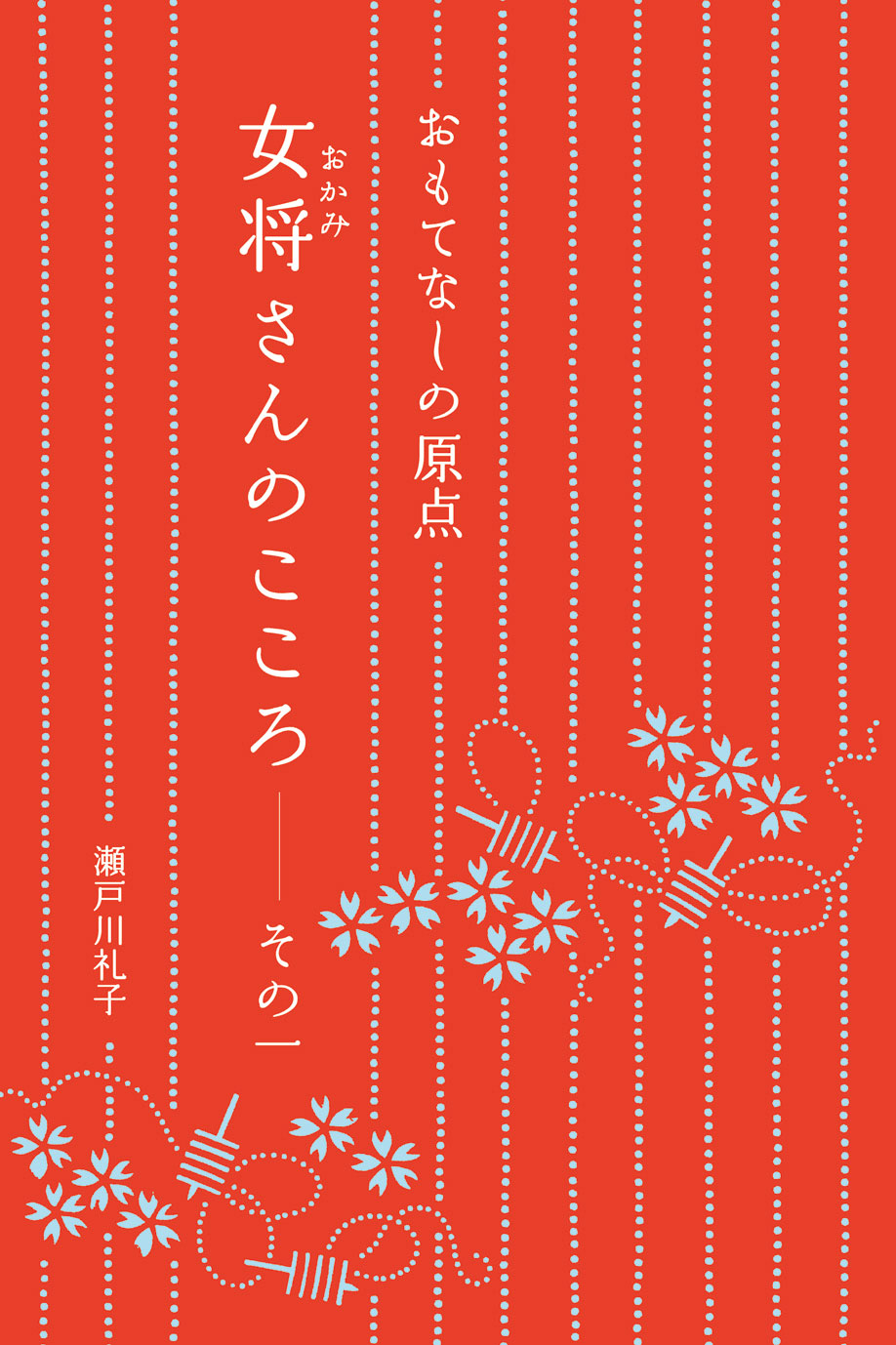国土交通省はこのほど、昨年4月に開業したバスタ新宿の「開業後1年の成果と課題」を発表した。当初計画で1日平均約3万人、1日最大約4万人としていたが、開業1年で1日平均約2万8千人、最大4万1140人で「実績は概ね順調」(国交省)と振り返った。開業から累計で利用者数が1千万人を突破したものの、新宿駅西口周辺の路上駐車は減らず、課題も残った。
便数は1日平均約1470便で、1日最大は1720便。方面別の1位は、利用者約98万人で河口湖、2位は約88万人で大阪、3位は約78万人の箱根となった。
これまで改善の声が多くあった、待合環境の改善も実施した。今年4月にコンビニエンスストアをオープンし、女子トイレも8室から21室に増設。ベンチも約200席増やし344席となった。
「問題が少しずつ解消されて良くなっている」(30代男性)との声も上がっていて、開業直後から待合施設の満足度「やや満足」と「満足」の合計は26%向上し、83%となった。
バスタ新宿前の国道20号の混雑状況は、開業当時と比べ回復傾向がみられる。開業後半年間のデータで混雑状況が悪化したため、昨年12月から高速バスの経路変更など対策を打ってきた。国交省は「引き続き、さらなる対策を講じる」と強調した。
国道20号は、事故状況の改善もみられた。高速バス停やタクシー乗降場の移転で、開業前から事故リスクが軽減。昨年と今年の4―6月期の急ブレーキ件数を比較すると、平日で64%減、休日で47%減となり、事故件数も平休合計で同13%減だった。
一方で課題も残った。新宿駅西口周辺で高速バスの路上駐車を確認したため、昨年11月に関係者に再発防止を要請。
要請後の12月が、1日13・0台、今年1月が同9・2台、2月が5・8台と下がったものの、3月が7・4台で、4月が6・6台、5月は10・8台、7月が13・7台と、要請後の12月を超えるまで増加した。「今後は悪質なバス事業者に対する警告や、バスタ新宿への乗入規制などの措置を強化する」(同庁)とコメントした。