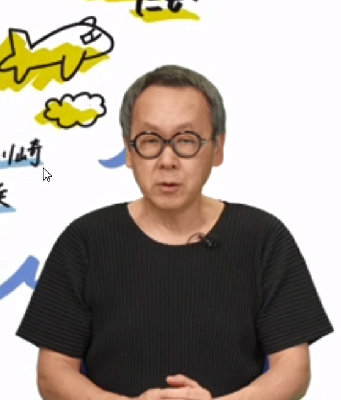2022年10月15日(土) 配信
クライアント企業から、地元のプロジェクトに料理人を紹介してほしいと依頼され、山形のアル・ケッチァーノのオーナー奥田政行シェフに連絡をしました。とても忙しいシェフなのですが、連絡するとすぐに快諾いただき、現地にお迎えすることができました。
さらに「皆さんがお集まりになる機会に、少しお話もしましょう」と、講演もしていただきました。その講演のあとにシェフから「この機会をつくってもらった西川さんへ、お礼を述べることができなかったのが失敗でした。ごめんなさい」との一言が、とてもうれしく記憶に残るものとなりました。
シェフに依頼するために山形まで伺い、何度も日程調整のための連絡をして、ようやく決まったプロジェクトでした。その言葉で、すべてが報われた想いでした。
そうした細やかな気遣いができるシェフだからこそ、常にお客様方に喜ばれる料理を提供することができるのだと思います。
シェフの料理を食べ始めたころ、あるパーティーに参加されることを知り、申し込みました。テレビや雑誌などでも紹介されている有名シェフが何人も参加され、1皿ずつ腕を振るうというとても魅力的なパーティーでした。
ただ料理が作られるだけでなく、その渾身のお皿が提供される度に、その料理を作ったシェフが、料理について解説をしてくれるのも楽しみの1つでした。食事だけでも特別感があるのに、それを作ったシェフが直接話をしてくれることは、料理の味をさらに高め楽しいものでした。
いくつかの料理を食べたあとに、奥田シェフの順番が来ました。他のシェフは自作の料理を得意げに話すなかで、奥田シェフだけは、「前後の料理がこうだから、それをつなぐためにこういった料理を作りました」と、そのパーティーの料理全体を見た1皿を作られていたのです。
提供されたすべての料理は、間違いなく美味しいものでしたが、コース料理となるとそれぞれが主張し合っているようにも感じていたのです。シェフのそのコメントを聞いたときの感動は、忘れることができません。それがきっかけで、その後も奥田シェフのレストランに機会がある度に伺うようになったのです。
講演のあとに私に掛けていただいた言葉からは、同時に感謝の想いを持つことの大切さを改めて感じた瞬間でもありました。
気付かないなかで、たくさんの方々の力を借りて私たちは仕事をしています。今の結果は、そのすべての人たちの力があったからです。
感謝する想いが、シェフのように細やかな気付きを生み、お客様に喜ばれる仕事につながるのです。
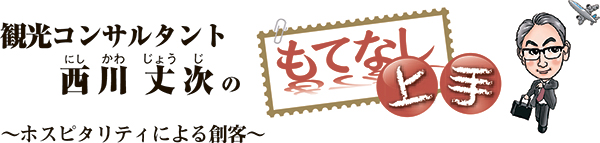
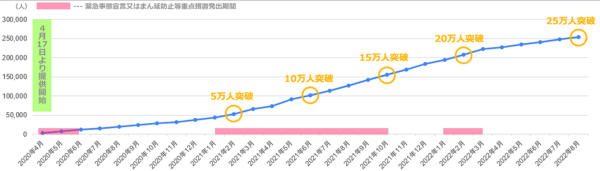

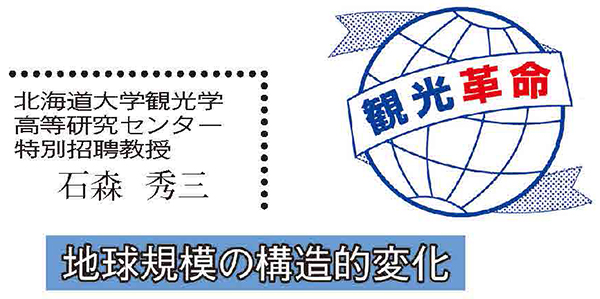

井口智裕志、平石理奈氏、北村剛史氏 WEB.png)


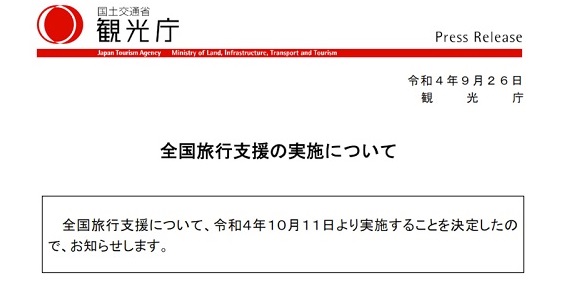
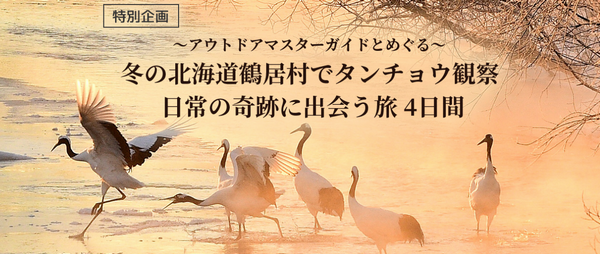



.jpg)
.jpg)