2024年3月4日(月) 配信

台湾貿易センター(TAITRA、黄志芳董事長)は3月5(火)~8日(金)まで開かれるアジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN2024」での台湾パビリオンの出店に伴い、最新の台湾フードの魅力を紹介する記者会見を3月4日(月)に開いた。音楽グループ「ブラックビスケッツ」のボーカルとして有名な台湾女優のビビアン・スーさんをゲストに招き、黄董事長とのミニトークショーや台湾グルメクイズで、台湾の食をPRした。
黄董事長は、「台湾から178社が出展し、189のブースを構え、13の自治体が参加する。台湾パビリオンは今年のFOODEXの中では2番目の大きさであり、過去最大規模で出展する」と話した。また、「台湾の食品業界は、日本市場をとても重要視しており、日本向けに開発したシルバー向け・オーガニック・SDGs・インスタント食品などのジャンルを新たに展示している。より安心安全な食を、日台両国で共に創造していきたい」と力を込めた。
台湾の各県市長が登壇し、屏東県の周春美市長はウナギの蒲焼き、嘉義県の翁張亮市長はカラスミとドライフルーツ、嘉義市の黄民輝市長はロイヤル蜂蜜ギフトセットなど、地元食材で作られたおすすめの特産物をPRした。
美貌の秘訣を聞かれたビビアンさんは、トレーニングやランニングなどの運動のほか、「鶏エキスという台湾の健康食品を愛用している」と紹介した。また、「日本で活動していたころは、パイコーハンやルーローハンが恋しかった。今回の展示会ではそういった台湾の食が同じ場所で味わえる」と笑顔を見せた。


、23日(土)の計2回.jpg)



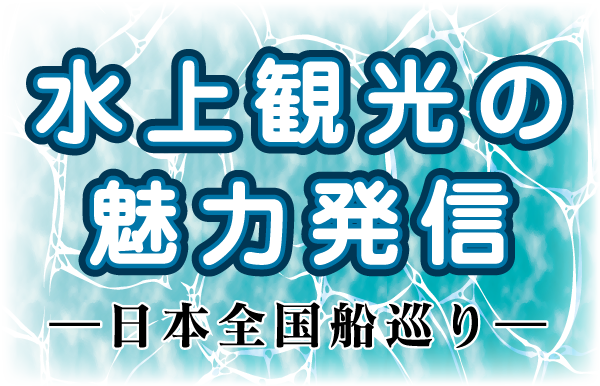



正午まで(写真はイメージ).jpg)



