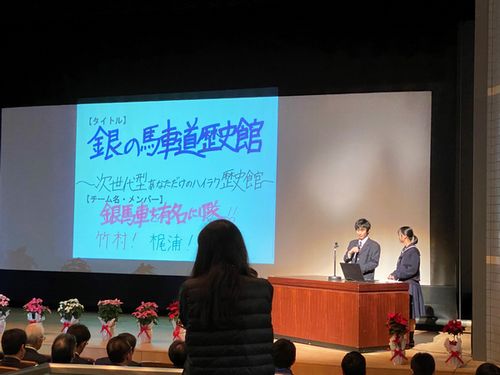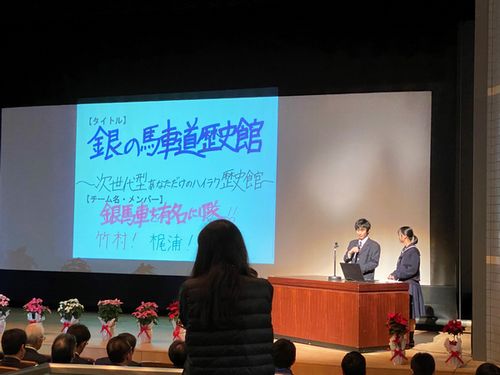2020年1月24日(金)配信
 スノーラフティング
スノーラフティング
北海道のほぼ中央に位置し、日本最大の山岳公園「大雪山国立公園」を擁する上川町で1月23日(木)、地形を生かした体験型ツアーがスタートした。
上川町が昨年から取り組んでいるアドベンチャートラベルを推進するため、上川町DMC「大雪山ツアーズ」が実施する。いずれも冬をダイナミックに楽しむコースで、日帰りのツアーパッケージだ。昨年開催し好評を博した「Aコース:雪遊びを満喫しよう!~大雪高原旭ヶ丘 スノーアクティビティ体験プラン~」に加え、今年新メニューとなった「Bコース:凍った滝を見に行こう!~スノーシューで行く氷瀑ウォッチング~」「Cコース:自然の彫刻を見に行こう!~スノーシューで行く 層雲峡の大氷柱群と大函・柱状節理~」と、全3種のラインナップ。いずれのコースも、大雪山系に囲まれた上川町の冬の自然を、普段なかなか体験できない形でアクティブに満喫できるプランとなっている。
ツアー開始に合わせて層雲峡総合観光コミュニティセンター「黒岳の湯」施設内に層雲峡アクティビティインフォメーションデスクを期間限定で開設する。上川町のアドベンチャートラベルの情報拠点として2022年に開設予定の「アドベンチャートラベルインフォメーションセンター(仮)」の前身として機能する。
□大雪山アドベンチャーズ
Aコース:雪遊びを満喫しよう!~大雪高原旭ヶ丘 スノーアクティビティ体験プラン~
 スノーキャットクルーズ
スノーキャットクルーズ
大雪高原旭ヶ丘の広大な敷地でスノーラフティングやチューブ滑りを時間内滑り放題で楽しめる。北海道でも珍しいスノーキャットクルーズ(圧雪車乗車体験)も可能。大雪山系の山々に囲まれた広大な敷地で、北海道の広さを体感できる。
催行日 :1月11日(土)-3月30日(月) ※火曜日を除く毎日
所要時間 :約3.5時間
申込締切日:3日前
募集人員 :8人(最少催行人員2人)※2歳以下は参加不可
料金 :おとな・こども 9千円 ※未就学児は無料(昼食なし)
料金に含まれるもの:タクシー代・体験費用(レンタル費用含む)・昼食代
会場 :大雪高原旭ヶ丘
Bコース:凍った滝を見に行こう!~スノーシューで行く氷瀑ウォッチング~
層雲峡の自然氷瀑は、国道沿いだけでも約20以上あり、落差10-120メートルの氷瀑が数多く点在している。北海道の中でも内陸性の気候のため、冬季は冷え込むことから、国道沿いにある数多くの滝は12月上旬にはほぼ完全結氷する。このツアーでは、落差約45メートルの完全結氷した『七賢峰の滝』を見ることができる。
催行日 :1月23日(木)-3月15日(日) ※火曜日を除く毎日
所要時間 :約2時間
申込締切日:3日前
募集人員 :8人(最少催行人員2人)※小学生以下は参加出不可
料金 :おとな(中学生以上) 6千円
料金に含まれるもの:体験費用(レンタル費用含む)・ガイド費用
会場 :層雲峡 周辺
Cコース:自然の彫刻を見に行こう!~スノーシューで行く層雲峡の大氷柱群と大函・柱状節理~
 層雲峡の氷柱群
層雲峡の氷柱群
このツアーでは、高さ約10メートルの氷柱が横幅約300メートルにわたって見ることができる。これらの氷柱は岩肌からしみ出した雨水や雪解け水などが、崖から垂れ落ちる時点で寒気に晒され凍り付き、上から下へ徐々に成長したもの。併せて、3万年の歴史を経て形成された柱状節理の断崖絶壁を間近に見ることができる。
催行日 :1月23日(木)-3月15日(日) ※月・火を除く毎日
所要時間 :約2時間
申込締切日:3日前
募集人員 :8人(最少催行人員2人)※未就学児は参加不可
料金 :おとな・こども(小学生) 6千円
料金に含まれるもの:体験費用(レンタル費用含む)・ガイド費用
会場 :大函周辺













-web.jpg)
-web.jpg)