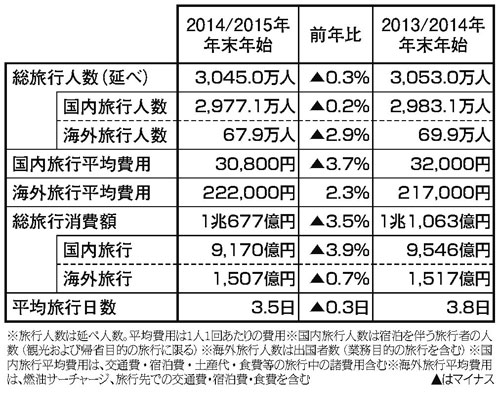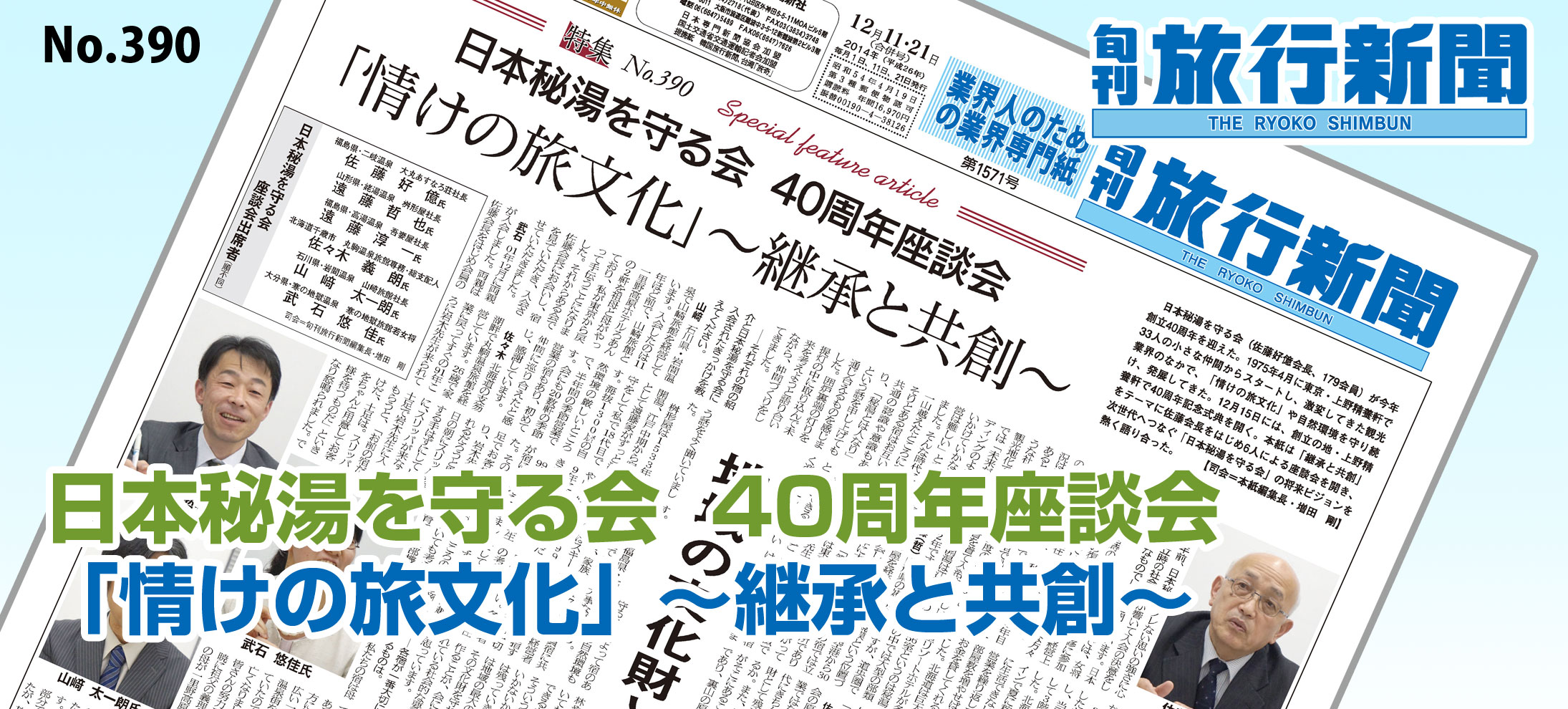長野県と岐阜県にまたがる御嶽山の噴火で、観光業など地域経済に影響を受けている長野県では、関係団体が「木曽復興を応援する運動」を展開している。
呼びかけ人は、県や長野県市長会、長野県町村会など。各団体は、木曽地域での宿泊や木曽の物産品の購入をPRしている。
木曽エリアは現在、スキーシーズンを迎え、開田高原マイアスキー場(木曽町)などは運営中。御嶽山の噴火により、火口から4キロが入山規制となっており、「おんたけ2240」(王滝村)は営業を見合わせている。
長野県大阪事務所では、南木曽町に伝わる防寒着「なぎそねこ」を販売中。手作りならではの着心地が特徴という。
同事務所の松澤繁明所長は、「木曽エリアに多くのお客様に来ていただき、支援の輪を広げていきたい」と話している。
九州観光推進機構と九州運輸局はこのほど、韓国・済州島発のトレッキング「九州オルレ」の新コースを3つ認定。2月までに随時オープンする。九州オルレは今回の認定で、全15コースとなる。
第4次コースとなる今回の3コースは、八女コース(福岡県八女市)、別府コース(大分県別府市)、天草・苓北コース(熊本県天草郡)。
すでにオープンしている八女コースは、山の井公園から始まる全9・2キロ。所要時間は3、4時間。童男山古墳、市指定記念物の犬尾城址などが見どころとなる。別府コースは、志高レストハウスから出発する全11キロで、所要時間は4、5時間。由布岳や鶴見岳を望む山上湖「志高湖」などを通る。2月28日にオープンする天草・苓北コースは、富岡港を起点とした全11キロ。所要時間は4、5時間。富岡城や白岩崎などを巡る。