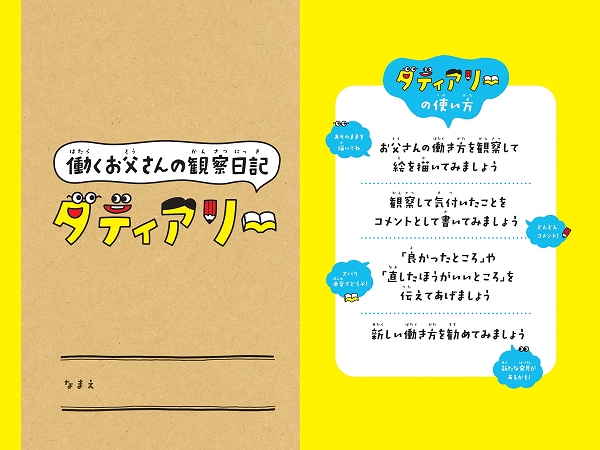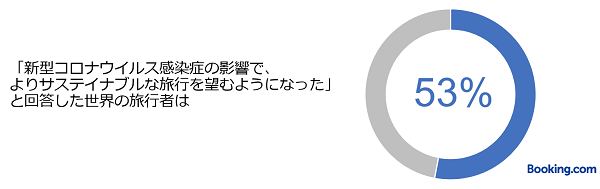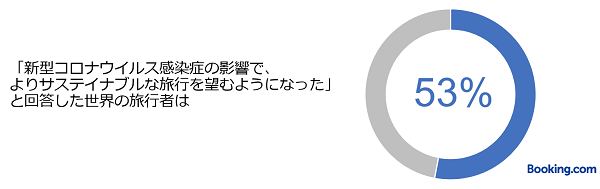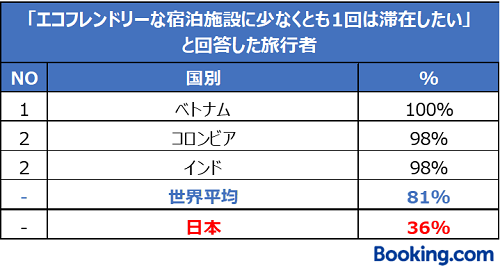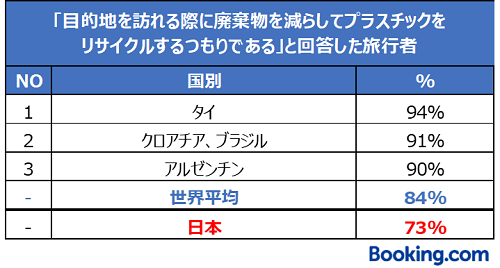2021年4月23日(金) 配信
 イメージ
イメージ
JTB(山北栄二郎社長)は4月22日(木)、「2021年ゴールデンウィーク(4月25日~5月5日)の旅行を取り巻く環境と1泊以上の旅行に出かける人の意識調査」の結果を発表した。GWに旅行に「行きたい」と考えている人は10.3%と、例年の半分以下に留まった。また、旅行者を感染防止を意識し、旅行先は域内志向の割合が高かった。
調査は、今年のGWに実施する1泊以上の旅行について、全国の15~79歳までの男女1535人を対象にインターネットアンケートを行った。調査期間は4月9~14日。
GW期間中の旅行について「行く」「たぶん行く」と回答した人の合計は10.3%で、コロナ禍前の調査では例年約25%で推移していたのと比べ、半分以下となった。
性年代別では、男性29歳以下が19.1%、女性29歳以下が16.5%と若年層ほど旅行意欲が高かったのに対し、男性60歳以上は6.9%、女性60歳以上は3.7%と低調だった。
旅行に行く目的や理由は「リラックスする、のんびりする(40.6%)」がトップで、次いで「家族と楽しく過ごす(38.8%)」「自然や風景を楽しむ(34.5%)」となった。
旅行の出発日で最も多かったのは、5連休初日の「5月1日(25.8%)」だった。次いで「4月29日(13.7%)」「5月2日(12.6%)」と続いた。
旅行日数は「1泊(39.2%)」が最多で、続いて「2泊(28.6%)」「3泊(16.3%)」となり、3泊までの旅行が全体の8割を占め、短期旅行の傾向がうかがえる。
旅行先は「関東(20.5%)」を選んだ人が最も多く、次いで「近畿(13.7%」「東海(11.1%)」の順。居住地別に旅行先をみると、全国的に旅行先と居住地が同じ地方で、域内の旅行の割合が高かった。
1人当たりの旅行費用は「1~2万円未満(23.8%)」がトップで、「1万円未満(21.3%)」「2~3万円未満(20.1%)」となり、3万円未満が全体の6割を占めた。
利用交通機関は「乗用車・レンタカー(65.0%)」「JR在来線・私鉄(19.6%)「JR新幹線(17.7%)」の順だった。
今後、新規感染者の増加や国・自治体からの自粛要請が厳しくなった場合の対応については「今より感染者数が増えた時点で旅行は中止する(8.1%)」「状況・条件によっては旅行を中止する(43.5%)」を合わせると51.6%にのぼった。一方で「状況に関係なく当初の予定通り旅行する」は31.8%だった。
同社の宿泊・国内企画商品の予約状況によると、緊急事態宣言中だった昨年よりは増加しているものの、19年比では75%減と大幅に減少。コロナ禍前のGWは沖縄や東京ディズニーリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどが人気だったが、今年は居住地域内および近隣エリアへの旅行が中心となっている。
宿泊予約状況では、海外旅行の代替需要による高価格帯の施設、客室や個室で食事ができる、客室に露天風呂があるなど、ほかの宿泊客と接する機会が少ない施設の人気が高く、新型コロナ感染防止を強く意識していることがうかがえる。
星永重全旅連青年部部長、猪俣敏斗学観連代表-WEB.png)
星永重全旅連青年部部長、猪俣敏斗学観連代表-WEB.png)












.jpg)