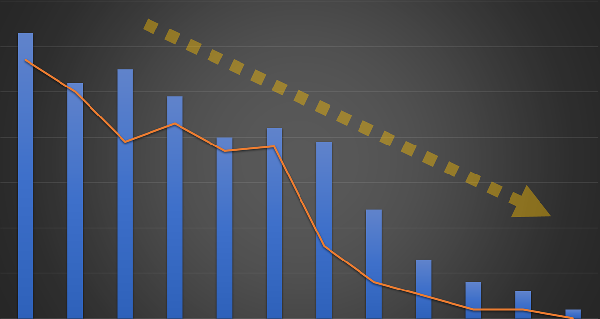2024年3月1日(金) 配信
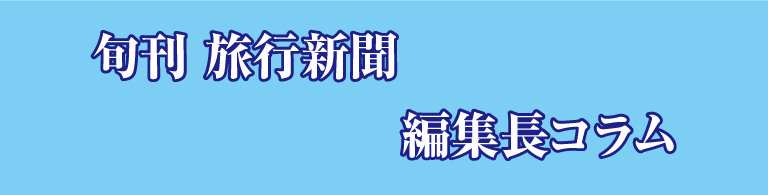
本紙1・3面で「日本秘湯を守る会」創立50周年座談会を掲載している。10年前の創立40周年のときも同様の座談会を開いたことを鮮明に記憶している。
昨年末、静岡県・熱海温泉で開催された日本秘湯を守る会の定時社員総会で、佐藤和志さん(秋田県・乳頭温泉郷鶴の湯)から声を掛けられた。
「古い資料を探していたら、旅行新聞さんの記事が出てきてね。とても参考になりました」
その記事がいつの時代なのかはわからなかったが、笑顔で語り掛けていただいた佐藤さんのお話に、私はとてもうれしく、そしてありがたく感じた。
50年という、半世紀にも及ぶ日本秘湯を守る会の長い歴史のどこかで、当事者に感謝されるほど本紙の先輩がしっかりと取材していたことを思い、使命感のようなものを覚えた。
¶
20年以上前に、群馬県・法師温泉長寿館を取材した。2月か、3月の冬から春にかけての時期で、長寿館に向かう山々や道路脇には白い雪が積もっていた。乗客のまばらなバスはゆっくりと細い山道を分け入っていく。「本当にこんなところに宿があるのか」と窓の外を眺めながら、なんだか心細くなった。
やがて細い道がカーブして、歴史を刻む木造の宿「長寿館」が現れた。宿の周りにはたくさんの客で賑わっており、宿も、客も太陽の光を浴びて、雪の中で輝いて見えた。
長寿館の岡村興太郎さんは囲炉裏の傍で、緊張気味の私にさまざまな話をしてくれた。それはとても古い時代の話で、長寿館の始まりにまつわるものだった。私は断片的にしか理解できずに、早く録音をしながら正式なインタビューを始めたい素振りを見せたが、岡村さんはすぐに察知して「まあ、まあ、まあ」という感じの表情で、「(そんなに焦らなくても)ゆっくりしていきなさい」と笑顔で言っているようだった。夕食をいただいたあと、岡村さんは大好きなお酒の瓶を持ってきた。2人とも赤い顔になりながら色々なお話をしてくださった。
日本秘湯を守る会という言葉を耳にすると、名誉会長の佐藤好億さん、佐藤和志さん、岡村興太郎さんの3人の顔が瞬時に思い浮かぶ。そして今は、星雅彦会長(新潟県・栃尾又温泉 自在館)へと引き継がれ、「旅人の心に寄り添う」という理念が、さらに若い世代へと継承されていこうとしている。
¶
2011年3月11日に発生した東日本大震災直後の5月に、福島県・二岐温泉大丸あすなろ荘を訪れた。東北は地震と津波により未曾有の被害を受けていた。そして福島県は原発という別の問題も存在していた。
佐藤好億さんは、秘湯の宿が地域に存在することの意味や、ブナの原生林、温泉を守っていくこと、そしてこの国におけるエネルギー問題の深い闇と溝の部分まで語っていただいた。
夕方6時から日付が変わる12時まで6時間にわたる取材後、深夜1人で川沿いの温泉に入っていると、地響きのような轟音と大きな揺れを感じた。まだ東日本大震災の余震が間断なく続いている最中だったのだ。
¶
創立50周年座談会には、次世代を担う安部里美さん(山形県・大平温泉滝見屋)、君島永憲さん(栃木県・奥塩原あらゆ温泉渓雲閣)、髙橋大志さん(静岡県・雲見温泉かわいいお宿雲見園)も出席され、新しい歴史を作っていく力を感じた座談会だった。
(編集長・増田 剛)
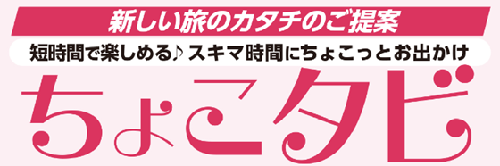




©Yostar.jpg)
©Yostar.jpg)