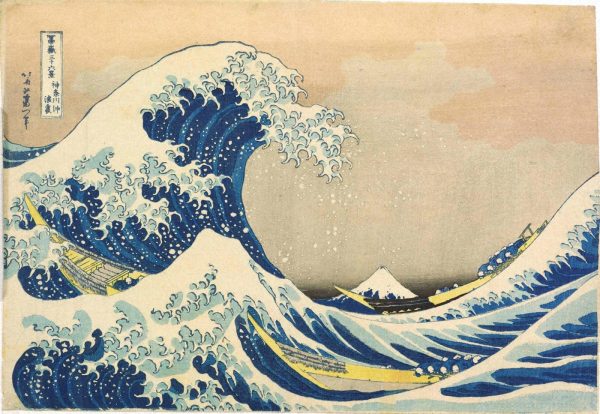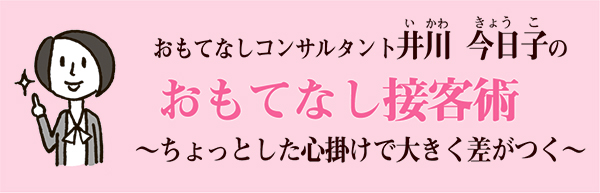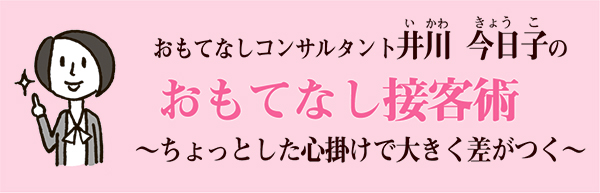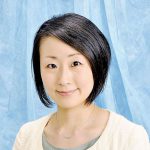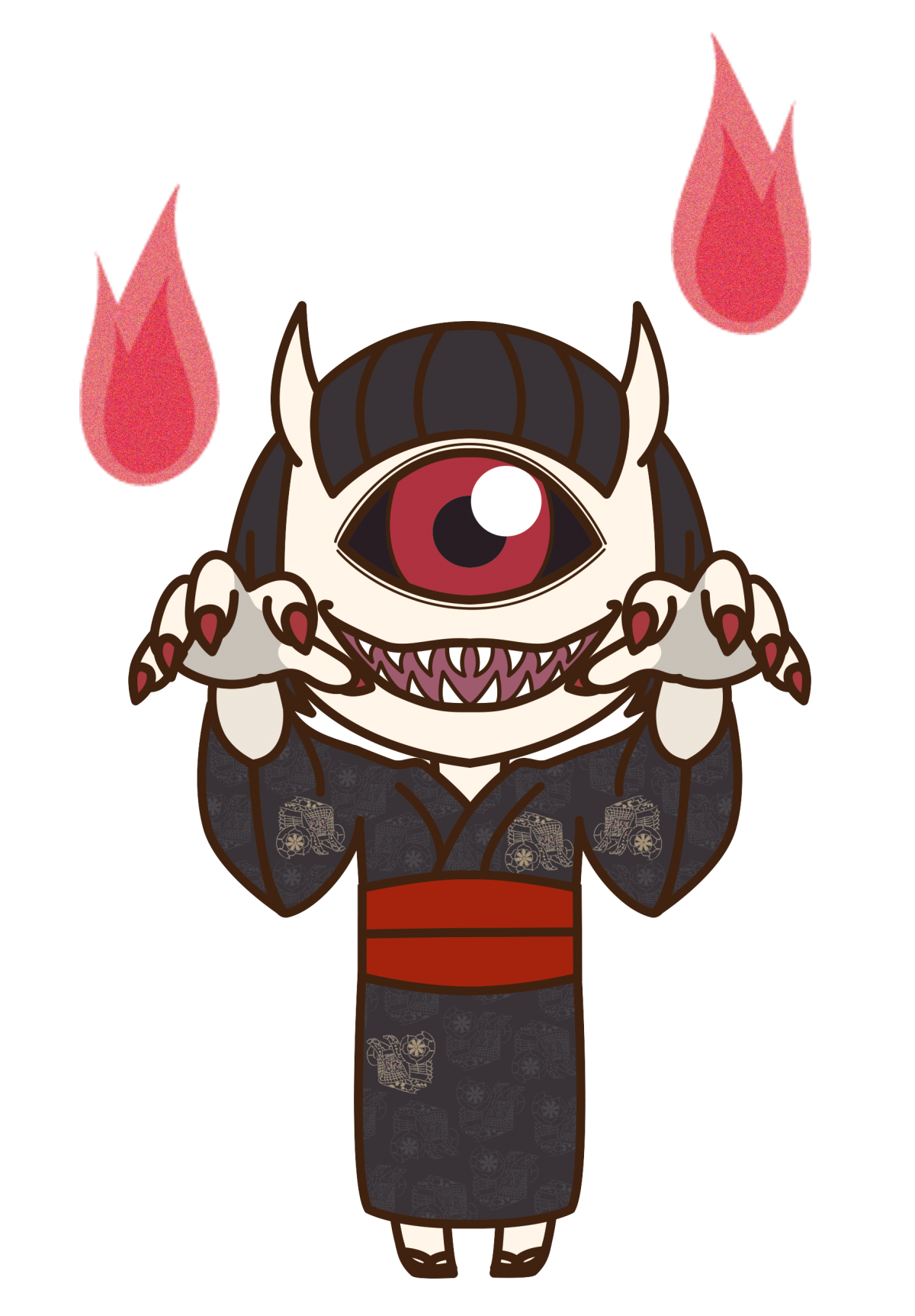2020年4月19日(火)配信

旅の総合メディアを運営するTABIPPO(清水直哉社長、東京都渋谷区)は、半年間で未来の観光に貢献するニューノーマルなビジネスプランを生み出すプログラム「POOLO NEXT(ポーロ ネクスト)」の受講者募集を開始した。公開記念として令和時代の観光について語る無料公開セミナーも開催する。
POOLO NEXTは2030年の観光業界を担う次世代リーダー養成スクールだ。2021年6月から半年かけて受講者一人ひとりが本気で実現したいビジネスプランを考える。観光業界で活躍するビジネスリーダーによる全12回の講義や月1回開催されるメンターとのフィードバック面談を経てビジネスプランを完成させる。募集定員は50人。参加費は通常プラン33万円(税込)、特待生になると受講料が無料または50%引きとなる。
□「POOLO NEXT」3つの魅力
1)他では得られない実践的な知識
全12回の講義では、観光業界の最前線で活躍するビジネスリーダーたちが、本やネットでは得られない実践的で生々しい事業のリアルを伝える。机上の空論ではない、実例に基づくケーススタディによって、ここでしか得られない実践的な知識が身につく。
2)全員が完走するための手厚いサポート
事業構想を1人だけで作り切ることは簡単でない。POOLO NEXTではメンターとの面談や専用のワークシートを通して手厚くサポートする。事業立ち上げの経験がない人でも最後まで完走できる体制を用意している。
3)共に頑張る仲間との出会い
POOLO NEXTにはこれから共に未来の観光を引っ張る次世代リーダーたちが集結する。互いの事業プランを徹底的に討議し、プログラムを通して生まれたつながりは、参加者にとって貴重な経験に。
□無料公開セミナーも開催
第1回 なぜ今、旅行/観光なのか?
日時 :2021年4月27日(火)午後7:30-9:30
使用ツール :Zoomウェビナー
参加費 :無料
ゲスト :
篠塚 孝哉氏(株式会社令和トラベル 代表取締役社長)
太田 英基氏(株式会社スクールウィズ 代表取締役)
内容 :
令和におけるトラベル領域のビジネスチャンスについて考える。海外旅行をターゲットにしている令和トラベルと、日本人の海外留学をサポートするSchool With。現在、非常に厳しいトラベル領域のビジネスへの挑戦と市場をどう捉えているのか深堀りする。
第2回 令和の観光に必要な変革とは?
日時 :2021年5月10日(月)午後7:30-9:30
使用ツール :Zoomウェビナー
参加費 :無料
ゲスト :
鮫島 卓氏(駒沢女子大学 観光文化学類 准教授)
加藤 遼氏(株式会社パソナJOB HUB ソーシャルイノベーション部長)
内容 :
令和における必要な変革と観光/旅行業界に求められていることは何か。観光/旅行業界におけるイノベーションの起こし方についてゲストが語る。