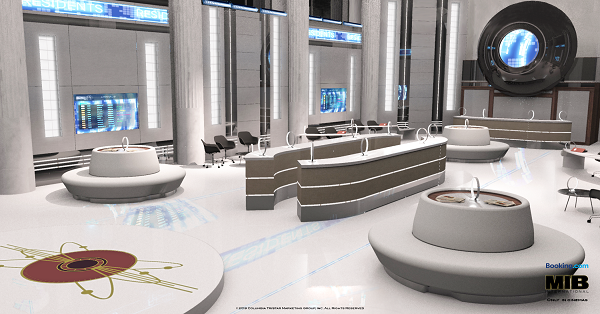2019年5月21日(火) 配信

高品質のおもてなしサービスを提供することで、お客の強い支持を得て集客している宿の経営者と、工学博士で、サービス産業革新推進機構代表理事の内藤耕氏が、その人気の秘訣を探っていく対談シリーズ「いい旅館にしよう! Ⅲ」の2回目は、丸峰観光ホテル(福島県・芦ノ牧温泉)の星保洋社長と、現場責任者が登場して座談会を行った。調理場の意識改革が進み、個人客に対応した「1品出し」のコース料理が高い評価を受け、宿全体にも好影響を与えている動きを探った。
【増田 剛】
◇
――丸峰観光ホテルの歴史を教えてください。
星:父の星保が南会津の田島町(現・南会津町)で1958(昭和33)年からタクシー会社を経営していました。
しかし、マイカーの普及により、「今後タクシー会社は厳しくなる」ことを予想し、父はレストランかドライブイン、旅館の経営を考えていました。県内各地を探すなか、芦ノ牧温泉で旅館が売りに出ていたので買収しました。69年6月のことで、今年50周年になります。
当時は12室程度の小さな宿で、タクシー会社を経営しながら、母が旅館を切り盛りしていました。タクシー会社は82年に売却しました。
――宿の大型化はいつごろからですか。
星:宿を始めて2年目の71年に宴会場と、客室も150人収容に増築しました。73年には5階建ての300人収容に、77年には700人収容と、規模を短期間に拡大していきました。
79年に父が他界しました。それから母の弘子が社長に就任し、81年に5階建てだった本館を7階建てに嵩上げしました。
88年には600畳規模の大コンベンションホールを作りました。91年に大浴場、92年に6室の「離れ山翠」を新設しました。
600畳の宴会場は東北でもあまりなかったので、首都圏から大規模な団体客が当館に訪れました。その後、大型団体が減少していくなかで、大宴会場を細分化し、レストランや料亭街に改修しました。
また、芦ノ牧温泉にも大型旅館が増え、競争激化が進みました。このため、個人客の対応を強化しようと別館を24室の露天風呂付き客室に改装しました。
92年に「離れ山翠」を作ったときから、団体客中心の「本館」、個人客に対応する「別館」、これに「離れ山翠」は高級旅館を目指し、3つのカテゴリーでお客様を受け入れていこうと考えていました。
本館と別館は当時から、仕込みは“セントラル厨房”のスタイルで、盛り付けはそれぞれ「お客様の近くで行う」という大枠の考え方がありました。「離れ山翠」は、団体客とは違う1品ずつ出すコース型の料理を開発して提供していました。
17年4月に母からの社長交代を機に、個人客に対しては、どこの大型旅館でもやっている料理をまとめて出す「お膳出し」から、今の芦田料理長と一緒に「1品出し」のコース料理へと変革を加速させています。
内藤:旅館のほかに飲食業もやっていますが、いつから始めたのですか。
星:2000年に郡山市内で中華レストランを開業しました。
飲食業界はとても厳しく、「これまでやっていた旅館は甘かったな」と実感しました。その後、郡山駅の駅ビルに入居し、今年で15年になります。和食も提供するようになり、失敗も幾つかしましたが、レストラン経営をしていてよかったなと思います。
内藤:旅館の経営が甘く感じられたのはどうしてですか。
星:旅館は基本的に予約があるので決まった料理を提供しますが、飲食店はいつお客様が来て何を注文するか分からないなか、柔軟に対応しなければなりません。需要予測によって人員の配置が必要ですし、駅ビルだと電車の到着時間も頭に入れながらの細かな計算も必要です。そういう習慣は旅館にはありませんでした。
内藤:生産管理の勉強を随分されたと聞きました。
星:若いころから旅館業ではなく、流通業界の勉強会や、工場の生産管理システムのセミナーにも参加するようになりました。
このように飲食業など、さまざまな経験をして社長に就任し、改革の土壌が整いつつあるのを感じます。調理場から本格的に改革を始め、芦田料理長と試行錯誤を続けてきて同じ方向を向いているのもありがたいですね。
芦田:大小の料亭などでのそれまでの経験を評価していただき、団体料理だけでなく、旅館の新しい料理の開発を担う「離れ山翠」で1品出しのお手伝いができるとのことだったので、ここの料理長を10年以上前に引き受けました。
内藤:旅館料理はどのような印象でしたか。
芦田:まず量の多さに驚きました。団体客中心の献立づくりにも戸惑いました。作り置きの提供の仕方も当初は理解できませんでした。
内藤:どうして旅館は作り置きをするのですか。稼働の低いときも作り置きをしますね。……
【全文は、本紙1754号または5月27日(月)以降日経テレコン21でお読みいただけます。】